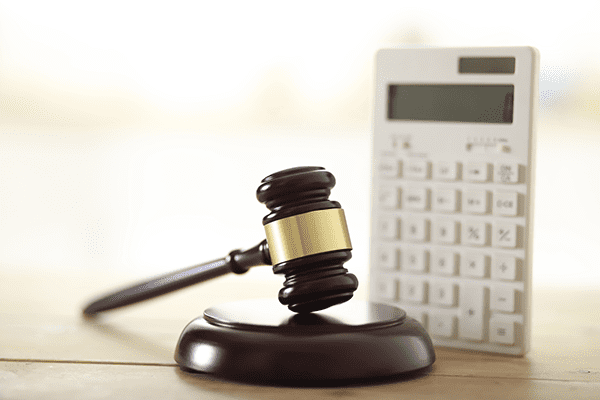遺留分とは、相続での最低限の取り分です。
しかし、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成することはできるため、遺言によって自分の遺留分が侵害される場合もあるでしょう。
この場合には、遺言書などで遺産を多く受け取った相手に対して、「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう請求することです。
では、遺留分侵害額請求は、どのように進めればよいのでしょうか。
この記事では、遺留分侵害額請求について、弁護士がくわしく解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害されている相続人が遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することです。
遺留分については、侵害されている本人が請求して初めて認められますので、必ず請求(遺留分を請求する意思表示)をしてください。
また、遺留分侵害額請求には時効があるため注意が必要です。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法第1048条:遺留分侵害額請求権の期間の制限)
遺留分侵害額請求で知っておきたい遺留分の基本
遺留分侵害額請求をする前に、遺留分の基本について理解しておきましょう。
遺留分とは
たとえば、遺言書に「相続財産はすべてAさんへ」と書かれていたとします。
この「Aさん」が親族ならまだしも、赤の他人だったなら遺族は愕然としてしまうでしょう。
実は、こういったケースは少なくありません。
すべての財産を一人の方へという場合もあれば、ご親族の内一人だけに財産を渡さないといった場合もあります。
このような場合、法律では一部の法定相続人に最低限の権利を保障しています。
これが「遺留分」です。
遺留分を請求できる法定相続人は「被相続人の配偶者」「子(直系卑属)」「父母(直系尊属)」です。
遺留分の割合の例は次のとおりです。
- 直系尊属(例えば両親)のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
- それ以外の場合:相続財産の2分の1
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分のある相続人・ない相続人
遺留分は、すべての相続人にある権利ではありません。
遺留分のない相続人は、たとえ亡くなった人(「被相続人」といいます)が自分に一切遺産を相続させない旨の遺言書を遺していたとしても、遺留分侵害額請求をすることは不可能です。
まず、次の相続人には遺留分の権利があります。
- 配偶者である相続人
- 第一順位の相続人:被相続人の子。子が被相続人より先に亡くなっている場合には、その亡くなった子の子である孫
- 第二順位の相続人:被相続人の親。親がいずれも被相続人より先に亡くなっている場合には、祖父母
一方、兄弟姉妹や甥姪は第三順位として相続人になることはあるものの、これらの者には遺留分がありません。
遺留分割合
遺留分割合は、原則として2分の1です。
ただし、第二順位の相続人である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合には、例外的に3分の1とされています。
これに法定相続分を乗じて、個々の遺留分を算定します。
たとえば、相続人が配偶者と長男、二男である場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。
- 配偶者:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1
- 長男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
- 二男:2分の1(全体の遺留分)×4分の1(法定相続分)=8分の1
つまり、仮にこのケースで「全財産を長男に遺贈する」との遺言書が存在した場合、二男は全財産の8分の1にあたる遺留分を支払うよう、長男に対して請求できるということです。
遺留分算定の基礎となる財産
侵害された遺留分を正確に算定するためには、遺留分算定の基礎となる財産について理解しておく必要があります。
遺留分算定の基礎となる財産とは、遺留分割合を乗じることとなる金額です。
たとえば、上の例で遺留分算定の基礎となる財産が8,000万円であれば、二男が長男に対して請求できる金額は1,000万円となります。
遺留分算定の基礎となる金額は、原則として被相続人の遺産総額から負債総額を控除した額です。
また、次の生前贈与も遺留分算定の基礎に算入されます。
- 相続人以外への生前贈与:相続開始前1年間にしたもの
- 相続人への生前贈与:相続開始前10年間にしたもののうち、婚姻や養子縁組のためにしたものと、生計の資本としてしたもの
ただし、これら以前にした贈与であったとしても、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与であれば、遺留分算定の基礎に算入されます。
この遺留分算定の基礎となる金額を正確に算定することは容易ではなく、金額の算定が争点となるケースも少なくありません。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求は、相手方(受遺者または受贈者)に対する意思表示をもってすれば足りますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示にならない可能性があります。
調停の申立てとは別に、内容証明郵便等により意思表示を行っておくのが確実です。
なお、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも遺留分侵害額請求権を行使する旨を知らせておくべきです。
内容証明郵便による意思表示を行った後は、相手方と協議交渉をすることで遺留分の侵害額を支払ってくれる場合もありますが、そう簡単には支払ってくれない場合もあります。
遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合は、家庭裁判所で話し合う「調停」、それでも応じてもらえない場合には裁判を起こす「訴訟」という方法があります。
では、それぞれの方法について順を追って解説します。
ここでは、被相続人である父が「全財産を長男に相続させる」旨の遺言書を遺しており、二男が遺留分侵害額請求を検討しているとの前提で解説しましょう。
相続人同士で話し合う
遺留分を侵害する遺言書が存在した場合、話し合いで解決できる可能性もあります。
たとえば、父の死亡後に遺言の存在を知った長男が二男を気の毒に思い、「遺言では自分が全部相続することになっているけど、A銀行の預金は二男が受け取ればよい」などと遺言書とは異なる分割に応じてくれる場合もあるでしょう。
また、二男から「自分が何も相続できないのは納得できない」などと長男に申し入れたところ、遺留分侵害額請求にまで発展することを避けたい長男が、二男に対していくらかの金銭を支払う提案をすることも考えられます。
内容証明郵便を送付する
ここから先は、長男が自発的には遺留分の支払いに応じない場合の対処方法です。
まず、二男から長男に対して遺留分を請求する旨の意思表示を行います。
この意思表示の方法は法律で制限されているわけではなく、口頭や普通郵便などであっても請求の効力は生じます。
しかし、「言った・言わない」のトラブルを避けるため、内容証明郵便で意思表示をすることが多いでしょう。
内容証明郵便とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度です。
遺留分侵害額請求には時効がありますが、内容証明郵便を送ることで時効期間内に請求したとの証拠が残ります。
内容証明郵便で請求をした遺留分の支払いに長男が応じれば、この時点で解決です。
調停を申し立てる
内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしても長男が支払いに応じなかったり、遺留分算定の基礎となる財産について意見が食い違ったりする場合もあるでしょう。
この場合には調停を申し立て、解決を図ります。
調停とは、家庭裁判所で行う話し合いです。
話し合いとはいえ両者が顔を合わせて行うのではなく、調停委員が交互に意見を聞く形で話し合いを調整します。
訴訟を提起する
調停で意見がまとまらない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
訴訟になれば、裁判所が諸般の事情を考慮のうえ支払うべき遺留分侵害額を決定します。
遺留分減殺請求からの改正点
遺留分侵害額請求は、以前「遺留分減殺(げんさい)請求」という名称でした。
これが、2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法により名称が変わり、その性質も改められています。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求との最大の違いは、「現物返還であるか金銭の支払いであるか」という点です。
以前の遺留分減殺請求では、現物返還が原則とされており、金銭での返還は例外的な位置づけでした。
たとえば、遺産が4,000万円相当の土地、2,000万円相当の建物、預貯金2,000万円の計8,000万円であり、全財産を相続した長男に対して遺留分割合が4分の1である二男が遺留分減殺請求をしたとします。
この場合には、「土地の持分4分の1、建物の持分4分の1、預貯金のうち500万円」が自動的に二男のものとなることが原則でした。
しかし、遺留分減殺請求をするような間柄で土地や建物が共有になれば、後に別のトラブルの原因となりかねません。
そこで、遺留分侵害額請求は金銭での支払いに一本化されました。
同じケースで二男が長男に対して遺留分侵害額請求をした場合には、二男が長男に対して2,000万円(=8,000万円×4分の1)の金銭債権を持つこととなります。
遺留分侵害額請求をする際のポイント
遺留分侵害額請求をする際には、次のポイントを踏まえて行いましょう。
遺留分制度についてよく理解しておく
遺留分は、請求できる相続人の範囲が限られていたり、金額の計算がやや複雑だったり、時効があったりと、注意すべき点が少なくありません。そのため、遺留分侵害額請求をする際には、まず遺留分制度についてよく理解しておく必要があるでしょう。
時効期間内に請求をする
遺留分侵害額は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害の事実を知ったときから1年以内に行わなければなりません(民法1048条)。
また、たとえ被相続人が死亡したことや遺言書の存在を知らないまま時間が経過したとしても、相続開始の時から10年を経過すると、もはや遺留分侵害額請求をすることはできません。
そのため、遺留分侵害額請求は、相続の開始や遺留分を侵害する遺言書などの存在を知った後できるだけ速やかに行う必要があります。
内容証明郵便で請求する
上記のように、遺留分侵害額請求には時効が設けられています。
そのため、時効期間内に請求した証拠を残すため、内容証明郵便で請求をするとよいでしょう。
遺留分侵害額請求をする方法は法律で規定されていないため、口頭や普通郵便などであるからといって請求の効果が生じないわけではありません。
しかし、口頭や普通郵便であれば相手が「時効期間内に請求されていない」などと主張した場合に、確かに時効期間内に請求したとの証拠を示すことが困難です。
そのため、実務上ではよく内容証明郵便が使用されています。
弁護士へ依頼する
遺留分侵害額請求自体は、ここまでの留意点さえ踏まえればさほど難しい手続きではありません。
しかし、実際には、遺留分侵害額請求をした後で遺留分算定の基礎となる財産の額などについて双方の主張が食い違ったりするなどし、解決にいたるまでに難航するケースは少なくありません。
自分で交渉をした場合には、相手の提示額が適切であるのか判断が難しかったり、相手の有利な内容で合意してしまったりする可能性があります。
また、請求をしたにもかかわらず、相手が一向に支払いをしない場合もあるでしょう。
このような事態を避けるため、遺留分侵害額請求は弁護士へご相談ください。
遺留分侵害額請求はAuthense法律事務所へお任せください
自分にとって不利な内容の遺言書が遺っていた場合には、遺留分侵害額請求が選択肢の一つとなります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された自分の遺留分相当額を金銭で支払うよう、遺産を多く受け取った相手に対して請求する手続きです。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年(令和元年)7月1日に施行された改正民法により名称が変わり、内容も多少変更されています。
遺留分侵害額請求を自分で行えば、請求を無視されたり支払額の算定において不利な内容で合意してしまったりするかもしれません。
そのような事態を避けるため、遺留分侵害額請求は弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所では相続トラブルの解決に力を入れており、これまでも多くの遺留分侵害額請求をサポートしてきました。
遺留分侵害額請求をご希望の際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力