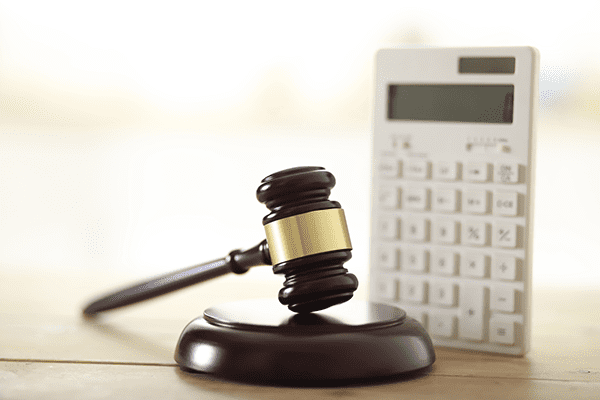M&Aにはさまざまな方法がありますが、事業承継ではもっともシンプルな「株式譲渡」によることが多いでしょう。
では、M&Aによる事業承継にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
ここでは、M&Aによる事業承継について弁護士が詳しく解説します。
事業承継の3パターン
事業承継には、主に次の3パターンがあります。
- 親族内承継
- 親族外承継
- M&A
初めに、それぞれの概要を解説します。
親族内承継
親族内承継とは、経営者の子など親族に事業を承継させる方法です。
中小企業においては、もっとも多い事業承継方法であるといえるでしょう。
しかし、親族内に適任者がいない場合はこの方法は選択できません。
また、経営者としての資質や能力に欠ける親族を無理に経営者へ押し上げるなどすると、社内に軋轢が生じるリスクがあります。
親族外承継(社内承継)
親族外承継(社内承継)とは、社内の役員や従業員に事業を承継させる方法です。
長年ともに働いてきた人の中から後継者を選定できるため、信頼できる人物を選びやすいしょう。
また、社内の雰囲気が大きく変わりにくいこともメリットです。
一方で、親族外承継では承継の対価がハードルとなることが少なくありません。
親族外承継では、株式会社であれば自社株を無償譲渡するのでなく、適正な対価で売買することが多いのですが、後継者候補が株式を買い取るだけの資金を有していないことが少なくないためです。
また、現経営者の個人保証を外しにくいこともデメリットだといえます。
M&A(社外承継)
M&Aとは「Mergers and Acquisitions」の略であり、会社の合併や買収を意味します。
後継者不足が叫ばれる昨今、M&Aを事業承継に活用する企業が増えています。
M&Aの方法には次のものなどがあります。
- 株式譲渡
- 事業譲渡、会社分割
- 株式交換、株式移転
- 合併
必要に応じて適切な方法を選択する必要があるでしょう。
株式譲渡
株式譲渡とは、売り手が買い手に株式を売却する方法です。
事業承継で用いられる場合は、現経営者が所有する自社株式を他社へ売却する形で行うことが多いでしょう。
株式譲渡は比較的手続きが簡単で迅速に完了できるため、中小企業のM&Aでよく用いられます。
株式譲渡では対象会社の全事業が承継されるため、簿外債務・偶発債務が存在する場合にはそれらも併せて承継されてしまいます。
そのため、後ほど解説をするデューデリジェンスが特に重要な意味を持つでしょう。
事業譲渡、会社分割
事業譲渡は、売り手の「全部」または「一部」の事業を買い手に売却する方法です。
会社の事業に関する個々の権利・義務を取引行為として譲渡することにより、当該事業を承継します。
一方、会社分割は、企業の全部または一部の事業を分割して、新たに設立する企業(新設分割)又は既存の企業(吸収分割)に承継する方法です。
手元に残したい事業を経営者自身が選別したい場合や、複数の後継者にそれぞれ別の事業を引き継がせたい場合、事業承継においてこれらの方法が用いられることがあります。
株式交換、株式移転
株式交換は、既存の会社にかかる全株式を他の会社に取得させて完全親会社とする方法です。
一方株式移転は、既存の会社にかかる全株式を新たに設立する会社に取得させて完全親会社とするものです。
これらは経営統合や事業拡大、ホールディングスを設立する場合などに用いられる方法です。
既に設立済みの会社を完全親会社にする場合は株式交換が利用され、新たな会社を設立し完全親会社とする場合は株式移転が利用されます。
合併
企業同士を結合して1つの企業とすることを合併といいます。
合併前のそれぞれの会社が消滅して1つの新会社が設立される新設合併と、1つの会社を存続会社として他の会社はその会社に吸収される吸収合併とが存在します。
合併は包括承継であり、消滅会社の権利義務の一切を存続会社が承継することになります。
そのため、個々の財産の移転手続きが不要です。
たとえば、後継者がいない事業では、建物などの事業用財産を有効活用したり従業員の雇用を確保できたりするほか、存続する会社にとってはより早く効率的に新事業に進出することができます。
一方で、資産のみならず負債、さらには潜在的債務や偶発的債務をも承継してしまうため、存続会社としてはリスクが多くあります。
そのため、M&Aを行って株式譲渡により対象会社を完全子会社にし、数年を経てから潜在債務や偶発債務が存在しないことを確認して合併を行うことが少なくありません。
このように、合併には法定の手続きが必要であり、また 従業員の雇用関係や債権者等、多数の関係者の利害もとの経済状況に考慮する必要もあります。
そのため、法律や税務の観点からの検討が求められ、実務上事業承継において合併が利用されるケースは多くはありません。
細分化された同族会社を整理する場合等に用いられることがあります。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
M&A(社外承継)で事業承継をするメリット
M&Aで事業承継をすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
主なメリットは次のとおりです。
社内や親族に後継者候補がいなくても承継できる
親族内承継や親族外承継(社内承継)をしようにも、適任者がいない場合も少なくないでしょう。
その場合、自分の引退と同時の廃業が頭をよぎるかもしれません。
しかしM&Aの場合、社内や親族に後継者候補がいなくても事業を継続させることが可能です。
後継者不足が叫ばれる中、この理由からM&Aを選択する企業は少なくありません。
創業者利益が獲得できる
M&Aでは、自社を売却するにあたって対価が得られることが一般的です。
そのため、これまで自社株を持っていた経営者がまとまった利益を獲得することができます。
これまで骨身を惜しまず育て上げてきた企業がよい条件で売却できれば、経営者として喜ばしいことでしょう。
また、得た利益を元手に新たなビジネスを始めたり、ビジネスから引退してセカンドライフを送ったりするなど、将来の選択肢が広がります。
個人保証から解放される
会社が金融機関から借り入れをする際、経営者個人が保証をするケースは珍しくありません。
そして、親族内承継や親族外承継(社内承継)の場合はこの個人保証の切り替えができず承継のハードルとなったり、経営者を退いたにもかかわらず引き続き保証を求められたりする可能性があります。
一方、M&Aでは、個人保証を外すよう買手企業が金融機関と責任を持って交渉する旨などを織り込むことが多いでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
M&A(社外承継)で事業承継をするデメリット
M&Aで事業承継をすることには、デメリットもあります。
主なデメリットは次のとおりです。
企業文化が承継できない可能性がある
M&Aによって事業承継を行うと、会社の経営母体がこれまでとは違う企業や個人となります。
そのため、企業文化までの承継は難しく、企業風土や社内の雰囲気が大きく変化する可能性があります。
また、それにより従業員が退職することもあるかもしれません。
必ずしも理想の買い手が見つかるとは限らない
M&Aでは、必ずしも理想の買い手が見つかるとは限りません。
購入を希望する企業から問い合わせがあったとしても、たとえば企業としての方向性が大きく違ったり、対価について意見がまとまらなかったりする可能性があるでしょう。
できるだけ妥協しない条件での買い手を見つけるため、M&Aでの買い手企業は時間を十分にかけて探すことをおすすめします。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
M&A(社外承継)で事業承継をする流れ
M&Aはどのように進めていけばよいのでしょうか?
基本的な流れは次のとおりです。
専門家に相談をする
M&Aでの事業承継を視野に入れたら、早期に専門家へ相談します。
専門家へ相談することでM&Aのサポートが受けられるのみならず、進め方やM&Aによる事業承継が本当に自社に向いているかなどのアドバイスも受けられることでしょう。
Authense法律事務所には、M&Aによる事業承継に詳しい専門家が多数在籍しています。
M&Aでの事業承継をご検討の際には、Authense法律事務所までご相談ください。
買い手候補を探す
M&Aで事業承継を行う方向に決めたら、買い手候補を探し始めます。
M&Aで買い手候補となる企業を探す方法には、次のものなどが挙げられます。
それぞれ一長一短があるため、専門家へ相談のうえ自社に合った方法を選択してください。
- 知人や取引先からの紹介
- M&A仲介会社への依頼
- M&Aマッチングサイトの活用
- 金融機関への紹介依頼
買い手候補との交渉を行う
買い手候補からの問い合わせがあったら、買い手候補と基本的な条件交渉などを行います。
この段階では決裂するケースも少なくありません。
なお、M&Aの交渉にあたっては、自社の財務状況などを開示することとなります。
そのため、自社の情報を開示する前に秘密保持契約を取り交わすことが一般的です。
基本合意を締結する
M&Aをする方向で引き続き詳細な交渉を進めることに合意した場合は、両者間で基本合意を締結します。
基本合意では、この段階までに合意が成立した事項や、この後のプロセスに関する事項などを盛り込みます。
デューデリジェンスが実施される
基本合意の締結後には、買い手企業によるデューデリジェンスが実施されます。
デューデリジェンスとは、M&Aに先立って相手企業の財務状況や相手企業が抱えるリスクなどを徹底的に調べ洗い出す手続きです。
デューデリジェンスには次のものなどが存在します。
- 事業デューデリジェンス
- 財務デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- 法務デューデリジェンス
- 人事デューデリジェンス
M&Aをすると、売り手企業の資産や債務、リスクなどは原則としてすべて買い手企業に引き継がれます。
そのため、買い手企業がM&Aの成立後に不測の損害を被ることを避け、また適正な売買価格を選定するためにデューデリジェンスが行われます。
最終条件の交渉をする
デューデリジェンスを終えたら、その結果を踏まえ最終交渉に入ります。
最終交渉ではM&Aの対価や時期、その他条件面などについて細かなすり合わせを行います。
最終契約を締結する
最終条件の交渉がまとまったら、最終契約を締結します。
これで手続き上でのM&Aは完了となります。
この後は事業の統合や整理、許認可の引き継ぎ、各種手続きなど実務的な統合作業が進みます。
適宜専門家によるサポートを受けながら進めていきましょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
M&A(社外承継)での事業承継を成功させるポイント
M&Aでの事業承継を成功させる主なポイントは次のとおりです。
企業の価値を磨く
自社をよりよい条件で買ってもらうには、買い手が「買いたい」と希望する企業でなければなりません。
そのため、M&Aによる事業承継を決めたら、企業価値を高めるためのブラッシュアップを行いましょう。
たとえば、利益率の向上や役員借入金・役員貸付金の解消、社内規程の整備、未払い残業代の解消などが挙げられます。
企業価値のブラッシュアップは、一朝一夕にできるものではありません。
そのため、課題を絞って1つずつ問題を解決し、企業価値の向上を目指しましょう。
早くから準備に取り掛かる
M&Aによる事業承継を検討したら、できるだけ早くから準備に取り掛かることをおすすめします。
もっとも早くから取り組むべきことは、1つ上で解説した企業価値の向上でしょう。
企業価値を高めることで、よりよい条件で売却できる可能性が高くなるためです。
また、専門家への相談も早期に行っておくことをおすすめします。
M&Aによる事業承継を数多く見てきた専門家へ相談することで、自社が今行うべきことが明確となるためです。
そして、早くから買い手の募集を始めることで、希望に近い買い手を選定しやすくなるでしょう。
信頼できる外部の専門家に相談する
M&Aによる事業承継を検討したら、信頼できる外部の専門家に相談をすることがおすすめです。
初めて自社を売却しようとする場合は何から始めればよくわからないことが多いうえ、本当にM&Aが最適な方法であるのかなど非常に悩ましいことでしょう。
Authense法律事務所はM&Aによる事業承継のほか、親族内承継や親族外承継(社内承継)についても豊富な実績があります。
そのためM&Aありきではなく、多様な方法の中から自社にとって最適なプランについてアドバイスすることが可能です。
事業承継でお困りの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
情報漏洩に注意する
M&Aによる事業承継を検討している際は、情報の漏洩に特に注意しなければなりません。
なぜなら、M&Aについて従業員が持つイメージはさまざまであるためです。
たとえば、M&Aに関して「従業員が解雇される」「会社の業績が悪いときに身売りをする手段」などと思い込んでいる場合もあるでしょう。
経営陣の知らないところでこのような噂が広まり混乱が生じてしまうと、退職者が急増して事業が立ち行かない事態となるかもしれません。
そうなると企業価値が低下してしまいかねず、M&Aの交渉が決裂するリスクも生じます。
そのため、M&Aに関する情報は特に慎重に取り扱い、最終的に相手企業と合意が成立してから慎重に開示をすることをおすすめします。
M&A(社外承継)での事業承継はAuthense法律事務所へご相談ください
事業承継のうちもっとも多い方法は親族内承継でしょう。
また、信頼できる役員や従業員など社内の人物に事業を承継する場合もあります。
しかし、そもそも親族や社内に適任者がいないとこれらの承継は実現することができません。
そこで増えているのがM&Aによる事業承継です。
M&Aによる事業承継では、創業者利益を得やすいことや個人保証を外しやすいことなどのメリットがあります。
ただし、必ずしも理想の買い手が見つかるとは限らないことや、企業風土が承継されない可能性があることには注意する必要があるでしょう。
M&Aでの事業承継を成功させるためには、弁護士などの専門家へご相談ください。
Authense法律事務所では、M&Aによる事業承継のサポートに力を入れています。
事業承継の方法でお悩みの際やM&Aでの事業承継をご検討の際は、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力