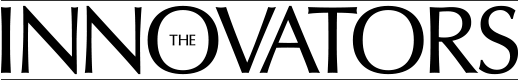創建から1200年以上の歴史を誇る清水寺。これまでにおよそ10回にわたって火難に遭っている。
「清水寺は預かっているだけ」「次世代にしっかりとした形でお渡しするのが自分の役目」と語る現貫主の森清範師に、これまでどのように先人たちが清水寺を守り続けてきたのか、話を聞いた。
取材/元榮太一郎(本誌発行人) Taichiro Motoe・山口和史(本誌編集長) Kazushi Yamaguchi
文/山口和史 Kazushi Yamaguchi 写真/西田周平 Shuhei Nishida
かつて10回遭難した「火災」の恐ろしさ
- 1200年以上の伝統を持つ清水寺の貫主を務める、この責任は大きい。たとえば参拝者の事故。せっかく参拝に訪れても、施設の不備や不注意で取り返しのつかないケガをさせてしまったら、大問題になりかねない。
森師: 参拝にお見えになる方々に事故がないように切に気をつけています。気をつけていても、事故が起こるときは起こるんですけれども、起こらないようにというそんな願いを切に持っています。
- もっとも恐ろしいのは火災だろう。木造建築は、一度火に覆われてしまえばすべてが灰燼に帰してしまう。実際、1200年の長い歴史のなかで、清水寺はおよそ10回、すっかり焼ける火難に遭っている。
森師: そのたびに我々の先輩方がすぐに建て直してくれて現在があります。それぞれの事情が違うにしても、先輩方が努力を重ねて現在へと清水寺を繋いでくれました。これは当時の皆さんが、大変なご尽力を各時代において重ねていただいて、そして参拝の皆さんが来てくださって、ありがたいことに現在があり、おかげさまで最後の火事から約400年も無事に過ごせているんです。
この400年、無事に来ている諸堂伽藍を、粗相のないようになんとか火の粉から救って無事に次の世代に渡していかなくてはならない。そんな強い思いがありますね。
「応仁の乱」からの復興の歴史

- 清水寺が特に大きなダメージを受けたのは、やはり応仁の乱(1467~1477年)だった。
森師: 応仁の乱で京都の街はほぼすべてが焼けました。みんな焼けたんです。清水寺も焼けてます。麓の下町から兵火が広がって焼けているのですが、応仁の乱の後、お寺の復興ということで、願阿上人という勧進僧が清水寺に入ってこられました。
- 現在の富山県の漁師の家に生まれたと伝えられる願阿上人は、一遍が興した鎌倉仏教の一つ時宗の教えを受け、遊行の勧進僧となった。勧進僧とは、諸国を巡って寺院や神社の造立や修復、仏像や鐘の製作から橋梁の建設など、人々の生活に必要な施設の建設に必要な資財を募る僧侶を指す。この願阿上人が、戦争による火災で全焼した清水寺を建て直すために奔走した。
森師: 全国を巡って勧進による寄附を集めて清水寺を建て直そうとした願阿上人が、手始めに作ったのが釣り鐘なんです。清水寺は京都の街を見下ろす場所に建っています。この高い位置から鐘の音を京都の街へ響かせて、『もう戦争なんてやめよう。京都の人たちよ、心をひとつにして復興しよう』という願いを込めて、釣り鐘をはじめに作ったんですね。
- 願阿上人の勧進により1478年(文明10年)に鋳造された鐘は、現在、重要文化財として宝物殿に保管されている。
森師: 清水寺を再建すると言っても一人ではできません。さまざまな方が賛同者となっています。願阿上人の勧進活動を引き継いだ御坊にお堂を寄進したのが越前の守護大名、朝倉貞景でした。
- 熱心な観音信仰の信者だった貞景が、清水寺のために建てたのが朝倉堂だ。1510年(永正7年)に完成し、本尊の観音菩薩が安置されている。
森師: でも、この立派にできたお堂も、1629年(寛永6年)に火事ですっかり焼けてしまうんですね。
- およそ10回、全焼している清水寺だが、最後に大きく焼失したのがこの寛永の大火だった。本堂をはじめ、奥の院、阿弥陀堂、三重塔などほとんどの建物が焼失している。そして、徳川家光の寄進で再建されたのが、現在境内に見ることのできる諸堂だ。
森師: 京都の大切なお寺が燃えたということで、当時の徳川三代将軍だった家光が幕命をかけて再建築しろと命じたんですね。現在の建物は、火災からわずか4年間で作り上げたんです。すごいスピード感ですね。私は思うんです。こんなに近接して建てられているお堂ですよ。順番に手を付けていたのではこの期間でできないと思うんです。あちこち同時並行的に建築を進めたんだと思うんですね。
となると、大工さんたちとはここにずっと泊まって作業をしていたんでしょう。大工さんだけじゃありませんね。瓦屋さん、石屋さん、壁屋さんといった職人の方々がこの境内で小屋を作って寝起きしたんでしょうね。夜は仕事ができませんから、朝一番に起きてやったんでしょう。そんな先人たちから受け継いだ清水寺を、次世代に繋ぐという責任はやはり大きいですよね。
Profile
森 清範 師
1940年、京都・清水生まれ。1955年に当時の清水寺貫主、 大西良慶の元に弟子入り。1963年、花園大学卒業。真福寺住職を経て1988年に清水寺貫主、北法相宗管長に就任。1995年からは財団法人日本漢字能力検定協会が主催する「今年の漢字」を、清水寺の舞台上で揮毫している。「清水寺まんだら」(春秋社)、「心を摑む」(講談社)、「四季のこころ」(KADOKAWA)など著書多数。