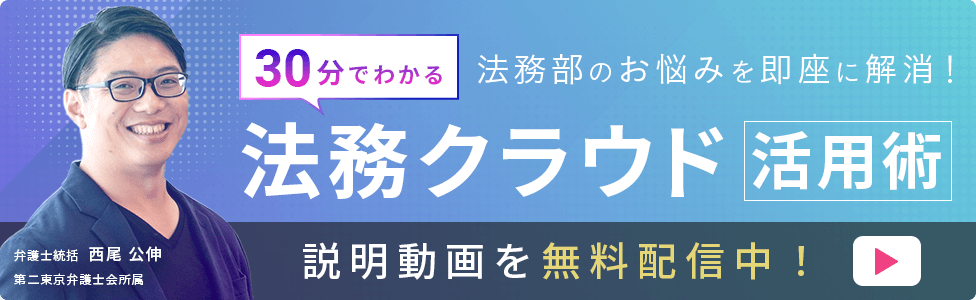税務調査に対して、恐ろしいものとのイメージを持っている企業は少なくないでしょう。
しかし、脱税などをしていなければ、さほど恐れる必要はありません。
では、税務調査ではどのような点がチェックされるのでしょうか?
また、対応時にはどのような点に注意すればよいのでしょうか?
今回は、税務調査について詳しく解説します。
目次隠す表示する
税務調査とは
税務調査には、主に「強制調査」と「任意調査」の2つがあります。
ここでは、それぞれの概要について解説します。
強制調査
強制調査とは、国税局査察部(通称「マルサ」)が行う調査です。
非常に大口な事案や悪質な事案が対象であり、検察官へ告発することを目的として行われます。
裁判所からの令状の交付を受けて事前予告なく行われるものであり、調査を拒否したり日程変更を依頼したりすることはできません。
なお、テレビドラマなどで税務調査が題材とされる場合はこの強制調査が描かれることが多いですが、実際に強制調査が入ることは稀です。
よほど多額かつ悪質な脱税をしていなければ、強制調査の対象となることはないでしょう。
任意調査
任意調査とは、令状などを取らず納税者の同意に基づいて行われる税務調査です。
一般的な企業が税務調査を受ける場合、この任意調査であることがほとんどです。
任意調査は事前に連絡があることが多いものの、現金を多く取り扱う事業者などでは例外的に事前の日程調整なく任意調査が行われることもあります。
ただし、任意調査である以上、その日の都合が悪い場合は別の日に出直してもらうことも可能です。
「任意」との名称ではあるものの、調査自体を拒否したり必要な資料の開示を拒んだりすることはできません。
なぜなら、税務職員には納税者に質問や検査のできる「質問検査権」が認められているためです(国税通則法74条の2)。
税務調査の流れ
税務調査は、どのような流れで進行するのでしょうか?
一般的な流れは次のとおりです。
- 税務署からの調査通知が入る
- 顧問税理士と相談をして事前準備をする
- 調査当日を迎える
- 税務調査を踏まえた指摘事項に回答する
- 税務調査の結果が出る
ここからは、任意調査であることを前提として解説します。
税務署からの調査通知が入る
任意調査では、あらかじめ税務署から調査の通知が入ることが一般的です。
税務代理権限証書に、納税者への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載がある場合には、原則として当該税務代理人に連絡が入ります。
税務調査の日程を調整する
税務調査の事前連絡は、事務所側から調査日時の指定があります。
ただし、必ずしも指定された日程を受け入れなければならないわけではなく、都合が悪い場合は別の日程で調整することも可能です。
顧問税理士と相談をして事前準備をする
税務調査の日程が決まったら、顧問税理士と相談しながら事前準備を行います。
事前準備では、必要書類の準備を行うほか、税務署からなされる質問へのシミュレーションをしておくと安心です。
税務調査で必要となる書類は、次のものなどです。
- 請求書、納品書、領収書
- 契約書、見積書
- 預貯金通帳
- 総勘定元帳、仕訳帳
- 議事録
- 扶養控除申告書や源泉徴収簿など社会保険関連の書類
総勘定元帳や仕訳帳などは会計ソフトに入っていることも多いため、必要に応じて印刷しておいてください。
調査当日を迎える
あらかじめ取り決めた日に、税務調査を受けます。
税務調査にかかる日数は個人事業や小規模事業者で1日から2日程度である一方で、ある程度規模の大きな会社では3日から4日を要することもあります。
顧問税理士がいる場合は専門的な質問には税理士が応えてくれることが多いものの、取引状況など企業が直接回答すべき場面もあります。
税務調査を踏まえた指摘事項に回答する
立ち合いを必要とする調査を終えた後、税務署から追加の質問がなされたり追加での資料提出が求められたりすることがあります。
質問への回答や資料の追加提出を求められたら、速やかに対応しましょう。
そのうえで、税務署からの指摘事項に回答したり、交渉を行ったりします。
この回答や交渉は、原則として顧問税理士が対応します。
税務調査の結果が出る
ここまでの調査を踏まえ、税務署から税務調査の結果が通知されます。
税務調査の着地点は、次のいずれかとなります。
- 申告是認:申告内容に問題が認められないこと
- 修正申告:税務署からの指摘を認めて企業が自ら正しい内容で申告しなおすこと
- 更正:納税者が自ら修正申告をしない場合に、税務署側が申告の誤りを正すこと
是認とならなかった場合は原則として修正申告を行うこととなります。
税務署からの指摘に納得ができない場合は修正申告をせず更正を待つことも1つの手ですが、延滞税や、過少申告加算税が課される可能性もありますので、対応は顧問税理士と慎重に協議した方がいいでしょう。
納得のいかない更正がなされた場合は、処分に不服申立てをして争うことが可能ですが、実務上、覆る確率はかなり低いといわれています。
税務調査で主にチェックされる主なポイント
税務調査では、どのような点がチェックされるのでしょうか?
税務調査で確認されることの多い主なポイントは次のとおりです。
- 決算書で前期との増減が大きい項目
- 売上の期ズレや除外
- 在庫の計上漏れ
- 経営者の公私混同
- グループ間取引
決算書で前期との増減が大きい項目
勘定科目のうち、前期からの増減が大きい項目は重点的にチェックされることが一般的です。
変動が大きい場合は、そこに誤りや不正が隠れている可能性があるためです。
変動があったとしても、正当な事情があれば問題はありません。
そのため、前期の決算から数字が大きく(おおむね10%以上)増減した項目がある場合は、変動した理由を説明できるよう準備しておいてください。
売上の期ズレや除外
税務調査では、売上の「期ズレ」や除外がないかチェックされることが少なくありません。
期ズレとは、本来であれば当期の決算に計上すべき項目を、翌期にずらすことなどです。
また、売上の除外とは、現金で受け取った売上などを計上しないことを指します。
期ズレや除外は、いずれも当期分の税金が不当に減少する結果となります。
これらは非常によくある脱税手法でありミスが多い点であるため、税務調査において重点的に確認されることが多いでしょう。
在庫の計上漏れ
在庫の計上漏れも、税務調査で確認されがちなポイントです。
その期の経費として計上することができる売上原価は、原則として次の式で算定します。
- 当期の売上原価=期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高
そのため、在庫である期末棚卸高に計上漏れがあると、売上原価が実際よりも大きく計上されて、その期分の税金が少なくなる効果をもたらします。
これも、「期ズレ」の一種です。
特に製造業や卸売業など在庫を多く抱えることの多い業種では、在庫の計上漏れによる税額への影響が大きくなりやすいでしょう。
こちらもよくある脱税手法であるうえミスの多い項目でもあるため、重点的に確認されることが多いといえます。
経営者の公私混同
経営者の公私混同も、税務調査で重点的に確認されやすい項目の1つです。
特に個人事業や中小企業では、経営に直接関係のない費用が経費として計上されていることが少なくありません。
経営者の公私混同としては、次のものなどが考えられます。
- 勤務実態がない家族や交際相手などを従業員であるように見せかけて給与を支払っている
- 社宅として経費に計上している住宅に、会社とは関係のない子息や交際相手などが住んでいる
- プライベートで使っている高級車を会社名義で購入している
- プライベートな外食費や旅行代を経費として計上している
- 自宅用の家電や家具を経費として計上している
このような点について税務調査で確認され、指摘されることが少なくありません。
グループ間取引
グループ企業がありグループ間での取引がある場合、税務調査で重点的に確認されます。
なぜなら、グループ企業間での取引は脱税の手法として用いられることが少なくないためです。
たとえば、黒字の企業がグループ内の赤字企業に対して、多額の手数料などを支払うことで黒字企業の利益が圧縮され、納税額を引き下げることなどが想定されます。
そのため、グループ内の取引がある場合は、正当な目的で行っているものであることを特に明確に説明する必要があります。
税務調査の対応ポイント・注意点
税務調査に対応する際は、そのような姿勢で臨めばよいのでしょうか?
最後に、税務調査の対応ポイントや注意点について解説します。
- 事前に顧問税理士と打ち合わせをする
- 誠実に対応する
- 質問されたことにのみ答える
- 手元に残したい書類はコピーしておく
事前に顧問税理士と打ち合わせをする
税務調査の連絡が入ったら、顧問税理士とあらかじめ入念な打ち合わせを行うことをおすすめします。
どのような質問がなされどのような資料が確認されるのかあらかじめ把握しておくことで、調査当日に落ち着いて対応しやすくなります。
顧問税理士がいない場合は、スポットで対応してくれる税理士に対応を依頼することも可能です。
顧問税理士との打ち合わせでは、税務調査へ向けて不安な事項を正直に伝えるとよいでしょう。
税理士が不正に加担することはできないものの、正直に話すことで状況に応じた最善の方法をアドバイスしてもらえる可能性が高くなるためです。
また、当日の流れや質問されそうな項目についてもアドバイスを求め、必要に応じてシミュレーションをしておくと安心です。
誠実に対応する
税務調査当日は嘘をつくことなく、誠実に対応してください。
税務署の調査官は場数を踏んだプロであり、企業がどのように脱税をするのか熟知していることが一般的です。
また、調査官が何も知らないように質問をする場合であっても、訪問前にすでに不正の証拠をつかんでいることも少なくありません。
さらに、税務調査で嘘をついてこれが発覚した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処される可能性があるほか、通常よりもさらに重いペナルティである「重加算税」の対象となる可能性もあります(国税通則法128条2項、68条)。
そのため、税務調査では嘘をつきとおそうなどと考えるのではなく、誠実に対応してください。
質問されたことにのみ答える
税務調査において嘘をつくべきではないものの、聞かれてもいないことまで多くを話す必要はありません。
質問されていないことまで多くを話した結果税務署から話の矛盾を指摘され、痛くもない腹を探られる可能性があるためです。
なお、税務職員が行う雑談には意味があることが多く、単純に雑談を楽しんでいるわけではないことも知っておいてください。
手元に残したい書類はコピーしておく
税務調査の際に、資料の持ち帰りを要求される場合もあります。
この持ち帰りには必ずしも応じる必要はないものの、そのまま持ち帰りに応じることで調査がスムーズに進むことも考えられます。
そのため、顧問税理士のアドバイスを受けつつ、持ち帰りに応じてもよい書類のうち手元に情報を残したい書類についてはあらかじめコピーをとっておくとよいでしょう。
また、税務職員に資料の持ち帰りを認める際は、必ず持ち帰る資料について漏れなく記載をした預かり証の発行を求めてください。
預かり証をもらい忘れてしまったり預かり証の記載に不備があったりすると、預けた資料が返ってこないときに返還の請求が難しくなったり、税務職員にどのような資料を渡したのかがわからず、業務に支障をきたしたりする可能性があるためです。
まとめ
税務調査を怖いものであると感じ、緊張することも多いでしょう。
しかし、事前に顧問税理士へ相談するなどして適切な準備を行うことで、落ち着いて対応しやすくなります。
税務調査で見られやすいチェックポイントを確認し、あらかじめシミュレーションをしておくとよいでしょう。
そのうえで、当日は質問されたことにのみ回答することを心がけ、質問に対しては誠実に回答してください。
税務調査で嘘をつきとおすことは困難であるうえ、嘘が判明した場合のペナルティは小さなものではないためです。
なお、税務署が下した更生に納得がいかない場合は、この処分に対し不服申立てをして争うことが可能です。
税務調査についてお困りの際はまず顧問税理士などの税理士へアドバイスを求め、その後不服申し立てをする場合は税務訴訟に強い弁護士へご相談ください。
記事監修者

森中 剛
(第二東京弁護士会)一橋大学法学部法律学科卒業。元裁判官。企業法務、M&A、労働法、事業承継、倒産法(事業再生含む)等、企業に係わる幅広い分野を中心とした法律問題に取り組む。弁護士としてだけでなく、裁判官としてこれまで携わった数多くの案件実績や、中小企業のみならず、大企業や公的企業からの依頼を受けた経験と実績を活かし、企業組織の課題を解決する多面的かつ実践的なアドバイスを提供している。
-
この記事に関するお問い合わせ Contact
掲載内容や業務に関するお問い合わせは
Contact
こちらまで -
資料請求はこちらから Request Documents
弁護士法人Authense法律事務所の
資料請求
サービス資料をダウンロードいただけます。 -
会員登録はこちらから Sign Up
会員にご登録いただくと、ここでしか読めない
新規会員登録
全ての会員記事をお読みいただけます。