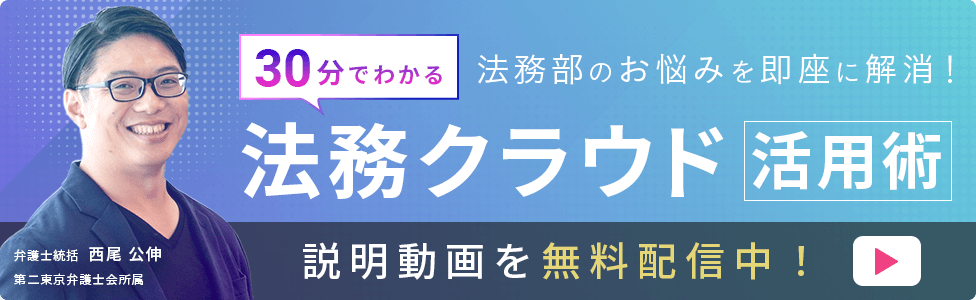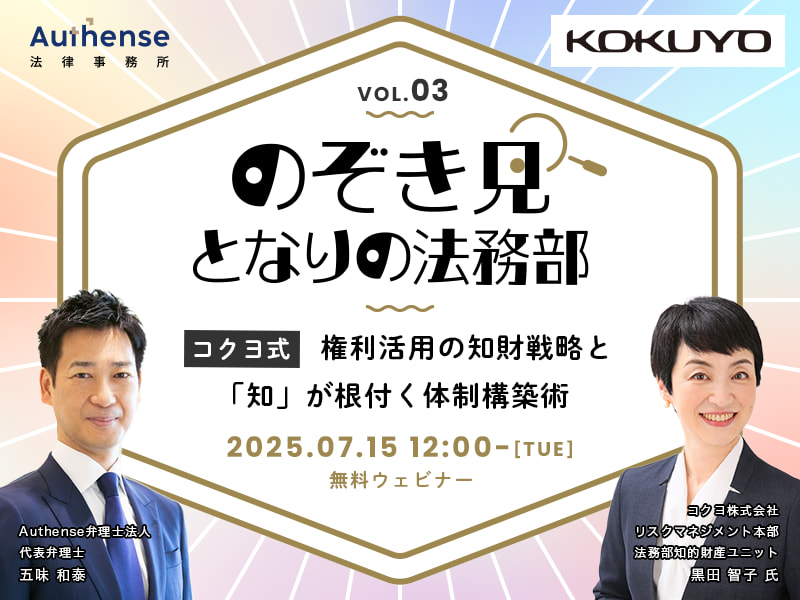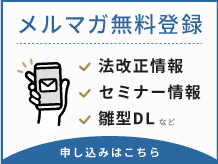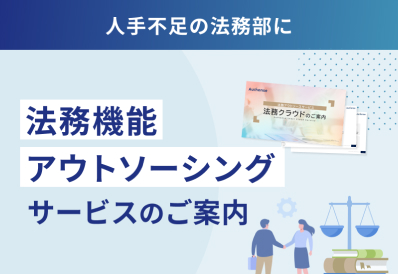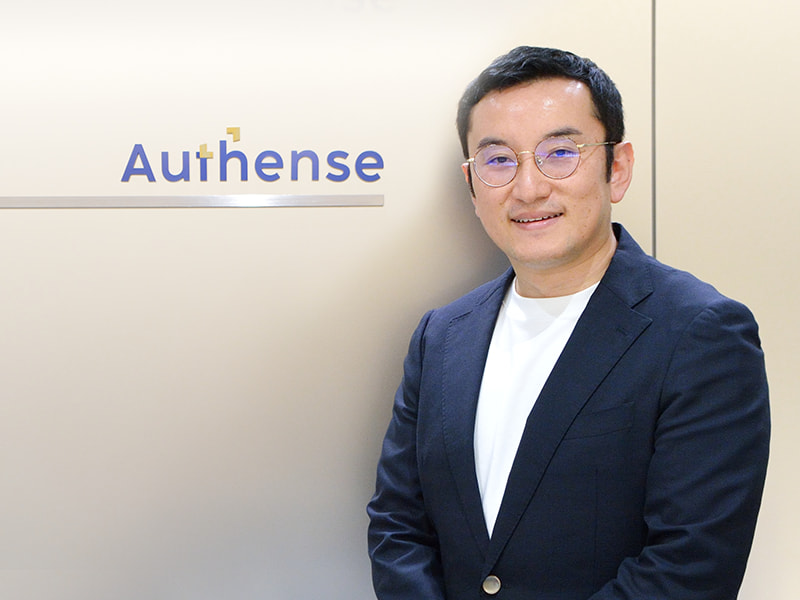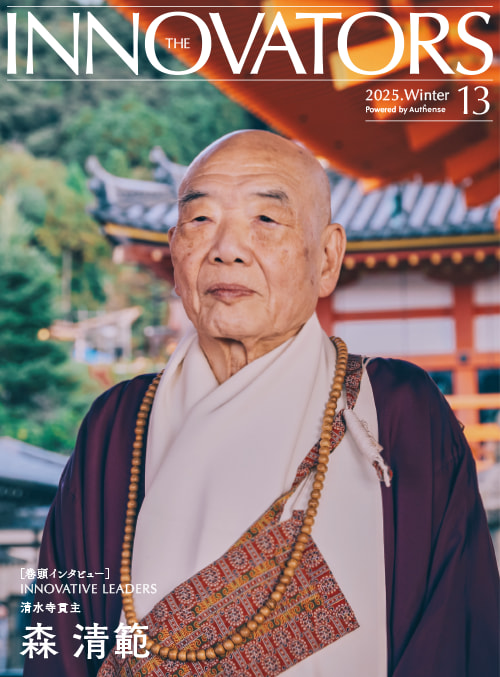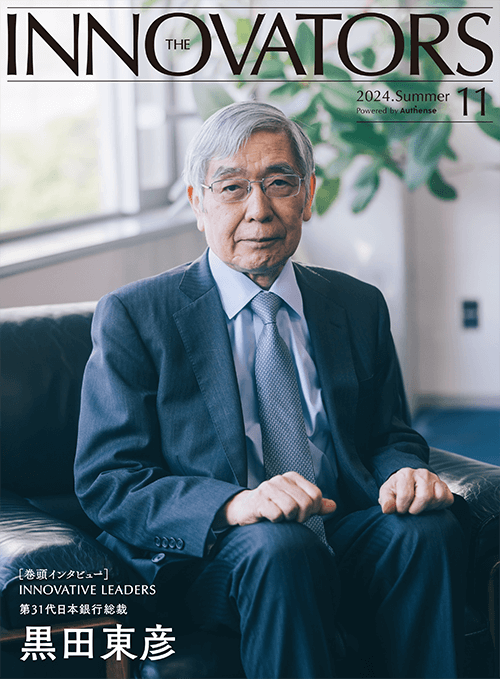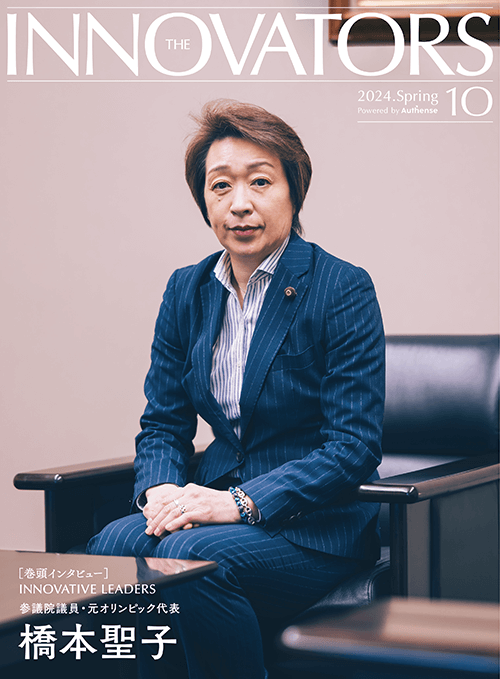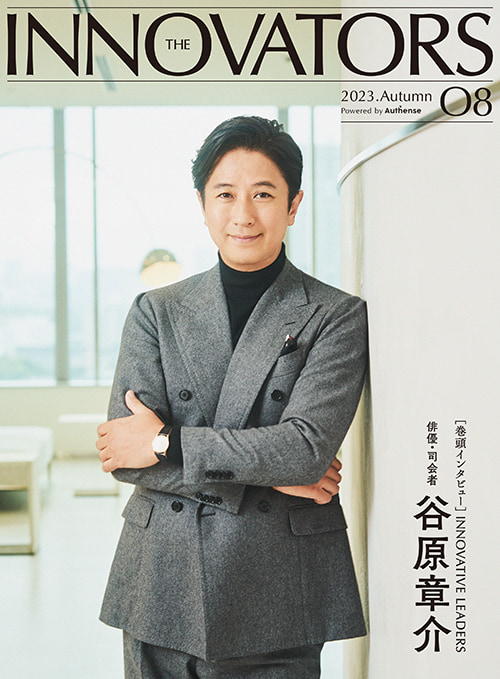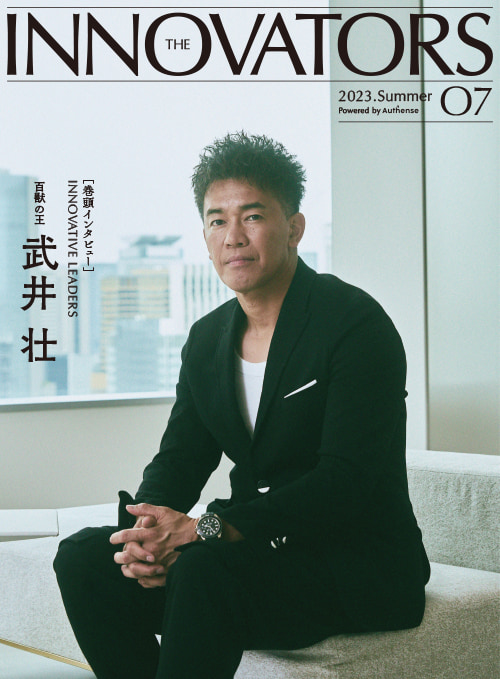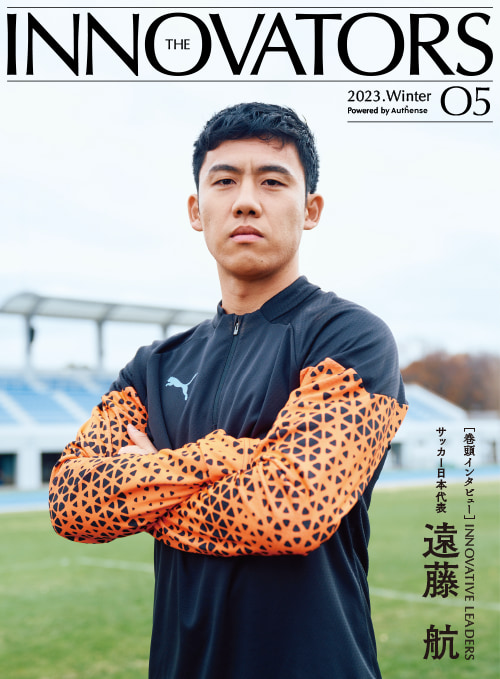近年、ネットやニュースなどでコーポレートガバナンスという言葉を耳にする機会が増えています。 コーポレートガバナンスは企業にとって重要な課題の一つといっても過言ではありません。 今回は、コーポレートガバナンスの概要、目的とメリット、内容と事例を説明します。
目次
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
概要
コーポレートガバナンスという言葉は一義的ではありませんが、東京証券取引所が上場企業を対象に定める「コーポレートガバナンス・コード」の前文において、次のような定義と説明が設けられています。
「・・・『コーポレートガバナンス』とは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する。・・・これらが適切に実践されることは、それぞれの会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与することとなるものと考えている。」(2018年6月1日改訂「コーポレートガバナンス・コード」株式会社東京証券取引所)
ここで謳われているように、コーポレートガバナンスの目的は、①違法・不正な意思決定が行われないための仕組みを構築し会社のリスクや不祥事を防止すること(いわゆる「守りのガバナンス」)と、②業績向上のために適切なリスクをとった経営判断をスピーディーに行うことができるようにすること(いわゆる「攻めのガバナンス」)と整理できます。
Q.ソフトローとしてのコーポレートガバナンス・コードとは?
A.コーポレートガバナンス・コードはソフトローである、と説明されることがあります。
国家が制定した法令であり最終的に国家による強制力が担保されているルールがハードローであるのに対し、国家以外の主体が内容を定め法的な強制力がないルールがソフトローです。
会社法や金融商品取引法はハードロー、東京証券取引所の上場規程やコーポレートガバナンス・コードはソフトローにあたります。
コーポレートガバナンスが重視されることとなった背景
コーポレートガバナンスが日本で重視されはじめたのは、バブル崩壊後の1990年代です。
この頃、国内の大手企業などで不祥事が多発しました。
たとえば、品質チェックの不正や粉飾決算、常態化した労働基準法違反などです。
上場企業では株主の大半は社外の人であり、その企業の役員などではありません。
そのため、仮に企業が品質検査の不正など不祥事が常態化していたとしても、株主がそのような事実を知ることは困難です。
企業が不正を隠蔽している以上、株主は知る由もないためです。
その結果、ある日突然思いがけない不祥事が明るみに出たと同時に株価が暴落し、株主が大きな損失を被る事態が生じました。
このような事態が今後も頻発する可能性があるとなれば、投資にはリスクが高過ぎるため、日本企業へ投資する投資家が減り、日本全体が衰退してしまうでしょう。
また、同時期には、アメリカで世界最大手のエネルギー販売企業が経営不振に陥り巨額の負債を抱えて倒産した「エンロン事件」が起きました。
アメリカでは、このことを契機として、企業の情報開示の信頼性を高めることを目的とした「SOX法」が制定されています。
その後、日本においても、上場企業に対し内部統制報告書の提出を義務付ける金融商品取引法の改正などがなされ、これが「日本版SOX法」と呼ばれています。
このような流れを受けて、東京証券取引所の上場規程などが見直され、コーポレートガバナンスが重視されることとなりました。
コーポレートガバナンスの目的とメリット
上記のコーポレートガバナンス・コードで「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上」が企業にとっての究極的な目的とされているとおり、コーポレートガバナンスは企業価値向上のための手段であると位置付けられます。
バブル崩壊後の約20年余、日本企業の稼ぐ力は諸外国に比べて低迷し、株価指数に表される日本企業の企業価値は、諸外国と比較して一人負けの状況と指摘されています。その中で、企業価値の向上を図る上で乗り越えなければならない課題の多くが、コーポレートガバナンスに関するものと指摘されています。
企業価値の向上は、株主・投資家のメリットであるのみならず、従業員の待遇向上や福利厚生の充実、取引先との良好な関係の維持、地域社会への貢献などにつながるため、当該企業のすべてのステークホルダーのメリットであると言えます。
Q.企業価値とは?
A.企業価値とは、会社の財産、収益力、安定性、効率性、成長力など、株主の利益に資する会社の属性またはその程度をいうものとされています。
企業価値の評価方法は、キャッシュフローや利益をベースにした評価方法(インカムアプローチ)、株式市場の評価をベースにした評価方法(マーケットアプローチ)、純資産をベースにした評価方法(ネットアセットアプローチ)など異なる複数のアプローチがあり、唯一正しい評価方法があるのではなく、評価の目的や企業のステージ・戦略・状況によって、選択的または複合的に適用されるべきものになります。
コーポレートガバナンスのガイドライン
コーポレートガバナンスを強化するといっても、コーポレートガバナンスの強化に向けて行うべきことは膨大であり、拠りどころがなければ適切な対応は困難でしょう。
そこで、コーポレートガバナンスには、さまざまなガイドラインが存在します。
これらのガイドラインは、各種研究会における報告書などに基づいて、コーポレートガバナンス・コードを実践するための実務指針として策定されているものです。※1
それぞれのガイドラインの内容は、次のとおりです。
コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針
「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」は、通称「CGSガイドライン」とも呼ばれます。
これは、コーポレートガバナンスのもっともベースとなるガイドラインです。
そのため、コーポレートガバナンスの強化に取り組む際には、まずはこのガイドラインを熟読するべきでしょう。
CGSガイドラインでは、企業がコーポレートガバナンス・コードに示された原則を実施するに当たって考えるべき内容を示しつつ、「稼ぐ力」を強化するために有意義と考えられる具体的な行動が取りまとめられています。
グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針
「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」は、実際の経営が法人単位ではなくグループ単位で行われている場合を対象にしたガイドラインです。
企業不祥事は子会社などで行われる場合もあるため、子会社を含めたグループ全体でガバナンスを効かせなければなりません。
このガイドラインでは、グルーブガバナンスの実効性を確保するために一般的に有意義と考えられる具体的な行動が示されています。
事業再編実務指針
「事業再編実務指針」は、事業再編に焦点を当てたガイドラインです。
コロナ禍では、多くの企業が危機に陥りました。
また、今後の「ポストコロナ」を見据え、今後事業ポートフォリオの組替えや事業再編の必要性が生じる企業は少なくないことでしょう。
そこでこのガイドラインでは、主に日本企業における事業ポートフォリオの変革を後押しするための効果的な手法を整理しています。
社外取締役の在り方に関する実務指針
「社外取締役の在り方に関する実務指針」は、令和2年に策定された比較的新しいガイドラインです。
コーポレートガバナンス改革をより実効性のあるものとするため、社外取締役の担う役割が重要視されています。
そこで、このガイドラインでは社外取締役に期待される役割を明確にするとともに、社外取締役が役割を果たすために行うべき具体的な取り組みについて定められています。
コーポレートガバナンスを強化する方法
企業がコーポレートガバナンスを強化する主な方法は、次のとおりです。
企業理念の見直しを行う
コーポレートガバナンスの強化には、まず企業の存在意義や企業の在り方を再定義しなければなりません。
そのため、企業理念から抜本的に見直す必要が生じる可能性があります。
コーポレートガバナンスに強い弁護士へ相談する
コーポレートガバナンスの強化を、自社のみで推し進めることは容易ではありません。
場合によっては、企業内の部署を再編成したり、給与体系を変更したりするなど、抜本的な見直しが必要となる可能性があるためです。
そのため、コーポレートガバナンスの強化を進めるにあたっては、コーポレートガバナンスに強い弁護士をパートナーとしてチームに組み入れるとよいでしょう。
弁護士とともに進めることで、より効率的にガバナンス強化を進めやすくなります。
社外取締役や監査役の設置や見直しを検討する
コーポレートガバナンスの強化には、企業運営のチェック体制の整備が不可欠です。
そのため、企業運営を監査する立場である社外取締役の設置や、監査役の見直しなどを検討しましょう。
特に、監査役は本来取締役などの職務執行を監査する立場であるものの、取締役と近しい関係の者が担う場合には忖度などが生じ、適正なガバナンスが働かないおそれがあります。
行動規範を作成する
行動規範とは、企業の役員や従業員の行動指針を定めたルールです。
法令順守の他、行うべきでない行動、顧客に提供する価値などについて定めます。
役員や従業員が判断に迷った場合にはこの行動規範に立ち返り、行動規範に照らして判断する役割を持ちます。
業務の責任と権限を明確化する
責任の所在が不明確であれば、ガバナンスが効きづらくなるおそれがあります。
そのため、コーポレートガバナンスを強化するためには、業務の責任と権限の明確化が不可欠といえるでしょう。
ガバナンス強化の取り組みを社内へ向けて周知する
ガバナンス強化は、社内全体で取り組むべき課題です。
そのため、コーポレートガバナンスを強化する際には、すべての従業員や関係者へ向けて取り組みを周知しましょう。
コーポレートガバナンスの内容と事例
コーポレートガバナンスについての規範(ルール)としては、まず会社法・金融商品取引法があり、選択可能な機関設計や企業の規模や状況に応じた情報開示の規定が設けられています。
ガバナンス体制の構築は、これらのハードローで規定される制度や規律を前提に行うことが必要になります。
具体的には、登用可能な人材の選定や想定されるリスクをもとに、監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社の選択や任意の諮問委員会の設置などを検討することとなります。
一方、ソフトローであるコーポレートガバナンス・コードでは、コンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するルール)を前提に、目指すべきガバナンス体制の方向性にまで踏み込んで、5つの基本原則と30の原則及び38の補充原則が定められています。
5つの基本原則
- 株主の権利・平等性の確保
株主の実質的な権利や平等性の確保、少数株主等への配慮等 - 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
従業員や顧客といった多様なステークホルダーとの協働等 - 適切な情報開示と透明性の確保
財務情報や非財務情報の主体的な開示、情報の有用性の向上等 - 取締役会等の責務
企業戦略の設定、適切なリスクテイク、独立社外取締役の有効な活用等 - 株主との対話
株主総会以外での株主との対話、株主と会社の相互理解の促進等
⑴ 伊藤忠商事株式会社の例
総合商社の伊藤忠商事では、「豊かさを担う責任(Committed to the Global Good)」という企業理念などに則り、長期的な視点に立って企業価値の向上を図る基本方針に従って、コーポレートガバナンス体制が構築されています。
具体的には、通常の業務執行が経営陣へ委任されつつ、独立した社外取締役の複数名選任、社外役員中心の「ガバナンス・報酬委員会」「指名委員会」の設置、社外取締役比率を3分の1以上とすることなどにより、経営の監督が強化されています。
経営の執行と監督の分離が促進され、モニタリング重視の体制に移行した事例といえます。
⑵ 株式会社ツムラの例
漢方薬品メーカーのツムラは、2017年6月、コーポレートガバナンスの強化のため、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行しています。
監査等委員会は3名中2名が社外取締役であり、監査等委員が取締役会の議決権を保有することで取締役会の監督機能が強化されるとしています。
また、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役中心の「指名・報酬諮問委員会」が設置され、社外取締役による監督が強化されています。
⑶ 日本航空株式会社の例
日本航空株式会社では、会社と株主とのコミュニケーションを図る活動として、株主との対話を担当する経営陣や責任者の指定・配置、四半期決算や経営計画公表時の説明会の開催、株主向けレポートの発行や施設見学会の開催、株主との対話の結果の経営陣へのフィードバックなどが行われており、株主との対話や相互理解の促進に向けた活動が行われている事例と言えます。
Q.内部統制とコーポレートガバナンスの関係は?
A.内部統制とは、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令順守の達成などを目的にした、企業のリスク管理のプロセスです。
会社法では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制などが、いわゆる内部統制システムと呼ばれ、大企業など一部の会社ではその体制整備に関する決定が義務付けられています(会社法348条4項など)。
内部統制システムは、コーポレートガバナンスの一部と位置づけることができます。特にモニタリング重視のガバナンス体制を採用する場合には、業務執行の決定権限が経営陣に委任される範囲が広がるため、より内部統制システムの構築と運用が重要となります。
まとめ
コーポレートガバナンスの充実は、中長期的に企業価値を向上し、すべてのステークホルダーにメリットをもたらします。
一方、ガバナンス体制は、具体的な各企業の状況や経営方針などを前提に、現実的に設計する必要があります。
また、上場企業に限らず、中小企業や成長期待の高いベンチャー企業においても、事業承継や少数株主対応、資本政策やIPO準備などにおいて、コーポレートガバナンスの理解と対応は不可欠となります。
リスクが顕在化していない平時や、企業規模が大きくなる前にこそ、コーポレートガバナンスについての理解と準備を進めておかれるべきでしょう。