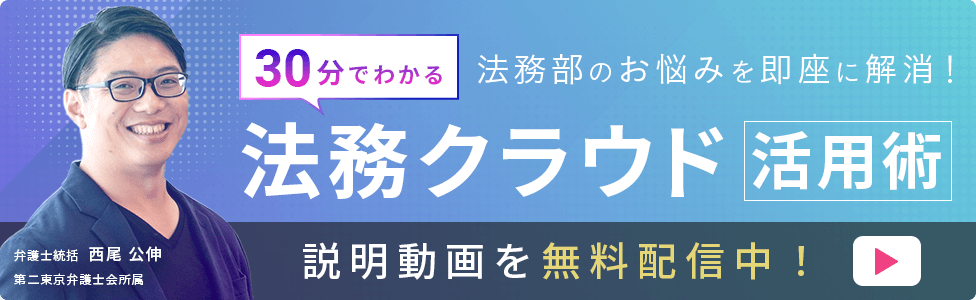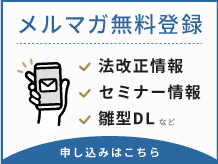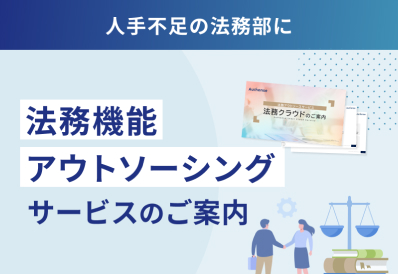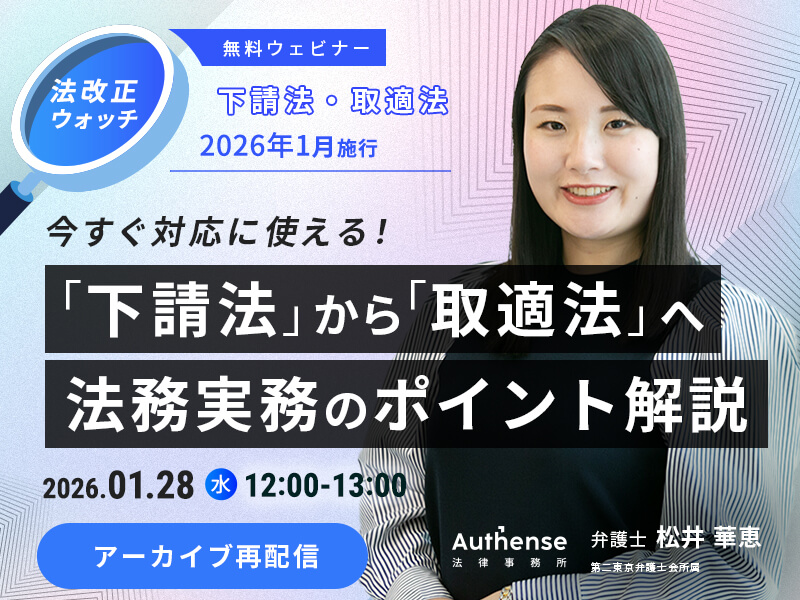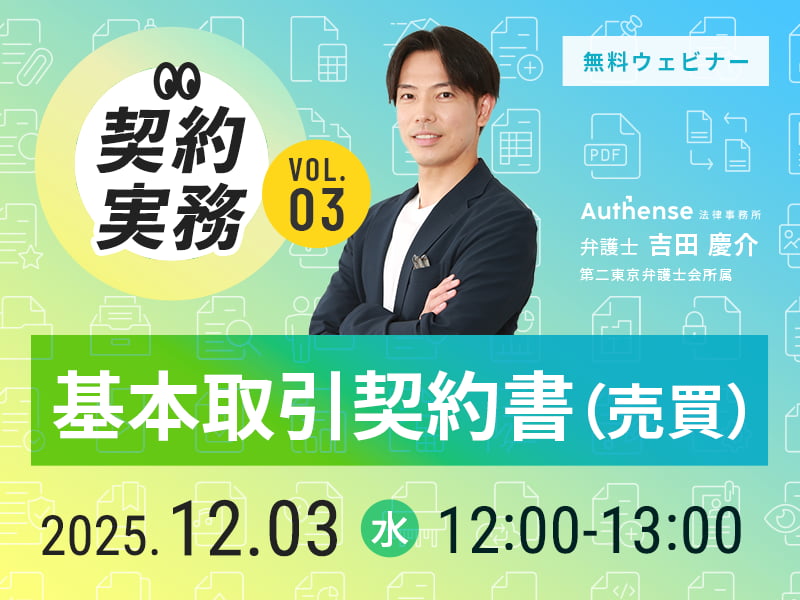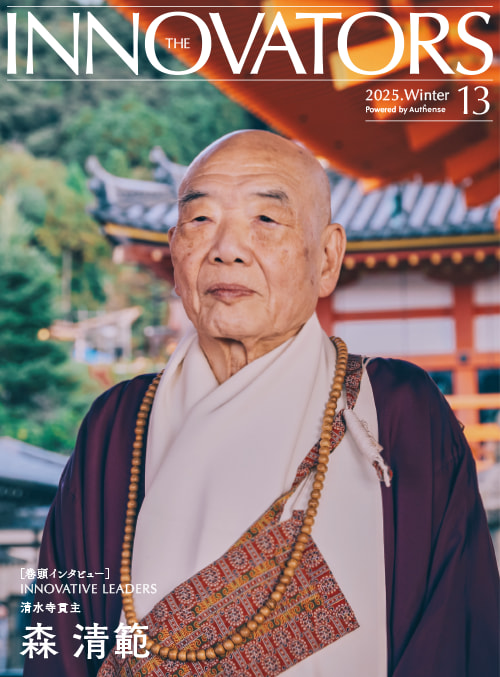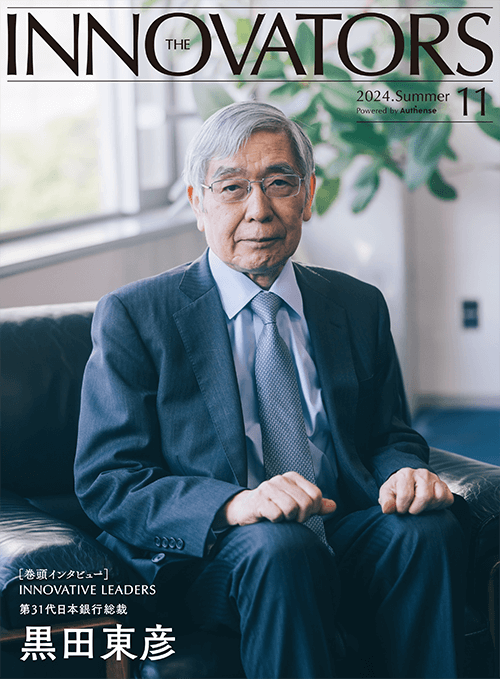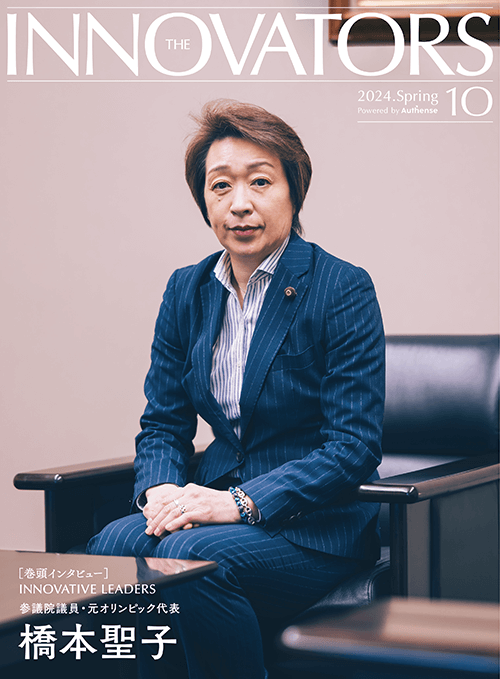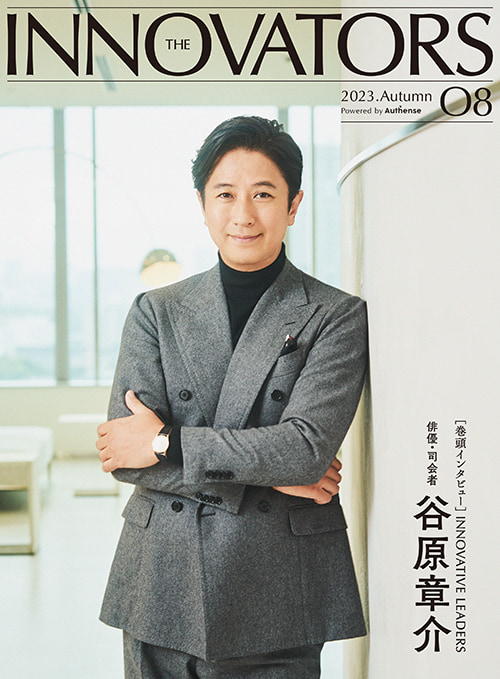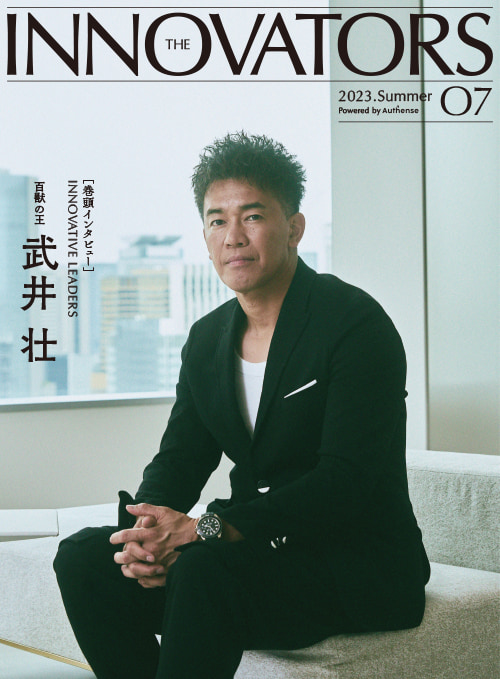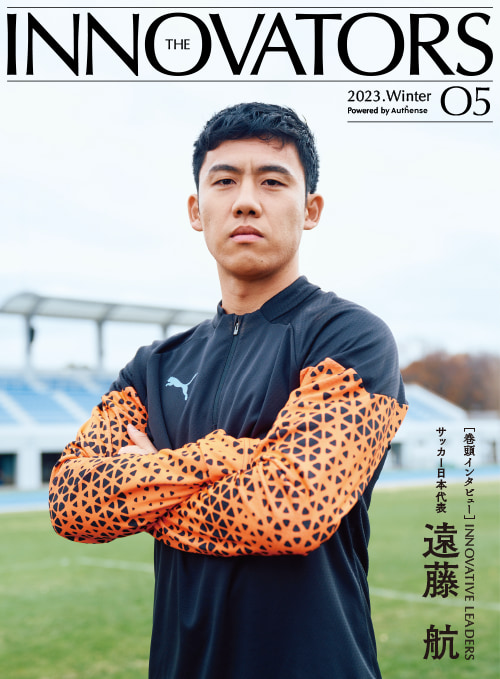2022年4月1日より、中小企業についてもパワーハラスメント防止のための措置が事業主に義務づけられました。
ハラスメントはすべての企業にとって大きなリスクとなり得ます。
ハラスメントが起きた場合に企業に及びうる影響や対応方法、弁護士の活用方法、予防策までわかりやすく解説します。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
パワハラなどのハラスメントが企業に及ぼす影響
パワハラなどのハラスメントは、どの企業でも発生する可能性のある問題です。
例えば、自己の主観では「ハラスメントではない。教育である。」と思って行動していることでも客観的にはパワハラであると認定される場合があります。
自覚のないまま加害者になるのを防ぐには、何がハラスメントに該当する可能性のある行為なのか認識をする必要があります。
企業内でハラスメントを発生させないためには、ハラスメントに関する情報を共有し、アップデートをすることが不可欠だといえます。
パワハラの定義については、こちらの記事をご参照ください。
万が一ハラスメントが起きてしまった場合に企業が負う可能性のあるリスクは、次のとおりです。
社内の雰囲気が悪化する
ハラスメントが行われている企業では、社内の雰囲気が悪化してしまいます。
ハラスメントの被害者が憂鬱となることはもちろん、たとえば毎日のように同僚が大声で怒鳴られるなどの様子を目の当たりにしていれば、他の従業員のモチベーションも低下してしまいかねません。
パワハラを長期間放置すれば、日常的にパワハラを目にしていた他の従業員がのちに部下に対してパワハラを行うなど、パワハラが常態化する企業となってしまうリスクもあるでしょう。
人材が定着しない
ハラスメントが起きている企業では、人材が定着しない可能性が高くなります。
被害に遭った従業員が辞めてしまう可能性がある他、ハラスメントを目にした従業員も適切な対応をしようとしない企業に見切りをつけて退職しまう可能性が高くなるためです。
損害賠償請求がなされる
企業は、従業員が生命と身体の安全を確保しつつ労働することができるように必要な配慮をする義務(安全配慮義務)があります。
仮に企業がハラスメントを放置して、従業員の健康を害することを予測しえたのに、適切な対処をせず、従業員の健康を害したような場合、被害者である従業員から企業に対して安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求がなされる可能性があるでしょう。
企業のイメージが悪化する
ハラスメントが公となれば、企業のイメージが大きく低下してしまいかねません。
ハラスメントが公になるきっかけとしては、従業員がSNSなどで告発する場合などが考えられます。
ハラスメントへ適切に対処しない企業の商品は買いたくないと考える消費者は少なくないため、業績にも影響が出てしまいかねないでしょう。
また、新規の採用にも影響が及ぶ可能性があります。
ハラスメントを予防するために企業が取るべき対応策
ハラスメントは、企業の対応次第である程度予防することができます。
企業が行うべきハラスメントの予防策には次のものがあります。
ハラスメントについて理解する
人は様々な価値観を持っており、その人が置かれた状況や属性もそれぞれ違います。
自己の主観でハラスメントではないと考えて行動したことでも、受け手にとってはハラスメントと感じることもあります。
客観的に何がハラスメントに該当するのか、その定義を共通認識しておく必要があります。
ハラスメントについては厚生労働省が詳しいガイドラインなどを公表していますので、ガイドラインなどを読み込み、個々がハラスメントについて正しく理解をしてくことが必要です。※1
ハラスメントについての社内研修を行う
社内全体に向けて、ハラスメントについての研修を行うことが予防策の一つとなります。
ハラスメントだと知りながら意図的に行うような悪質なケースもあるかもしれませんが、そもそもハラスメントに該当する行為と気づかずにハラスメントを行ってしまうケースもあるでしょう。
すべての従業員に対してハラスメント研修を行うことで、ハラスメントに対する抑止力となり、また必要以上に委縮せず業務を行うことが可能となります。
自社での研修が難しければ、弁護士や社会保険労務士など外部の専門家に研修をしてもらうことも一つでしょう。
ハラスメントが起きた際の相談窓口を設置するなど対応体制を整備する
企業は、ハラスメントが起きることのないようハラスメントを受けた労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる必要があります。
具体的には、ハラスメントの相談窓口の設置などがこれに該当すると考えられます。
近時の法改正により、パワハラにおいても、パワハラ防止のために、企業が雇用管理上必要な措置を講じることが義務として明記されました。(「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称「パワハラ防止法」))。
2022年4月1日からは、中小企業を含むすべての企業にかかる義務が課されます。
-
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
-
メールでご相談予約
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00
ハラスメントが発生した際に企業はどのように対処すべき?
パワハラなどのハラスメントが発生してしまったら、企業はどのように対処すれば良いのでしょうか?
ハラスメント発生時に企業が取るべき対応には次のものがあります。
事実関係を確認する
パワハラなどハラスメントの相談を受けたら、まずは事実関係を確認しましょう。
具体的には、当事者や関係者への聞き取り調査などです。
トラブルが予想される場合には、弁護士など社外の専門家に立ち会ってもらうことも一つです。
調査により聞き取りができた事項は、すべて記録を残しておきましょう。
弁護士へ相談する
ハラスメントの内容が重大である場合や社内のみでの対応が難しい場合には、できるだけ早期に弁護士へ相談しましょう。
弁護士が入ることでより効果的に調査を進めやすくなる他、企業を守ることにもつながります。
相談者への不利益な取り扱いをしない
パワハラ防止法では、労働者がパワハラに関する相談を行ったことや、事業主によるパワハラ相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇やその他不利益な取扱いをしてはならないとしています。
当然ではありますが、ハラスメントの相談を受けた際には、この点にもよく注意をして対応するようにしましょう。
状況に応じ、加害者への懲戒処分等を検討する
ハラスメントの事実が確認できたら、その内容・程度などによっては、加害者に対し懲戒処分を検討せざるを得ない場合もあります。
その際、行ったハラスメントと比較して処分が重すぎるようであれば、処分が無効となる可能性があります。
そのため、加害者に対し懲戒処分を行う際には、あらかじめ弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
今や、ハラスメントはすべての企業にとって無視することができない問題です。
万が一社内でハラスメントが起きてしまった場合には、企業にとって重大な影響を及ぼす事態ともなりかねません。
リスクを減らすため、すべての企業はハラスメントと適切に向き合う必要があるでしょう。
そこで、Authenseでは、経験豊富な弁護士がパワハラ防止策の実施からパワハラが発生した場合の調査・対応まで一貫したリーガルサポートを行う「ハラスメント防止対策プラン」を提供しております。
具体的には、予防策としての社内研修の講師や相談対応社員へのサポート、就業規則の改訂のほか、パワハラが起きてしまった際の社内調査や当事者のフォロー、社内懲戒処分のサポート、再発防止策の策定まで、トータルでの対応が可能です。
ご要望に応じてオーダーメイドでプランを作成いたしますので、ご検討の際にはぜひお気軽にお問い合わせください。