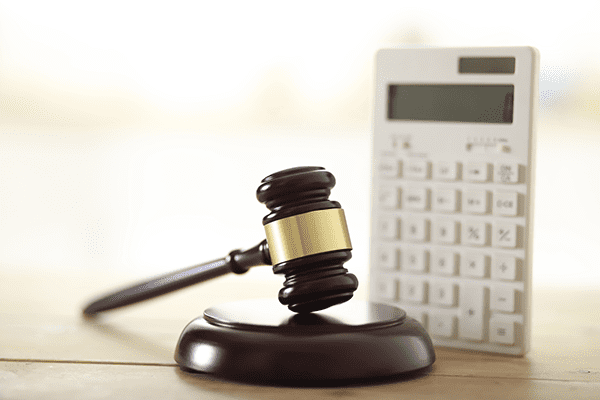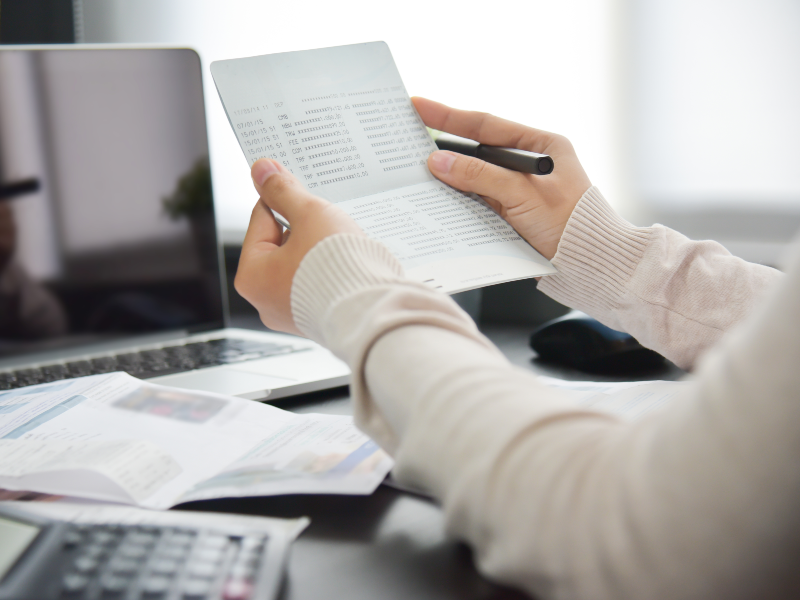相続財産の調査とは、必要な書類などを参照しながら、遺産の全容を確認する手続きです。
特に、遺産の数が多い場合や、亡くなった人と生前ほとんど交流がなかった場合などには、相続財産の調査が難航する可能性があります。
では、そもそも相続財産の調査は、どのような目的で行うものなのでしょうか?
また、相続財産の調査はどのように行えばよいのでしょうか?
ここでは、相続財産調査の目的や方法などについて弁護士が詳しく解説します。
相続人になったらまずやるべきこと
身内が亡くなり相続人になると、行うべきことが数多く発生します。
中でも、早期に行うべきことは次のとおりです。
役所関連の手続き
相続人になったらまず、役所関係の手続きを行います。
たとえば、死亡届の提出や年金関係の手続き、世帯主の変更届などがあります。
役所へ行く際には、いきなり出向くのではなく、あらかじめ電話などで必要書類を確認してから出向くとスムーズでしょう。
相続人の調査
葬儀が終わって少し落ちついたころから、亡くなった人(「被相続人」といいます)の相続人の調査を始めます。
なぜなら、後に行う遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)には相続人全員の参加が必要となるところ、相続人が一人でも漏れた遺産分割協議は無効となるためです。
相続人調査は、次の書類などを取り寄せて行います。
ただしこれは一例であり、状況によってはこれら以外の書類が必要となることもあります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合には、被相続人の両親それぞれの出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
なお、被相続人が父であり母と子のみが相続人である場合など、あえて調査するまでもなく相続人がわかっているケースもあるでしょう。
しかし、これらの書類は調査のためだけに取り寄せるものではなく、遺産分割協議の後で各遺産の名義変更や解約をするにあたって、各手続き先から提示を求められるものです。
そのため、このタイミングで集めておくことをおすすめします。
相続財産の調査
相続人の調査と並行して、相続財産の調査を進めます。
調査を始める時期は四十九日明け頃が一般的ではあるものの、被相続人に借金がある可能性がある場合などには、できるだけ早期から調査を始めることをおすすめします。
なぜなら、次で解説をする相続放棄の期限が短く、スケジュールにさほど余裕がないためです。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
相続財産調査の目的
相続財産調査は、何のために行うものなのでしょうか?
主な目的は次のとおりです。
遺産分割協議の参考とするため
目的の1つ目は、遺産分割協議の参考とすることです。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いです。
「遺産の内容がどうあれ、長男が全部相続すればよい」などと相続人全員の合意が成立しているのでない限り、遺産の全容がわからなければ誰が何を相続するかを決めることが難しく、遺産分割協議を行うことは困難でしょう。
そのため、遺産分割協議に先立って相続財産の調査を行います。
名義変更などの手続き漏れを防ぐため
目的の2つ目は、遺産の名義変更や解約手続きなどの漏れを防ぐことです。
各遺産の名義は遺産分割協議がまとまったからといって自動的に変更されるものではなく、相続人やその代理人などが一つずつ手続きを行わなければなりません。
遺産の全容が把握できていなければ、手続きが漏れてしまう可能性があります。
相続税申告の漏れを防ぐため
目的の3つ目は、相続税申告時の申告漏れを防ぐためです。
相続税とは、遺産などに対してかかる税金です。
遺産総額に過去の一定の贈与を加算した額が次の基礎控除額を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税は固定資産税などのようにあらかじめ計算された額が賦課されるものではなく、相続人など申告義務者が自ら算定し、申告しなければなりません。
相続税を漏れなく申告するためには、申告の前に遺産を調査しておくことが必要です。
申告期限後、仮に調査などで申告漏れが指摘された場合には、不足分の税金に加えて過少申告加算税や延滞税などの納付が必要となります。
相続放棄を検討するため
目的の4つ目は、相続放棄をするかどうかを検討する材料とすることです。
相続人は、原則として被相続人のすべての権利義務を承継します。
そのため、被相続人の借金などの負債があった場合には、原則としてその負債も承継しなければなりません。
また、負債は相続人間で取り決めたのみではお金を返すべき相手(「債権者」といいます)に対抗することはできない点にも注意が必要です。
たとえば、相続人間で「長男がすべての負債を承継する」との遺産分割協議を成立させたとしても、債権者は他の相続人である二男に対して弁済を請求することができるということです。
そこで、被相続人の負債を引き継ぎたくない場合には、相続放棄を検討することとなります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、初めから相続人ではなかったこととなる手続きです。
初めから相続人ではなかったこととなるため被相続人の借金を引き継がずに済みますが、自宅不動産や預貯金などプラスの遺産も一切相続できなくなる点に注意しなければなりません。
しかし、相続放棄をするかどうかを決めようにも、被相続人の遺産の全容が見えていなければ検討することは困難です。
そこで相続財産の調査を行い、相続放棄の是非を検討します。
なお、相続放棄の期限は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です(民法915条1項)。
そのため、被相続人に借金がある可能性がある場合には相続財産の調査を特に速やかに行う必要があります。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
相続財産調査の方法
相続財産を調査する主な方法は次のとおりです。
ただし、財産の内容や状況によってはこれら以外の調査方法も検討できるかもしれません。
自分での調査が難しい場合には、弁護士などの専門家へご相談ください。
不動産の調査方法
不動産の調査は、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)を法務局から取り寄せて行います。
全部事項証明書は、全国どこの法務局からでも、誰でも取得することが可能です。
ただし、全部事項証明書を請求するには地番や家屋番号の情報が必要であるため、まずはこれらの情報を得なければなりません。
なお、地番や家屋番号は住所と同じである場合もあるものの、住所とは異なる場合もあります。
また、一つの用途に使っている土地が2筆や3筆に別れていることもあるため、現地を見ただけで地番や家屋番号は判断できないことが多いでしょう。
そのため、まずはその不動産の所在地の市区町村役場から、被相続人が所有する不動産の一覧である、固定資産税評価証明書や名寄帳を取り寄せることをおすすめします。
これには地番や家屋番号が載っているため、この情報をもとに全部事項証明書を取り寄せることが可能です。
なお、被相続人の所有不動産は、固定資産税課税明細書(毎年市区町村役場から送付される、固定資産税納付書に同封されている書類)でも確認できます。
ただし、この固定資産税課税明細書には固定資産税がかからないほど評価額の低い不動産は掲載されないほか、共有の場合には原則として代表者宛にしか送付されません。
そのため、固定資産税課税明細書のみを参照すると不動産が漏れてしまう可能性がある点に注意が必要です。
預貯金の調査方法
預貯金の調査は、まず被相続人の通帳を確認します。
普段から使っていた金融機関であり、通帳の記帳もこまめにされていれば、通帳のみで情報がわかる場合もあるでしょう。
一方、近年では通帳を発行しない金融機関も存在するほか、通帳を紛失している場合もあります。
その場合には、被相続人の自宅などからキャッシュカードや金融機関からの書類、金融機関からもらったノベルティ(カレンダーなど)等を探しましょう。
そのうえで、取引のありそうな金融機関に残高証明書を請求することで、残高を知ることが可能となります。
被相続人の残高証明書の発行には、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等の提出が求められるため、事前に必要書類を確認しておくとよいでしょう。
通帳がない場合で、過去の取引履歴も知りたい場合には、取引履歴明細書(金融機関によって名称は異なります)も取り寄せておくとよいでしょう。
有価証券の調査方法
有価証券は、証券会社に預託しているケースが大半です。
そのため、まずは付き合いのあった証券会社を探します。
証券会社から定期的に郵送物が届いている場合には、その証券会社に口座がある可能性が高いでしょう。
他にも、証券会社のノベルティがある場合にも取引がある可能性があります。
また、被相続人が使っていたパソコンが開ける場合には、ブックマークされている証券会社がないか確認することも一つの方法です。
そのうえで、口座のある可能性がある証券会社に対して残高証明書を請求します。
これにより、証券会社に預託している有価証券が判明します。
この場合も、手続きの過程で被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等の提出が求められるため、事前に必要書類を確認しておくとよいでしょう。
借金の調査方法
被相続人の借金を調査するには、まず被相続人の自宅や郵便受けなどから督促状や催告書などを探します。
また、被相続人の通帳を確認し、まとまった金額の入金(借入の記録)や振り込み(返済の記録)がないかどうかも確認しましょう。
被相続人が不動産を持っている場合には、先ほど解説した不動産の全部事項証明書を取り寄せ、「権利部(乙区)」を確認することも有効です。
なぜなら、借り入れにあたって不動産を担保としているケースが少なくないためです。
この欄に抵当権などの記載があれば、借り入れがある可能性があります。
ただし、返済が済んでいるにもかかわらず、抵当権の設定が残っているケースも珍しくありません。
他にも、金融機関や信販会社などからの借金であれば、次の機関へ信用情報の開示を申し込むことで見つかる可能性があります。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- 一般社団法人全国銀行協会
ただし、照会によってすべての借金が把握できるわけではなく、一般個人からの借り入れやこれらに登録されていない機関からの借り入れなどは把握することができません。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
相続財産の調査を自分で行うデメリット
相続財産の調査は自分で行うこともできますが、弁護士などの専門家へ依頼することも可能です。
特に、相続人財産の数が多い場合や相続人間の関係性がよくない場合、被相続人と生前にほとんど交流がなかった場合などには専門家への依頼を積極的に検討するとよいでしょう。
なぜなら、自分で相続財産調査をすることには次のデメリットがあるためです。
手間と時間がかかる
自分で相続財産の調査をする場合には、調査に手間と時間がかかります。
特に、相続財産の種類が多い場合などには調査にかかる労力は少なくないことでしょう。
財産が漏れやすい
自分で相続財産の調査をした場合には、財産が調査しきれず漏れが生じる可能性があります。
特に、被相続人と生前深い交流のあった相続人がいない場合には、相続財産のすべてを漏れなく把握することは困難でしょう。
相続財産の調査に漏れが生じると、後から見つかった遺産に対して再度遺産分割協議や名義変更などの手続きが必要となったり、相続税申告に漏れが生じて税務調査で指摘されたりする可能性があります。
また、仮に後日多額の借金が見つかった場合にはもはや相続放棄が困難であり、借金を引き継がざるを得ない事態となるかもしれません。
なお、相続財産がまったく存在しないと信じたことで3か月以内に相続放棄などをしなかったなど特殊な事情がある場合には、期間が過ぎていても相続放棄ができる可能性があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
そのため、相続が起きてから相当の期間を過ぎてから初めて借金の存在を知った場合には、諦めずに弁護士へご相談ください。
他の相続人から着服や漏れを疑われる可能性がある
他の相続人との関係性がよくない場合に自分で相続財産の調査をした場合には、他の相続人から遺産の着服や調査の漏れを指摘されてトラブルとなる可能性があります。
そのため、相続人同士の関係性が悪いなど調査の正当性に疑念を持たれかねない場合には、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力
相続財産調査はAuthense法律事務所へお任せください
相続が起きた後早期に行うべきことの一つに、相続財産の調査が挙げられます。
なぜなら、相続財産の全容が見えていなければ遺産分割協議を行うのが困難であるほか、相続放棄をすべきかどうか検討することも容易ではないためです。
財産の調査に不足があれば、名義変更などの手続きが漏れたり、借金を見落として相続放棄が困難となったりするかもしれません。
漏れなく、かつ他の相続人から無用な疑念を持たれることなく相続財産調査を行いたい場合には、調査を弁護士へ依頼することも検討するとよいでしょう。
Authense法律事務所では相続手続きのサポートは相続トラブルの解決に力を入れています。
相続財産の調査でお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続に関するご相談は初回60分間無料です。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力