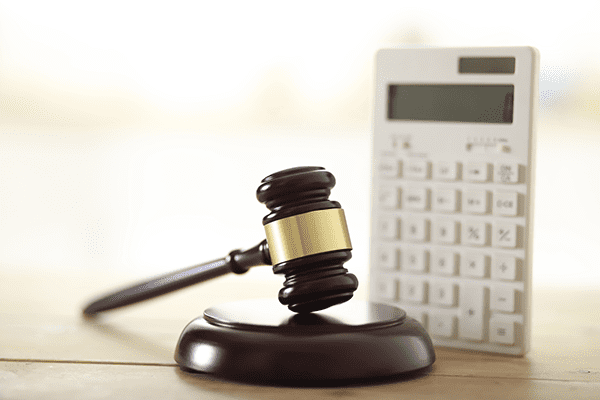遺言書を作成しても、遺言者が亡くなった後で遺言書の内容が自動的に実現されるわけではありません。
遺言書は、誰かが実際に金融機関で手続きをしたりすることで、初めて内容が実現されるものです。
この遺言書を、記載されている内容通りに実現する役割を担う人を「遺言執行者」といいます。
では、この遺言執行者の選任は、どのように行えばよいのでしょうか?
ここでは、遺言執行者の選任方法や選任手続きについて詳しく解説します。
遺言執行者とは?選任する重要性とは
遺言執行者とは、遺言書を、遺言書に記載された内容通りに実現する役割を担う人です。
せっかく遺言書を作成しても、その遺言書は、自動的に内容が実現されるわけではありません。
たとえば、遺言書を作ったからといって死後に自動的に不動産の名義が変わるわけでもなければ、金融機関が自主的に遺言書どおりに預金を割り振ってくれるわけでもありません。
つまり、遺言書を実現するには「誰か」がその遺言書の内容を実現しなければなりません。
その「誰か」とは次のいずれかとなります。
- 相続人
- 遺言執行者
そして、多くのケースで遺言執行者がいた方が遺言書の実現がスムーズです。
また、中には遺言執行者がいないと実現できない遺言内容もあります。
遺言執行者の選任が必要となるケース
遺言執行者は、どのような場合に必要となるのでしょうか?
遺言執行者が必須であるケースと、遺言執行者がいた方がスムーズであるケースに分けて解説します。
遺言執行者の選任が必須であるケース
次の遺言は、遺言執行者がいなければ実現することができません。
- 遺言書で相続人廃除をする場合や廃除の取消しをする場合
- 遺言で認知をする場合
遺言書にこれらの記載がある場合には、遺言執行者の選任が必須となります。
なお、これらの手続きを行うためには法的知識が不可欠です。
そのため、これらを行う際にはご家族などではなく、弁護士を遺言執行者に選任することも検討した方がよいでしょう。
遺言執行者を弁護士に依頼したい場合には、Authense法律事務所までご相談ください。
遺言書で相続人廃除をする場合や廃除の取消しをする場合
相続人の廃除とは、その相続の対象者である亡くなった人(「被相続人」といいます)に対して虐待をしたり重大な侮辱を加えたりするなど、著しい非行があった相続人から、相続人の資格を剥奪することです。
このような事情から遺産を一切渡したくないと考える場合は、その相続人に遺産を一切渡さない内容で遺言書を作成すればよいと考えるかもしれません。
しかし、子や配偶者など一定の相続人には「遺留分」があります。
遺留分とは、相続での最低限の取り分のことで、たとえ遺言書を用いたとしても剥奪することはできません。
そこで選択肢にあがるのが、推定相続人からの廃除です。
廃除が認められると、その相続人からは相続の権利が剥奪され、遺留分の権利もなくなります。
しかし、廃除の効果は重大であるため、相続人の廃除をするには家庭裁判所に申し立てて許可を受けなければなりません。
この廃除は被相続人が生前に行うこともできますし、遺言書に記載して死後に行ってもらうことも可能です。
遺言書の記載に従って家庭裁判所に廃除を求める手続きは遺言執行者が行うこととされており、遺言執行者の選任が必須となります。
また、生前に廃除をした相続人を許す手続き(廃除の取消し)も家庭裁判所に許可を受けなければなりません。
遺言書で行うには、遺言執行者の選任が必須です。
遺言で認知をする場合
認知とは、いわゆる婚外子を、父が自分の子であると認め、法的な親子関係を成立させる手続きのことです。
認知は生前に行うこともできますが、遺言書で行うことも可能です。
ただし、遺言書にもとづいて認知を行えるのは遺言執行者のみであるため、遺言書で認知をするには遺言執行者を選任しなければなりません。
遺言執行者がいた方が執行がスムーズとなりやすいケース
次のケースでは、遺言執行者の選任は必須ではありません。
しかし、遺言執行者がいたほうがスムーズでしょう。
- 遺贈をする場合
- 相続人によるスムーズな執行が難しい場合
遺贈をする場合
遺言書で遺贈をする際には、遺言執行者の選任をした方がよいでしょう。
なぜなら、遺贈をするには次のいずれかの人が手続きを行う必要があるためです。
- 相続人の全員
- 遺言執行者
相続人が近隣に住んでいて、少数であり、なおかつその全員が手続に協力的な場合は遺言執行者の選任までは不要かもしれません。
一方で、相続人が多い場合や、相続人の中に非協力的な人が1人でもいる場合は、相続人全員の協力で遺贈を実現することは困難です。
そのため、遺言執行者を選任した方がスムーズでしょう。
なお、遺贈とは遺言書に「相続させる」ではなく、「遺贈する」などとして財産を渡すことを指します。
相続人に対して「遺贈」をする場合もありますが、相手が相続人であれば「相続させる」とすることが多いでしょう。
一方、相続人でない人には「相続させる」ことはできないため、遺産を渡す相手が相続人でない場合はおのずと「遺贈」となります。
相続人によるスムーズな執行が難しい場合
遺言の執行は、相続人が行うことも可能です。
しかし、相続人が遠方に居住していたり、高齢であったりする場合、スムーズな執行は困難です。
そのため、相続人によるスムーズな執行が難しい場合にも、遺言執行者を選任した方がよいでしょう。
遺言執行者の選任方法1:遺言書で選任する
遺言執行者の選任方法には、「遺言書で選任する方法」と「相続開始後に家庭裁判所で選任してもらう方法」の2つがあります。
まずは、遺言執行者の選任方法として基本となる遺言書で選任する方法について解説します。
遺言書で遺言執行者を選任する方法
遺言書で遺言執行者を選任する方法は、遺言書内に遺言執行者を特定する情報(氏名、生年月日や住所など)を記載するのみです。
ただし、遺言書に書いたからといって、原則として相手に引き受ける義務が生じるわけではありません。
特に、事前に知らせないまま家族を遺言執行者に指定した場合、荷の重さから就任を拒絶されてしまう可能性もあるでしょう。
遺言書に遺言執行者を記載するにあたって、遺言執行者候補者の事前承諾を得ることは要件ではありません。
ただし、可能な限り事前に候補者の承諾を得ておいた方が、相続開始後にスムーズに引き受けてもらえる可能性は高くなるでしょう。
遺言書で遺言執行者を選任する際の記載例
遺言書で遺言執行者を選任する際の遺言書の記載例は次のとおりです。
ここでは、相続人の1人を遺言執行者として指定する例を紹介します。
第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、遺言者の長男である遺産一郎(昭和50年1月1日生)を指定する。遺言執行者は、遺言者名義の不動産の名義変更、遺言者名義の預貯金の名義変更、解約、払い戻し等、本遺言執行のために必要な一切の権限を有する。
遺言執行者は、続柄、氏名や生年月日などで特定して記載します。
そのうえで、その遺言の執行に関するすべての権限を有していることを付記しておくとよいでしょう。
遺言執行者の選任方法2:相続開始後に家庭裁判所で選任してもらう
次のいずれかに該当する場合において、遺言執行者が必要となる場合は相続開始後に家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらいます。
- 遺言書で遺言執行者が選任されていない場合や遺言書で遺言執行者が指定されていたものの、その者が遺言者より先に死亡しているなどの理由で遺言執行ができない場合
- 遺言書で遺言執行者が指定されていたものの、その者が遺言執行者への就任を拒絶した場合
なお、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てができるのは、遺言者が亡くなり、遺言書の効力が発生した後になります。
遺言者の生前に、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることはできません。
また、遺言書が自宅などで保管していた自筆証書遺言は、遺言執行者の選任申立てに先立って遺言書の「検認」を受ける必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封し、以後の偽造や変造などを防ぐ手続きです。
家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらう流れは次のとおりです。
必要書類を準備する
初めに必要書類を準備します。
遺言執行者の選任申立てに必要となる標準的な書類は次のとおりです。
- 家事審判申立書
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本または除籍謄本
- 遺言執行者候補者の住民票または戸籍附票
- 遺言執行者候補者が遺言者の親族である場合には、親族関係のわかる戸籍謄本や除籍謄本など
- 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
ほかに、執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。
なお、必要に応じて追加書類が求められる場合もあるため、その際は裁判所の指示に従って速やかに準備しましょう。
ご自分で用意することが難しい場合には、Authense法律事務所がサポート致します。
また、ご希望に応じてAuthense法律事務所の弁護士が遺言執行者に就任することも可能です。
家庭裁判所に申し立てる
書類の準備ができたら、管轄の家庭裁判所に申し立てます。
管轄の裁判所とは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立てをすると裁判所から遺言執行者候補者に対して「照会書(回答書)」が届きますので、届いたら速やかに返信します。
遺言執行者が選任される
遺言執行者が選任されると、家庭裁判所から申立人と遺言執行者に審判書が届きます。
審判書が届くのは、照会書への回答から1週間から2週間後くらいとなることが多いでしょう。
遺言執行者は誰を選任するべき?
先ほど紹介したように、遺言執行者の選び方には遺言書で指定する方法と裁判所に選んでもらう方法があります。
可能な限り遺言書内で選任しておいた方が相続開始後の手続きがスムーズでしょう。
では、遺言執行者には誰を選任するべきなのでしょうか?
遺言執行者の選び方は次のとおりです。
遺言執行者になれない人
次の人は遺言執行者になることができません。
- 未成年者
- 破産者
これら以外の人の場合、誰でも遺言執行者になることが可能です。
遺言執行者になるために、何か特別な資格が必要であるわけではありません。
また、その遺言書で遺産を渡す相手やそれ以外の家族などを遺言執行者に指定することも可能です。
ただし、遺言執行者は遺言者の死後に職務を行わなければなりません。
そのため、遺言者より年上の人や年齢の近い人などは避けた方がよいでしょう。
遺言者より先に亡くなってしまう可能性があるほか、存命であっても高齢で手続きをするのが難しくなる可能性があるためです。
遺言執行者に専門家を選任したほうがよいケース
遺言執行者には特別な資格は必要なく、家族やその遺言で遺産を渡す相手なども遺言執行者になることができます。
ただし、次のケースに1つでもあてはまる場合は、弁護士などの専門家への依頼を検討した方がよいでしょう。
- 家族や親族に適任者がいない場合
- 相続人間に争いがある場合や、遺言書が発端で争いが生じる懸念がある場合
- 自社株を相続させる場合など、確実にかつ速やかに遺言執行を行う必要がある場合
- 遺言書で相続人からの廃除、廃除の取消しや認知などをしたい場合
遺言執行者に就任する弁護士をお探しの際には、ぜひAuthense法律事務所までご相談ください。
遺言執行者の選任で困ったらAuthense法律事務所へご相談ください
遺言執行者は、その遺言書を記載どおりに実現する役割を担う人です。
遺言執行者の選任方法には「遺言書に記載して指定する方法」と、相続が発生してから「家庭裁判所に選任してもらう方法」の2つがあります。
相続手続きをスムーズに進めるには、遺言書で遺言執行者の選任をしておいた方がスムーズでしょう。
Authense法律事務所では、遺言書の作成サポートや相続手続き、相続トラブルの解決に力を入れています。
遺言書の作成をご検討の際や遺言執行者に就任する弁護士をお探しの場合、相続開始後の遺言執行手続きでお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続に関するご相談は初回60分間無料です。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力