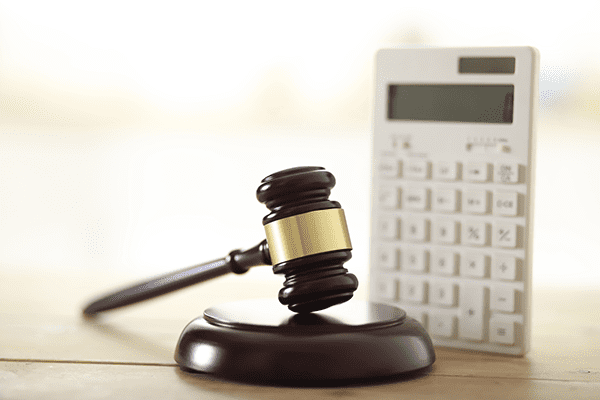しかし、相続人同士での遺産分けの話し合い(「遺産分割協議」といいます)がまとまらない場合もあるでしょう。
この場合には、遺産分割調停や遺産分割審判により遺産分割を図ることとなります。
では、これらはそれぞれどのように進行するのでしょうか?
また、遺産分割調停を有利に進めるコツなどは存在するのでしょうか?
ここでは、遺産分割調停と遺産分割審判について詳しく解説します。
亡くなった人の遺産を分ける方法
人が亡くなると、亡くなった人(「被相続人」といいます)の財産は、いったん自動的に相続人全員での共有となります。
しかし、共有のままではさまざまな不都合が生じるうえ、財産の使い勝手もよくありません。
そこで、たとえば「長男が不動産を取得して、二男がA銀行の預金を取得する」というように、遺産を分ける必要が生じます。
では、亡くなった人の遺産を分けるにはどのような方法があるのでしょうか?
主な方法は次の4つです。
方法1:遺言書に従う
被相続人が有効な遺言書を遺しており、その遺言書で各遺産の帰属先が決まっていた場合には、原則としてその遺言に従って遺産を分けます。
すべての遺産について遺言で帰属先が決まっている場合には、原則として次で解説する遺産分割協議は必要ありません。
方法2:遺産分割協議を行う
遺言書がない場合や遺言書で帰属先の指定がない財産がある場合には、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人全員で行う遺産分けの話し合いです。
遺産分割協議は相続人全員による合意で成立します。
そのため、一人でも協議内容に納得しない相続人がいる場合には、遺産分割協議を成立させることはできません。
遺産分割協議がまとまったら、協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。
そのうえで、相続人全員による合意を証するため、遺産分割協議書に相続人全員が実印で捺印します。
方法3:遺産分割調停を行う
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で行う遺産分割についての話し合いです。
話し合いといっても、遺産分割調停では原則として、相続人同士が直接話し合うわけではありません。
調停委員が交互に双方の意見を聞く形で話し合いを取りまとめます。
方法4:遺産分割審判を行う
遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立となり、遺産分割審判へ移行します。
遺産分割審判とは、裁判所に遺産の分け方を決めてもらう手続きです。
遺産分割審判では諸般の事情を考慮して裁判所が遺産の分け方を決めます。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停の一般的な流れは次のとおりです。
相続人の範囲を
確定する
・配偶者相続人
・血族相続人
第1順位:子又はその代襲相続人
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹又はその代襲相続人
遺産の範囲を確定する
・不動産
・預貯金
・有価証券
・債権(相続人の合意がある場合)
・債務(相続人の合意がある場合)
など
- 遺産の範囲に争いがあれば、
遺産確認訴訟の裁判を
別途申し立てる必要あり。 - 生前の使途不明金に争いがあれば、
不当利得 or 損害賠償請求訴訟
の裁判を別途申し立てる必要あり。
遺産を評価する
・不動産の評価
固定資産税評価額、路線価額、実勢価格(時価)など。
・非上場株式の評価
- 評価額に争いがあれば、
鑑定評価を行う必要あり。
各相続人の取得額を
決定する
・法定相続分
・特別受益
・寄与分
遺産の分割方法を
決定する
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有分割

遺産分割調停を申し立てる
はじめに、遺産分割調停を申し立てます。
申立先は、次のいずれかの家庭裁判所です※1。
- 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
- 当事者が合意で定めた家庭裁判所
申し立てには所定の申立書のほか、相続関係を証する戸籍謄本や遺産に関する書類などが必要です。
必要となる書類は状況に応じて異なるため、自分で申し立てをする場合には、あらかじめ管轄の家庭裁判所へ確認することをおすすめします。
なお、遺産分割では調停を経ずにいきなり審判を申し立てたとしても、裁判所の判断で調停に付されることが多いため、通常はまず調停を経ることとなるでしょう。
調停期日が決まり通知される
申立てから約2週間後~4週間後に裁判所から調停期日が通知されます。
この通知書は申立人のほか、相手方など相続人全員に送付されます。
調停期日は、申立て後2か月から3か月後あたりに設定されることが多いでしょう。
相手方が回答書などを作成し提出する
調停期日の通知書には申立人の主張を記載した申立書の写しが添付されています。
照会回答書などの返送が求められている場合には、相手方は指定の期限までにこれを記載して返送します。
また、相手方が自分の主張をまとめた答弁書を提出する場合もあります。
調停期日に家庭裁判所へ出向く
調停期日には、当事者がそれぞれ裁判所へ出向きます。
調停では直接双方が話し合いをするのではなく、裁判所の調停委員が交互に意見を聞く形で進行します。
1回の調停は標準的には2時間程度です。
複数回の調停期日を繰り返す
双方の主張が合致すればそこで調停の成立となりますが、1回の期日で解決することは多くなく、一般的には、4回から8回程度、調停が繰り返されます。
調停は、おおむね2か月から2か月半に一度のペースで進行します。
調停が成立したら「調停調書」が作成される
双方が納得し調停が成立したら、調停調書が作成され事件は終了します。
その後はこの調停調書を使って、遺産の名義変更や解約手続きなどを行います。
遺産分割審判の流れ
遺産分割審判の一般的な流れは次のとおりです。
調停不成立なら自動的に審判へ移行する
遺産分割調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続きへと移行します。
自分で改めて申し立てをする必要はありません。
審判期日に家庭裁判所へ出向く
審判期日に、家庭裁判所へ出向きます。
遺産分割審判では、裁判所が主張と証拠に基づき、分割方法を決定します。
事実関係に争いがある場合など、必要に応じて尋問が行われることもあります。
複数回の審判期日を繰り返す
遺産分割審判は、複数回の期日が開かれることが一般的です。
結論が出るまでの期間は事案によって異なりますが、数カ月から1年程度かかることもあります。
相続人同士が途中で合意できれば、審判を下すのではなく、話し合いによる解決も可能です。
審判が確定する
最終的に、裁判官が遺産分割の方法や内容に関する審判をします。
当事者は不服があれば即時抗告をすることができます。
期間内にいずれの当事者も即時抗告をしなければ、この時点で審判が確定します。
審判では審判書が作成され、確定後は裁判所に申請することによって確定証明書が発行されるため、これをもとに遺産の名義変更や解約手続きなどを行います。
「遺産分割調停」と「遺産分割審判」の主な違い
遺産分割調停と遺産分割審判は、それぞれ別の手続きです。
では、これらの主な違いはどのような点にあるのでしょうか?
主な違いは次のとおりです。
「調停」は話し合い「審判」は家庭裁判所が決める
遺産分割「調停」は調停委員が間に入って調整を行うものの、あくまでも話し合いの手続きです。
話し合いの成立を目指してサポートはしてくれるものの、裁判所が決断を下すわけではありません。
一方、遺産分割「審判」では諸般の事情を考慮のうえ裁判所が遺産分割方法を決めます。
ただし、先ほど説明したとおり、審判手続の途中で合意に至った場合には、審判によることなく話し合いで解決することもできます。
「調停」は相手と直接会うことはない「審判」は一堂に会することが多い
調停では原則として、当事者同士が直接顔を合わせることはありません。
それぞれ別の待合室で待機をして調停委員が交互に意見を聞きます。
一方、審判では、基本的に、双方当事者や代理人が同じ場に出席して期日が行われるため、相手と同じ空間で顔を合わせることが一般的です。
「審判」の方がより厳格な手続である
調停はあくまでも話し合いであるため、手続も内容も、比較的柔軟であるといえるでしょう。
一方、審判は裁判所が当事者の主張立証に基づいて判断するものであり、より手続も判断方法もより厳格です。
「審判」では相続人の誰もが望まない決断が下ることがある
遺産分割調停では、相続人全員が合意することを前提に、法定相続分とは異なる遺産分割を成立させることも可能です。
一方、審判では、法定相続分を原則に一切の事情を考慮して遺産分割がなされます。
そのため、場合によっては相続人の希望とは異なる審判となる可能性も否定できません。
たとえば、めぼしい遺産が自宅の土地建物のみであり、相続人である長男と二男はいずれもこれを売ることは避けたいと考えているとします。
しかし、他に適当な分け方がない以上、裁判所がこの土地建物を売ってその対価を分ける内容の審判をする可能性もあるということです。
遺産分割調停を有利に進めるポイント
遺産分割調停をできるだけ有利に進めるためにはどのような点に注意すればよいのでしょうか?
主なポイントは次のとおりです。
自分の希望を簡潔にかつしっかり伝える
遺産分割調停では、自分の希望を調停委員に対してしっかりと伝えることが必要です。
たとえば、「自宅の不動産はぜひ自分が相続したい」などです。
自分が取得したい財産についてしっかりと希望を述べ、相手と調停委員にそれが伝わるようにしましょう。
感情的にならない
遺産分割調停の場で、あまり感情的になるのは得策ではありません。
相続の場面では、自分の主張にどうしても感情が混じることもあるかと思います。
しかし、調停ではあらかじめ自分の主張を簡潔に整理して、自分の感情を長々と話したり調停委員に苛立ちの感情を向けたりすることは避けた方がよいでしょう。
嘘や隠し事をしない
遺産分割調停を有利に進めようとするあまり、嘘や隠し事をすることは避けましょう。
嘘や隠し事は、話の矛盾や相手が出した資料との整合性から発覚することが少なくありません。
嘘や隠し事が発覚すれば相手方から信頼できないと判断され、合意が難しくなる可能性があります。
相続問題に詳しい弁護士へ依頼する
遺産分割調停を有利に進めるためには、自分の主張を第三者が納得できるよう根拠や理由を示して整理しておくことが重要です。
また、相続に関する法律や裁判手続きなどへの正しい理解も不可欠でしょう。
しかし、これらを自分で行うことは、容易ではありません。
そのため、遅くとも遺産分割調停を申し立てる段階で相続問題に詳しい弁護士へサポートを依頼することをおすすめします。
弁護士へ依頼することで、調停の前にあらかじめ主張や証拠などを取りまとめておくことが可能となります。
また、調停期日に弁護士に同席してもらうこともでき、安心して調停に臨みやすくなる効果も期待できます。
さらに、弁護士がついていることで効果的な主張が可能となり、調停を有利に進めやすくなるでしょう。
遺産分割調停や遺産分割審判はAuthense法律事務所へお任せください
Authense法律事務所では、相続トラブルの解決や予防に力を入れています。
遺産分割調停や遺産分割審判に関してお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
相続に関するご相談は初回60分間無料です。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力