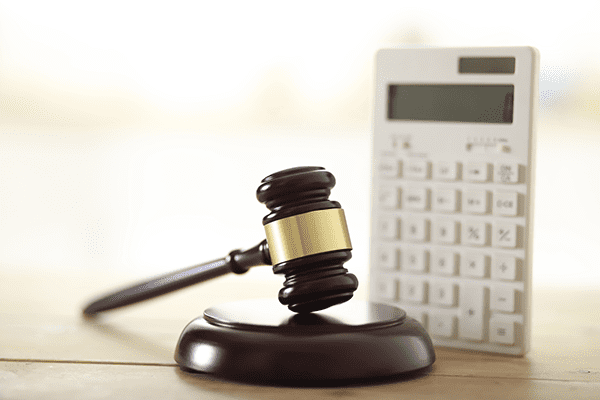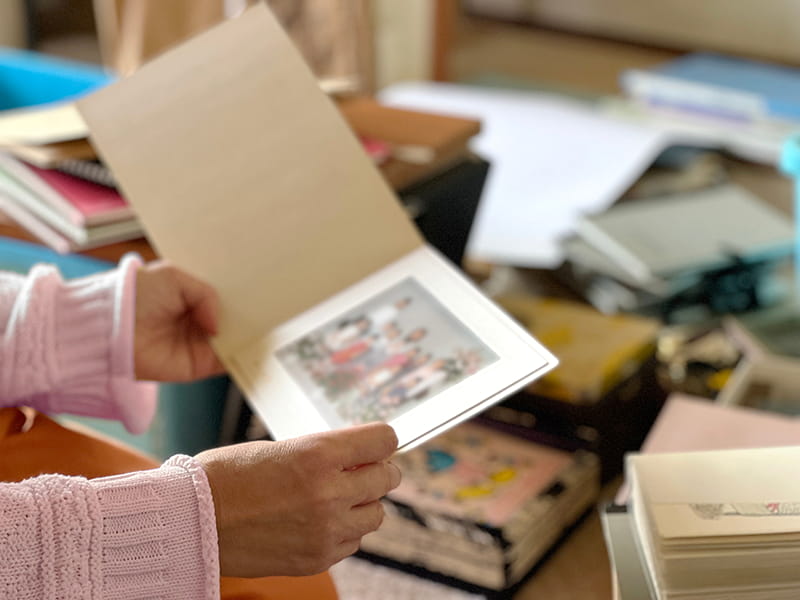自分が認知症になったり寝たきりになったりした場合、自分の財産はどのように管理すればよいのでしょうか?
他者に財産を管理してもらう方法には、主に「法定後見制度」「任意後見制度」「財産管理契約」「民事信託」の4つが存在します。
そこでここでは、それぞれの財産管理の概要を解説するとともに、財産管理契約のメリットデメリットなどについて弁護士が詳しく解説します。
老後の財産管理4パターン
老後の財産を他者に管理してもらう制度には、主に次の4つが存在します。
初めに、それぞれの制度について概要を解説します。
法定後見制度(成年後見制度)の活用
法定後見制度とは、本人の判断能力が低下した場合において、家庭裁判所に後見人などを選んでもらう制度です。
後見人などの候補者として家族などを挙げることもできますが、最終的に誰を後見人などとするのかは裁判所が決定します。
実際、弁護士や司法書士などの専門家などが後見人に就任しているケースも少なくありません。
専門家が後見人に就任した場合には、財産の内容に応じて月々数万円程度の報酬支払いが必要です。
法定後見制度には、本人の判断能力の状況に応じて次の3種類があります。
- 成年後見:判断能力が欠けているのが通常の状態
- 保佐:判断能力が著しく不十分な状態
- 補助:判断能力が不十分な状態
ここでは、成年後見を前提として解説します。
任意後見契約の締結
任意後見契約とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来の能力低下に備え、後見人の候補者との間で契約を締結しておく後見制度です。
法定後見制度とは異なり、本人が自分で選んだ相手を確実に後見人にすることができます。
原則として、任意後見契約は契約締結後すぐに効力を生ずるのではなく、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから効力が生じます。
任意後見契約の締結後に本人の判断能力が低下した場合、任意後見人となる人は速やかに任意後見監督人の選任の申立てをしなければなりません。
また、任意後見契約は公正証書で締結する必要があります。
財産管理等委任契約の締結
財産管理等委任契約(以下「財産管理契約」といいます)とは、本人判断能力がある間の財産管理について委任する契約です。
先ほど解説した任意後見人が実際に後見事務を開始できるのは、本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任されてからです。
そのため、契約を締結してから実際に判断能力が低下するまでの期間は、空白期間となるでしょう。
そこで、任意後見契約と組み合わせて財産管理契約を締結することがよく行われています。
つまり、契約の締結後すぐにこの財産管理契約が発効し、その後本人の判断能力が低下して任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約へと移行する形です。
このような契約形態を「移行型」といいます。
任意後見契約とともに財産管理契約を締結する場合には、財産管理契約も公正証書で締結することが多いでしょう。
一方で、財産管理契約のみを単体で契約することも可能であり、この場合には必ずしも公正証書である必要はありません。
民事信託(家族信託)の活用
民事信託とは、信託銀行や信託会社などを介さない信託契約です。
財産を引き受ける受託者が営利を目的としないことが必要であることから、家族や親族が受託者となることが一般的です。
そのため、「家族信託」と呼ばれることも少なくありません。
民事信託では、信託契約で定めることでさまざまな希望を実現することが可能です。
たとえば、経営者が自社株式を信託して事業承継に利用したり、賃貸アパートを信託して資産運用と相続対策に活用したりすることなどが検討できます。
単に財産を管理したり守ったりするのみならず、多様な目的を達成したい場合は、民事信託が1つの選択肢となるでしょう。
4つの財産管理制度の比較
先ほど紹介した4つの財産管理制度をまとめると次のようになります。
| 成年後見 | 任意後見契約 | 財産管理契約 | 民事信託 | |
|---|---|---|---|---|
| 利用開始時点での本人の判断能力 | 不要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 利用方法 | 家庭裁判所への申立て | 任意後見候補者と本人とで契約締結(公正証書) | 財産管理受託者と本人とで契約締結 | 受託者と本人とで契約締結 |
| 開始時期 | 審判確定後すぐ | 本人の判断能力が低下し任意後見監督人が選任されたとき | 契約で定めたとおり | 契約で定めたとおり |
| 監督機関 | 家庭裁判所 | 任意後見監督人 | なし | なし |
| 取消権 | あり | なし | なし | なし |
どの方法を選択すべきか判断に迷う場合は、Authense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所では、適切な財産管理制度を提案するのみならず、実際の契約締結などまでトータルでサポートいたします。
財産管理4パターンの選び方
財産管理の4パターンのうち、実際にどの形態を選択すべきか迷うことも多いでしょう。
基本的な考え方と選び方は次のとおりです。
すでに判断能力がない場合
本人がすでに判断能力を失っている場合、任意後見契約の締結や財産管理契約の締結、民事信託の組成は困難です。
そのため、この場合には法定後見の一択となります。
信頼できる家族や親族がいない場合
信頼できる家族や親族などがいない場合は、民事信託は活用できません。
なぜなら、民事信託は受託者が営利を目的としないことが求められるためです(信託銀行などが行う商事信託と名前は似ていますが内容は異なります)。
したがって、弁護士や一般の株式会社などを受託者として民事信託を締結することはできません。
一方、任意後見契約や財産管理契約では、弁護士などの専門家を受託者とすることが可能です。
そのため、本人が現状判断能力を有している場合は、専門家とこれらの契約を締結することを検討することとなります。
判断能力を喪失している場合は、法定後見の一択となるでしょう。
特定の相手にしか財産管理を任せたくない場合
たとえば信頼できる姪がおり、この姪に財産管理を任せたい場合もあるでしょう。
この場合は、法定後見以外である任意後見契約、財産管理契約、民事信託の3つが選択肢となります。
なぜなら、法定後見制度では後見人の候補者は挙げられるものの、必ずしもその候補者が後見人として選任されるとは限らないためです。
特に親族間で争いがある場合や財産が多額である場合などは、弁護士や司法書士などの専門家が後見人として選定される可能性が高くなります。
しかし、先ほども解説したように、判断能力がすでにない場合は法定後見を選択せざるを得ません。
そのため、特定の相手以外には財産管理を任せたくない場合は、元気なうちに財産管理契約や任意後見契約などを締結しておくことが必要です。
資産運用や相続対策など複雑な財産管理を任せたい場合
法定後見や任意後見は、あくまでも本人のために財産を管理する制度です。
そのため、これらの制度では資産運用や相続対策などを任せることはできません。
たとえば、「相続対策のために本人の預金を投入して賃貸アパートを建築したい」と希望しても、監督機関である裁判所が許可をする可能性は低いでしょう。
一方で、民事信託であればある程度自由な設計が可能です。
そのため、資産運用や相続対策などを任せたい場合は、民事信託が有力な選択肢となります。
財産管理契約のメリット
ここからは、先ほど紹介をした4つの制度のうち「財産管理契約」について解説します。
財産管理制度の主なメリットは次のとおりです。
開始時期や内容を自由に決められる
財産管理契約では、契約の開始時期や契約内容を自由に定めることが可能です。
判断能力が十分である成人同士が締結する契約であるため、法令による介入はほとんどありません。
判断能力が衰えていなくても開始できる
任意後見契約が発効するのは、本人の判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されて以降です。
しかし、たとえ判断能力が低下していない場合であっても、急な入院時における入院費の引き出しや支払いなどに対応してほしい場合もあるでしょう。
財産管理契約の場合、判断能力が低下していなくても開始させることが可能です。
特約で死後事務についても委任できる
財産管理契約を締結する際は、特約として死後事務委任についても定めることが少なくありません。
一般的に、委任契約は当事者のいずれかが亡くなった時点で失効します。
しかし、特約で定めておくことで、死後の一定の事務について委任することも可能です。
たとえば、次の事項などを委任することが多いでしょう。
- 葬儀や埋葬の手配
- 死亡届の提出
- 医療費などの支払い
- 永代供養の手配
財産管理契約のデメリット・注意点
財産管理契約には、デメリットもあります。
主なデメリットと注意点は次のとおりです。
社会的な認知度や信頼度が高くない
財産管理契約は徐々に認知されてきているとはいえ、成年後見などと比較すると、まださほど認知度は高くありません。
そのため、正式に締結をした財産管理契約書を提示しているにもかかわらず、金融機関が預金の支払いに応じないなど、実際の運用面でハードルが生じる可能性があります。
そのため、財産管理契約を締結する前に取引のある金融機関に対応について確認し、スムーズに取引ができそうな金融機関に預金を移すことも1つの手でしょう。
取消権はない
財産管理契約では、取消権を付与することはできません。
そのため、たとえば高齢である本人が騙されるなどして高額な商品を購入させられたとしても、財産管理契約の受任者が本人に代わって契約を取り消すことはできないということです。
取消権があるのは成年後見人のみとなります。
信頼できる相手を選定する必要がある
財産管理契約では、自分の財産に関するあらゆることを委任することになります。
実際の委任内容は契約内容によるものの、預貯金の払い戻しや解約などの権限を付与することも多いでしょう。
そのため、財産管理契約を締結する際は、信頼できる相手を慎重に選ばなければなりません。
委任する相手を誤ってしまうと、大切な財産が適切に管理されない可能性があるためです。
家族や親族に適任者がいない場合は、弁護士などの専門家に財産管理を委任することも1つの手でしょう。
財産管理についてお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
老後の財産管理で困ったらAuthense法律事務所へご相談ください
老後における自分の財産管理について、不安に感じる人は少なくありません。
特に子供がいない場合や、子どもがいても疎遠となっている場合には、不安が小さくないことでしょう。
老後の財産管理を他者に任せる方法には、主に「法定後見制度」「任意後見制度」「財産管理契約」「民事信託」の4種類があります。
それぞれに一長一短があるため、制度の内容やメリット・デメリットなどを十分に理解したうえで選択することが必要です。
また、すでに本人が判断能力のない常況となっている場合は、選択できる財産管理制度は法定後見の一択となってしまいます。
選択肢の幅を広げるため、財産管理についてはできるだけ早くから検討することをおすすめします。
Authense法律事務所では、財産管理契約や任意後見制度など、財産管理に関する相談に対応しております。
ご自身やご家族の財産管理についてお困りの際には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
初回のご相談は60分間無料です。
ささいなお悩みもお気軽に
お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら
オペレーターが弁護士との
ご相談日程を調整いたします。
- 24時間受付、通話無料
- 24時間受付、簡単入力