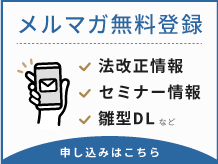昨今、「ファッションロー」という言葉を耳にする機会が増えましたが、それがどういう意味なのかご存じでしょうか。
ファッションローとは、そのような名前の法律が存在するというわけではなく、知的財産法をはじめとするファッションビジネスに関連する法分野全般をいいます。
目次
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
ファッションローが誕生した経緯
1711年、フランスで、「リオン絹織物産業の共同従業者および製造者のデザインの盗用に関する執政官規則」が制定されます。
これがファッションローの始まりであるため、ファッションローは古くから存在したということになります。
しかし、ファッションローという分野が大きな注目を集め始めたのは比較的近年になってからです。
近年はIT技術の進化により、アイテムのデザインの模倣が容易になったことや、ファッションブランドを運営する企業が会社として自社の権利を保護に積極的になっていることをきっかけに、各社が自社の商品の価値を保護しようという動きが活発になり、ファッションローが注目されることとなりました。
ファッション業界が抱えている法的課題
上述のように、今日ではファッションローという言葉をよく耳にすることになりましたが、それに伴い、ファッション業界では様々な法的な課題が生じています。
ここでは、代表的な3つの法的課題点を取り上げます。
課題1:ブランドネームやロゴの商標登録
「運営しているブランドのブランドネームやブランドロゴの使用を停止するように求める警告書が届いてしまった」という法律相談が急増しています。
ご自身のブランド名やブランドロゴを商標登録していないことによる紛争が近年目立つようになっているのです。
「商標」とは、ファッションビジネスにおいては、ブランド名やブランドロゴのことをいいます。
そして「商標権」とは、ブランド名やブランドロゴマークを保護する権利です。
商標を商標権で保護するためには、特許庁に対して商標出願のうえ、商標登録をする必要があります。
つまり、商標登録をしなければ、ブランド名やブランドロゴは商標法によっては保護されないということです。
たしかに、ブランド名やブランドロゴを保護可能な法令には、著作権法や不正競争防止法もあります。
ですが、商標登録を行うほうがより直截的に保護可能であるといえます。
そのため、安全に自社がブランド名やブランドロゴを使用し、かつ、ブランド名やブランドロゴを無断で使用された場合に法的に争うことをより容易に可能にするために、商標登録をし、商標権を取得することが重要です。
なお、商標は、ブランドをスタートする前に出願することが望ましいです。
同一または類似のブランドネームやロゴで、他の企業がすでに商標登録をしている場合、あとからブランド名を変更せざるを得なくなってしまうおそれがあります。
また、悪意のある第三者が先に出願をしてしまい、商標権を取得される可能性もあります。
課題2:模倣品への対策
「アイテムデザインを模倣されたため、模倣品の販売を停止させたい」という法律相談も増えています。
上述のとおり、近年では、IT技術の進化により、デザインの模倣をすることが容易になったため、市場に流通している流行りのアイテムデザインを模倣し、模倣品を大量生産してより安価な価格で販売し、多額の利益をあげるという手法を取る企業が増えています。
これまでも、流行りのアイテムの模倣品が生産されていることは多くありました。
しかし、模倣品を生産するまでに時間がかかっていたため、模倣の対象となったアイテムと模倣品が市場で競合することがなく、模倣の対象となったアイテムで各企業が十分な利益を確保することができました。
そのため、模倣品に対する対策を取る必要がなく、放置していたという事案も多く見受けられました。
しかし、技術の進歩により模倣品を製造するペースが速くなり、模倣の対象となるアイテムと模倣品が同一のシーズンで市場に現れるということが近年増加しています。
そうなってしまうと、消費者は、模倣の対象となったアイテムではなく、より安価な模倣品を購入するケースが増加してしまい、各企業は、模倣の対象とされたアイテムデザインによって十分な利益を確保することができなくなるケースが増えています。
そのため、各企業は、自社が生産したアイテムの模倣品を見つけた際は直ちに販売差止請求等による対策をすることが重要となっています。
万が一、自社の商品のデザインが模倣された場合には、商品販売などの差止請求や損害賠償請求を求めることができます(不正競争防止法2条1項3号、3条、4条)。
しかし、商品を販売してから3年を経過するとそのような請求ができなくなる(不正競争防止法19条1項6号イ)ため、もし自社商品の模倣品を発見した場合には、迅速な対応が求められます。
課題3:ステマ規制への対応
近年ではSNSの影響が若者の間で圧倒的であり、アパレルの広告は各SNSで行うことが最も効率的であるため、「ステルスマーケティング(ステマ)」が行われるケースが散見されていました。
ステルスマーケティングは、外形的にブランドと関係のない人が商品を消費者に勧めるという形を取っているため、消費者が商品に対する誤った評価を受けとることになり、消費者の合理的な判断を阻害するという点が問題視されていました。
ステルスマーケティングは、これまで日本では法律で規制されていませんでしたが、令和5年10月から景品表示法5条3号により規制されました。
これに違反した場合には措置命令(広告表示の停止等が命じられること)が行われることなり、さらに措置命令を守らない場合には罰則として2年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはその両方が課されることとなるため、よりプロモーションの方法に注意を払う必要があります。
ステルスマーケティングの類型は、ブランド関係者がブランドと関係ない人を装って商品を宣伝する方法の「なりすまし型」と、インフルエンサーに依頼をして商品を宣伝してもらう方法の「利益提供秘匿型」の2つがあります。
どちらの類型であっても、事業者が表示内容の決定に関与したといえるかによってステルスマーケティングに当たるかが判断されます。
なりすまし型は、企業のPR担当者が宣伝する場合に、事業者が表示内容の決定に関与したといえることになるのが原則です。
しかし、PRの方法次第では、企業のPR担当ではない人のSNSの投稿でもステルスマーケティングに当たってしまうことがあるので注意が必要です。
ステルスマーケティングと判断されないためには、企業として社内ルールを制定し、会社の従業員が自社の商品をSNS投稿する際には部署や仕事内容に関係なく「#PR」を付けるなどの対策が考えらます。
また、利益提供秘匿型は、「ブランドがインフルエンサーに特定の商品の宣伝を依頼しギャランティを支払う」というケースが、事業者が表示内容の決定に関与したといえる典型例となります。
この場合でも、一律にステルスマーケティングと判断されるのではなく、客観的な状況から事業者が表示内容の決定に関与したといえるかを判断することになります。
具体的には、ブランドとインフルエンサーのやり取りの内容、そのやり取りの態様、支払う対価の内容、その支払いが宣伝目的で支払われているか、事業者が過去に対価を提供していたか、今後提供する予定があるかなどを総合的に考慮して判断することとなります。
ステルスマーケティングと判断されないためには、以下のような点が重要です。
- 事業者が上述の要素を把握しておくこと
- 事業者がインフルエンサーに商品を提供する場合にどのような趣旨で商品を提供するかをあいまいにせずに話し合うということ
- インフルエンサーがSNSに投稿する場合には、「#PR」等をわかりやすく表示したり、タイアップ機能を利用したりするなどして提供元を消費者にわかりやすく明示すること
(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 令和5年3月28日消費者庁長官決定 参照)
GUCCIとGUESSの有名なファッションロー裁判事例を解説
ここで、上記のファッションローに関する法的課題が問題となったGUCCIとGUESSの裁判事例を紹介します。
この裁判は、アメリカ、イタリア及び中国で行われた裁判で、商標権侵害及び商品の模倣が問題となったものです。
イタリアのファッションブランドであるGUCCIは、2009年、GUESSが販売しているシューズのデザインに、GUCCIが商標登録をしている「Gマーク」及び赤と緑のストライプである「ウェブストライプ」を用いたことによりGUCCIの商標権を侵害したとして、GUESSに対して損害賠償請求をしました。
GUCCI が販売しているシューズは、ブラウンまたはベージュ色のアイテムで、「Gマーク」を2つ組み合わせたロゴが散りばめられており、かつ、シューズの左右にウェブストライプが施されているというデザインでした。
一方、GUESSが販売したシューズも、ブラウンまたはベージュ色のアイテムで、「Gマーク」を4つ組み合わせたクワトロGと呼ばれるロゴが散りばめられ、かつ、シューズの左右にウェブストライプと同色で同じ配置のストライプが施されていました。
この訴えに対して、アメリカの裁判所では、「Gマーク」を4つ組み合わせたロゴをブラウン又はベージュのアイテムで使用すること及びウェブストライプを使用することは、GUCCIの商標の一般化を招き、商標として価値を低下させるとして、GUCCIの主張を一部認めました。
本件は、最終的には2018年、GUCCIとGUESSの両当事者での和解により終了しました。
しかし、アメリカの裁判所では、上記のとおり商標権侵害と模倣について損害賠償請求を行ったところ、模倣についての損害賠償請求は認められないが、商標権侵害についても損害賠償請求は認められるという判断がされました。
このことから、本件は、日本での裁判ではないものの、商標登録をすることにより、自身が販売しているアイテムの模倣アイテムが発売された場合に、複数の法的請求をすることが可能になり、よりアイテムデザインの権利を保護しやすくなることから、商標登録の重要性を痛感できる事案となっているといえるかもしれません。
ファッションローガイドラインに書かれている内容
上述のように、近年では世界中でファッションローに対する関心が高まっています。
そのため、経済産業省は、2023年、「ファッションローガイドブック2023 ~ファッションビジネスの未来を切り拓く新・基礎知識~」を公表しました。
このガイドブックは、ブランドを立ち上げたらまずやるべきこと、ファッションデザインの権利についてブランドやデザイナーが知っておくべきこと、外部クリエイターとの付き合い方など、ファッションブランドを経営する際によく問題となる法的課題点についてチェックリスト方式でまとめられています。
そのため、ファッション業界の企業は、運営しているブランドが直面している問題が法的にどのような点について問題となるのか等の法的な問題点の大枠を手軽に知ることができるため、一度目を通しておきたいものとなっています。
これだけは押さえておきたいガイドラインの要点
ファッションローガイドブックは、上述のファッション業界の法的な課題についても、具体的に、かつわかりやすく説明しています。
商標登録の重要性
まず、ファッションブランドを立ち上げる前に、ブランドネームやブランドロゴについて商標登録をすることが重要であるという点を法的課題として挙げました。
しかし、どのようなブランドネームでも商標登録を受けられるわけではありません。いざ商標出願をしても様々な理由から出願したブランドネームを商標登録ができなかったということもあり得ます。
具体的には、スタイリッシュかつわかりやすく覚えてもらいやすいブランドネームを商標出願し商標登録しようとしたが、結局そのブランドネームで商標登録をすることができなかったという事例も多く見られます。
なぜなら、商標登録は、その商品のカテゴリーで一般的な名称として用いられているもの、簡単すぎる又は単純すぎる言葉が用いられているもの、他社のサービス名と類似するもの等は商標登録されにくいものだからです。
一般的な名称を誰か特定の人にのみ独占させてしまうと、他の一般的な名称を用いたい企業の活動に悪影響を及ぼしてしまうことになってしまいます。
また、一般的な名称で商標登録がされてしまうと、消費者がそのブランドネームを見た際に、それがどのブランドのことを指しているのかがわからなくなってしまうという側面もあり、上記のような商標は登録がしづらくなっています。
一方で、商標登録されやすいものは、造語や独自に考えたフレーズといったものです。
造語を作成する際も、シンプルな造語である場合には、すでに商標登録がされていることも多くあるため、検索システムやインターネットで事前調査をしながら作成することがおすすめです。
上記のようにお話をさせていただくと、ブランド名等は長くすればするほど商標登録がされやすいとして、ブランドネームをできる限り長くして商標登録をしたいと考えることが自然です。
しかし、安易にブランドネームを長くしすぎると、逆に類似のブランドネームを利用している者が存在している場合に、商標の侵害が認められづらくなってしまいます。
そのため、ブランドネームを考える際は、商標登録のしやすさと商標侵害がされた場合に請求が認められやすいかという点を考慮する必要があります。
ファッションローガイドブックでは、商標登録がしにくいブランドネームの大まかな類型がまとめられているため、ブランドネームを決定する際にどのような点に注意するべきかを知ることができます。
模倣品が販売された際の対応
また、自社のアイテムの模倣品が販売された際の対応もとても重要なことです。
一方で、他社のデザインを模倣したとして商品の差止請求や損害賠償請求をされないようにするということも、ファッションブランドを運営するうえで重要なことです。
具体的には、ブランドネームを見なくても特定のブランドのアイテムであると認識できるアイテムが存在します。
そのような商品は、デザインが有名であるとして法的な保護を受けることとなるため(不正競争防止法第2条1項1号、第2号、立体商標等の商標権)、安易に類似のデザインのアイテムを製造しないようにしましょう。
また、上記に当てはまらない有名でないデザインであっても、日本国内で発売されてから3年間はデザインが保護されることになります(不正競争防止法第2条第1項第3項)。
そのため、こちらについても安易に類似のデザインの商品を製造するべきではありません。
そして、イラストや絵については、著作物として著作権で保護されることとなります。
その期間は、著作者の死後70年間と長期にわたります。
昔のイラストや絵であっても、著作者の著作権が存続している可能性もあることを念頭におくことが重要です。
ファッションローガイドブックでは、模倣とはどのようなことを指すのか、どのくらい似ていると裁判所で模倣していると判断されるか等がイラストを掲載のうえ、解説されています。
これにより、どのようなデザインのコピーがアイテムデザインを模倣したと判断されるのを具体的に知ることができます。
契約書の内容
外部のクリエイター等に仕事を依頼する場合、必ず「契約」をすることとなります。
しかし、そもそも契約とは何か、契約書にはどんなことを記載すればいいか、契約書のひな型を先方から渡されたが何を確認すればいいかということは、多くの方が悩まれたことがあるのではないでしょうか。
契約書は、どのような条件で取引をすることになったかを後から確認できるようにするための書類です。
いわば、言った言っていないの水掛け論にならないようにするための書類です。
そのため、取引をする際は必ず契約書を作成しなければならないという意識を持つことが非常に重要です。
そして、契約書は、上述のとおり水掛け論にならないために作成するものですから、契約書にどのようなことが記載されているかという中身がもっとも重要です。
どのような条項が不可欠かは契約書の種類によるので、一概にいうことは難しいですが、誰と誰の間の契約なのか、業務の内容は具体的に何か、納期、対価(支払い金額)、支払期日などがその例として挙げられます。
ファッションローガイドブックでは、外部クリエイターとの契約書に記載するべき内容の項目が箇条書きで列挙されており、外部の方と契約をする場合に確認すべき最低限の項目を知ることができます。
ファッション業界の企業が今後気をつけるべきポイント
ファッションローガイドブックでは、ファッションブランドの経営に際して問題となる法的課題についての概要を幅広く説明しています。
そのため、何か法的な問題があった際に、ファッションローガイドブックを参照してどのような法的な課題があるのかを把握するのはとても重要なことです。
しかし、企業では法的な問題が発生し、しばらくしてから弁護士に相談をいただくケースも多くあり、その場合には後手にまわってしまい効果的な解決が困難であるということもしばしばあります。
ファッションビジネスにおいてもそれは例外ではなく、先回りをした対応が求められます。
ファッションブランドを立ち上げる際に、前もって商標登録手続きを行ったり、外部の者と契約を締結する場合の契約書を作成したりすることは、高度な法的知識が求められるものであるため、自社ですべてを行うのは容易ではありません。
また、商標登録は特許庁に対して商標出願を行うものであるため、記載を誤ったり、提出書類の不備により、かえって時間がかかってしまうということにもなりかねません。
そのため、ファッションブランドの法的問題にお悩みの場合には、速やかに弁護士などの専門家のサポートを受けるようにしてください。
Authense法律事務所がお力になれること
Authense法律事務所では、ファッションローに関するサポートに力を入れています。商標出願をしたい場合、自社商品の模倣品が販売されており模倣品の販売を差止めたり、損害賠償請求をした場合や、外部との契約書の作成や確認を弁護士に依頼したい場合は、Authense法律事務所までご相談ください。
Authense法律事務所には、ファッションローについての豊富な経験と実績を有する弁護士が在籍しており、Authense Professional GroupのAuthense弁理士法人との連携もしているため、法律のプロである弁護士と知的財産のプロである弁理士にあわせてご相談していただくことも可能です。
これまでにグループとして蓄積した専門的知見を活用しながら、弁護士及び弁理士が、ご相談いただいたファッションブランド様のブランド価値をともに守らせていただきます。
-
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
-
メールでご相談予約
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00