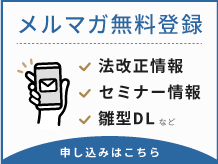<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
はじめに
海外企業との国際取引では、契約書が特に重要となります。
あいまいな契約をしてしまったり、内容を理解しないまま相手に提示された契約書をそのまま受け入れてしまったりすれば、思わぬトラブルに発展してしまうかもしれません。
今回は、当事務所が解決した、海外企業との契約についてご紹介します。
国際取引は、特に専門的な知識が必要となる分野のため、トラブルを避けるためにも、あらかじめ国際取引を専門とする弁護士へ相談し、契約書の確認をしてもらうなどの対策をとることが大切です。
ご相談までの経緯・背景
中国からの輸入品を販売しているBさんは、取引をしている中国のX社との間に契約書を作成していないことが気がかりでした。
その会社には、商品の買い付けはもちろん、商品タグの取り付けや商品の管理、顧客への発送など、Bさんのビジネスの根幹を担う業務を依頼していました。
しかし、ときおり依頼業務の実施態様が杜撰であるなど、顧客からのクレームに発展することもありました。
このままではいつか取り返しがつかなくなるかもしれないと考えたBさんは、X社と依頼業務の内容や補償や賠償請求など含めた契約を書面にて交わしたいと考え、当所にお見えになりました。
解決までの流れ
X社は中国の企業なのですが日本での業務を委託している会社があり、Bさんはその日本の会社とやり取りをしていました。
しかし、X社は中国資本の企業であるため、問題が起こった際には日本と中国、どちらの裁判所で、どちらの国の法律を基準に考えるのかが曖昧な状態でした。
さっそくX社に連絡を入れ、「契約書を作成しましょう」と打診すると快諾。順調に話が進むかと思いきや、法律の壁が立ちはだかりました。
X社は「うちは中国の企業なので、中国法で、中国の裁判所で」と譲りません。
しかし、それではBさんにとってリスクでした。
そこで、日本法、日本の裁判所を管轄にするためにはどうすればよいか考えました。
Bさんにとって、煩雑かつ大量の業務を安価で引き受けてくれるX社は命綱でした。
他方で、大量の発注をしてくれるBさんは、X社にとって大切な顧客でもありました。
そこで、「日本法、日本の裁判所を管轄とした契約でなければ、今後は取引ができない」と、交渉していきました。
並行して、同様の取引で日本法、日本の裁判所を管轄としたケースはないか、専門書籍や判例・裁判例をリサーチしました。
その結果、資本は中国の企業でも、日本法、日本の裁判所を管轄とすることも一応可能であり、また、日本の会社を巻き込むことで、よりそのような結論が説得的になるとの結論に至りました。
そこで、最終的には、日本の会社に連帯保証をしてもらう形で、望み通りの契約内容となりました。
結果・解決ポイント
相手方との交渉の際には、互いの立場を見極めることが大切です。
BさんにとってX社が欠かせない存在であったと同時に、X社にとってもBさんからの売上は無視できない金額でした。
BさんがX社に業務面においてかなりの依存をしていることを先方は知りませんので、「もしかしたら他社に乗り換えられるかもしれない」と思わせるよう、強気に交渉したことが解決につながったのではないかと思います。
また、徹底的にリサーチを行ったことも強気の交渉を可能にした一因です。
グローバル化が進む昨今、海外企業とのやり取りは増加しています。
トラブルが発生しても泣き寝入りしなくても良いように、事前に契約を書面にて交わしておくことの重要性はますます高まっています。
日本法とは異なる準拠法で運営している海外企業との契約の際には、現地の法律や商習慣などを理解した上での交渉が必要になります。
お困りの際には、海外企業との交渉経験が豊富な弁護士に、まずは一度ご相談ください。
-
些細なご相談もお気軽にお問い合わせください
-
メールでご相談予約
平日:10:00~最終受付18:00 /
土日祝:10:00~最終受付17:00