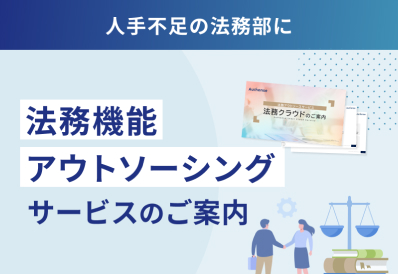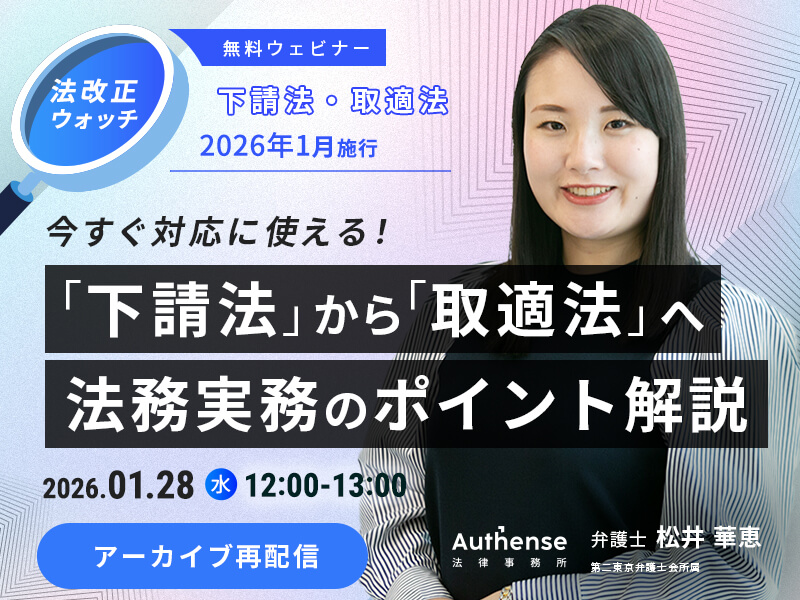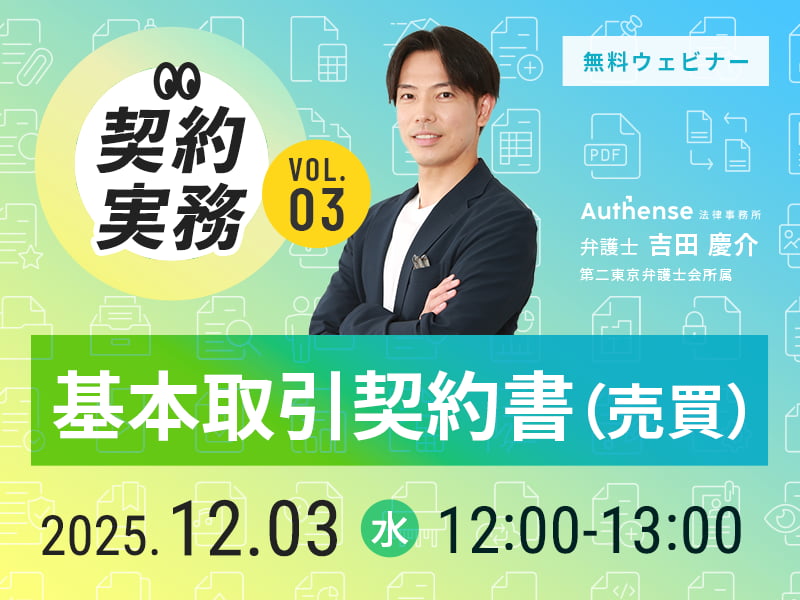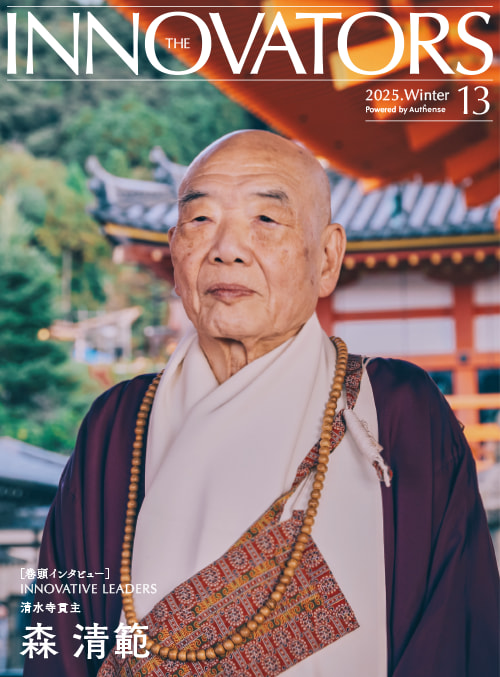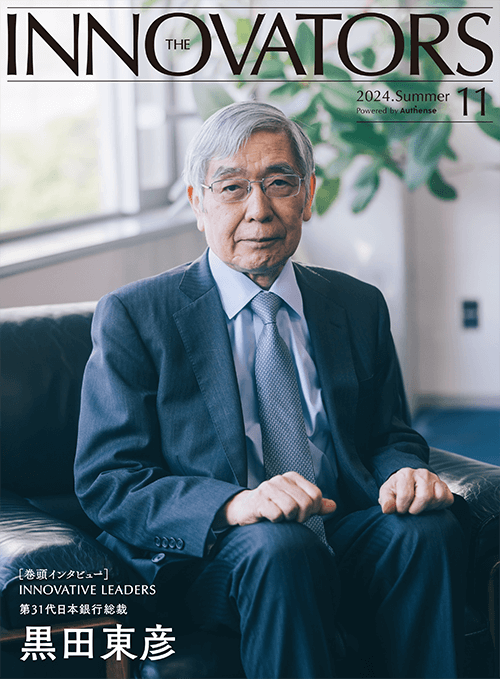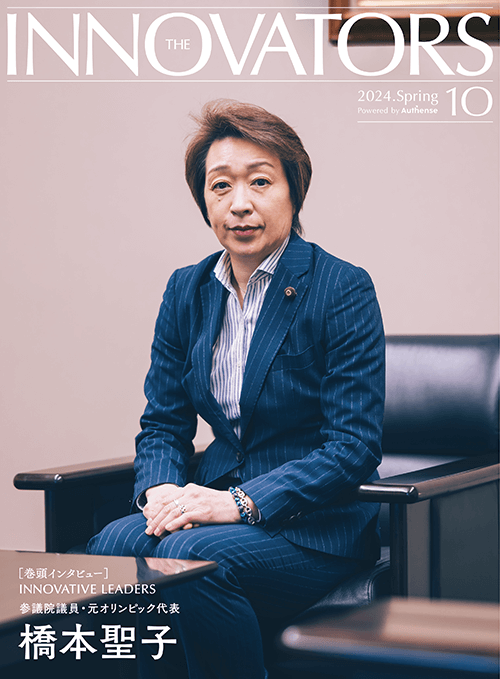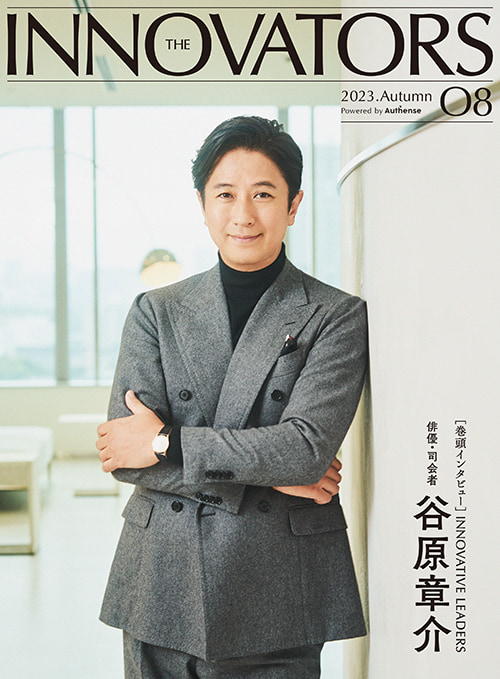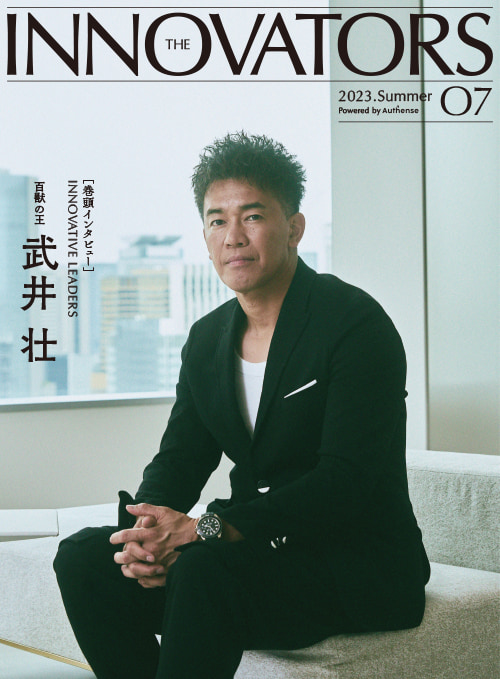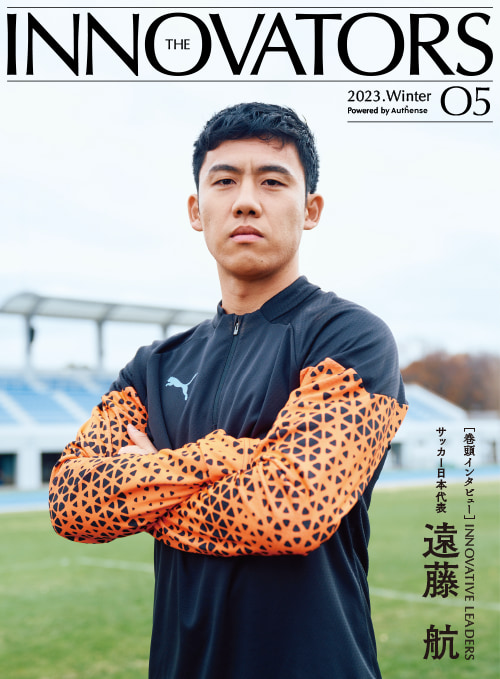自社で粉飾決算が生じると、民事・刑事での責任追及など企業にとって多大な影響が生じます。
では、粉飾決算はなぜ起きてしまうのでしょうか?
また、粉飾決算について弁護士へ相談することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、粉飾決算の概要や主な目的などを紹介するとともに、粉飾決算について弁護士に相談するメリットなどを解説します。
なお、当法律事務所「Authense法律事務所」は企業法務に特化したチームを設けており、粉飾決算が起きてしまった場合の対応や予防策などについてもご相談いただけます。
粉飾決算について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご連絡ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
粉飾決算とは
粉飾決算とは、企業の経営実績や財務状況を実際よりもよく見せるために行われる不正な会計処理です。
粉飾決算の目的は後ほど改めて解説しますが、金融機関からの融資の引出しや株価低迷を避ける目的などで行われることが多いでしょう。
逆粉飾決算との違い
「逆粉飾決算」も不正な会計処理の1つであるものの、企業の経営実態や財務状況を実際よりも「悪く」見せるために行われる点で粉飾決算とは異なります。
逆粉飾決算は、法人税額の軽減などを目的として行われることが多いでしょう。
不適切会計との違い
「不適切会計」も、企業の経営実態や財務状況を実際よりもよく見せかける点では粉飾決算と同じです。
ただし、粉飾決算は意図的に行われるものであるのに対し、不適正会計には意図的なもののほかミスによるものも含まれる点で異なります。
粉飾決算の主な目的
粉飾決算は、どのような目的で行われるのでしょうか?
粉飾決算がなされる主な目的を4つ解説します。
金融機関からの融資を引き出すため
1つ目は、金融機関からの融資を受ける目的です。
金融機関は、業績の芳しくない企業への融資に消極的になる傾向にあります。
一方で、業績が良く財務体質も健全であると判断されると、よい条件での融資を受けやすくなるでしょう。
そこで、金融機関からの融資を引き出すために粉飾決算を行い、業績や財務状況が良好であるように見せかけることがあります。
株価の低迷を避けるため
2つ目は、株価の低迷を避ける目的です。
上場企業である場合、企業の業績や株価へと直結します。
株主が期待した業績が出せないと、株価が低迷するほか、株主総会で役員の責任を追及される事態ともなりかねません。
そこで、これらを避ける目的で粉飾決算に手を染めることがあります。
公共工事に入札するため
3つ目は、公共工事などに入札する目的です。
公共工事に参入するには、その工事についての入札に参加して落札する必要があります。
しかし、多くの公共工事では入札のために一定の条件が付されており、業績によっては入札への参加さえできない可能性が生じます。
そこで、実際には業績面で入札への参加資格を満たしていないにもかかわらず、満たしていると見せかける目的で粉飾決算に手を染める場合があります。
不正行為を隠ぺいするため
4つ目は、不正行為を隠ぺいする目的です。
ここまでで紹介した3つの目的は、経理担当者などの個人の利益のためではなく、会社の利益のために誤った忖度をした結果であるといえます。
一方で、経理担当者や営業担当者などが自らの不正行為を隠ぺいする目的から、粉飾決算がなされるケースもゼロではありません。
たとえば、取引先の担当者などと結託して架空の取引をでっち上げたり実際の取引金額を改ざんしたりして、その見返りとして個人的にリベートを受け取る行為などがこれに該当します。
粉飾決算の主な手口
粉飾決算は、どのような手口で行われるのでしょうか?
ここでは、主な粉飾決算の手口を4つ紹介します。
なお、これらの手口は一般的によく知られており、隠し通すことは容易ではないでしょう。
架空売上の計上
架空売上の計上とは、実際には取引がないにもかかわらず商品やサービスを販売したと見せかけて、会計上のみで収益を計上する行為です。
会計上記載される取引先名は実在する企業や個人である場合もある一方で、架空の企業などとする場合もあるでしょう。
また、取引自体は実際に存在するものの、売上金額を実際よりも多く見せかけて計上する場合もあります。
在庫の過大計上
在庫の過大計上とは、期末在庫を実際よりも多く計上することで、業績がよいように見せかける行為です。
在庫の過大計上によって業績をよく見せられるのは、期末在庫が多ければそれだけその期に計上すべき仕入高が小さくなるためです。
原則として、その期に計上する仕入高は「期首在庫+当期仕入高-期末在庫」で計算するため、期末に残っている在庫が多いと、それだけその期の仕入れ高を少なく見せることが可能となります。
たとえば、実際には期首在庫が80、当期仕入高が200、期末在庫が50である場合、その期に計上すべき仕入高は230(=80+200-50)となります。
このとき、期末在庫を100に過大計上すると、その期に計上する仕入高は180(=80+200-100)に膨れ上がるということです。
これも、よく行われる粉飾決算の手法の1つといえます。
循環取引
循環取引とは、実際には商品やサービスを販売していないにもかかわらず、複数の企業間で利益を乗せて売上を循環させる行為です。
たとえば、A社からB社に対して50を売り上げ、B社からC社に対して70を売り上げ、C社からA社に90を売り上げ、というように、各社が架空の利益を乗せつつ、数字上だけで売上を循環させる場合などがこれに該当します。
循環取引もよく行われる粉飾決算手法の1つです。
実際にはこのように単純なものではなく、取引を複雑にして発覚しないよう細工する場合が多いでしょう。
経費の付け替え
経費の付け替えとは、本来はその期に計上すべき経費を翌期の経費としたり、実際にはその期に一括で計上すべき経費を固定資産などとして減価償却の対象としたりする行為です。
減価償却とは、機械装置や自動車など一定の資産を購入した場合に、これをその期だけの経費とするのではなく、複数年に渡って一定額ずつ(または、一定割合ずつ)計上するものです。
本来はその期に一括で計上すべき経費を固定資産として計上することで、その期に計上する経費が少なくなり、業績を実際よりもよく見せかけることにつながります。
粉飾決算で問われる主な責任
粉飾決算が発覚した場合、企業はどのような責任を問われる可能性があるのでしょうか?
ここでは、民事責任と刑事責任、社会的責任とに分けてそれぞれ解説します。
これから紹介するように、粉飾決算をすると企業や役員にとってさまざまな影響が生じます。
そのような事態を避けるため、日ごろから内部統制システムを構築するなど不正の抑止に努める必要があるでしょう。
民事責任
粉飾決算をした場合、民事責任を追及される可能性があります。
たとえば、粉飾した虚偽の決算書を信じて融資をした金融機関から融資の一括返済を求められる可能性があるほか、損害賠償責任を追及される可能性があるでしょう。
また、株主から粉飾決算を生じさせた責任を問われ、役員に対して会社への損害賠償を求められる場合もあります。
刑事責任
粉飾決算をして不正に融資を受けた場合、詐欺罪などの罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法246条)。
また、取締役などの役員が自身や第三者の利益を図るために粉飾決算に関与した場合には、特別背任罪などの罪に問われることもあります。
特別背任罪の法定刑は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科です(会社法960条)。
社会的責任
粉飾決算が明るみに出た場合、企業イメージが失墜し、顧客や取引先が離反するおそれが生じます。
また、株価が大きく低迷する可能性もあるでしょう。
さらに、粉飾決算の内容によっては上場廃止となる可能性も否定できません。
自社で粉飾決算が起きた際に弁護士に相談するメリット
自社で粉飾決算が行われていることに気付いたら、早期に弁護士へ相談しましょう。
最後に、粉飾決算について弁護士へ相談する主なメリットを4つ解説します。
- 適切な調査が可能となる
- 適切な対処がしやすくなる
- 裁判手続きを代行してもらえる
- 適切な再発防止策を講じやすくなる
適切な調査が可能となる
自社で粉飾決算が起きた場合、まずはその実態や原因、粉飾決算に関与した人物などについて的確に調査する必要が生じます。
調査が不十分であると誤った処分をするおそれが生じるほか、再発防止策を講じても的外れなものとなるおそれもあるためです。
しかし、この調査を自社だけで的確に行うことは容易ではないでしょう。
弁護士に依頼することで、粉飾決算に関して的確な調査をしやすくなります。
適切な対処がしやすくなる
粉飾決算の内容や原因などによっては、関係者を懲戒処分すべき場合もあるでしょう。
たとえば、経理担当者が横領していた場合において、その経理担当者を懲戒解雇することなどが挙げられます。
ただし、懲戒処分は原則として自社の懲戒規程に則って行う必要があるほか、たとえ懲戒規程を備えていても実際の行為に比して処分の内容が重すぎると、処分の無効などを主張されてトラブルとなるおそれも生じます。
弁護士にサポートを依頼することで、粉飾決算の実行者に対する適切な対処をとりやすくなります。
裁判手続きを代行してもらえる
先ほど解説したように、粉飾決算では民事責任などが追及され、裁判に発展する場合もあります。
たとえ裁判に至っても、弁護士が代理できるため企業の負担を軽減できます。
適切な再発防止策を講じやすくなる
自社で粉飾決算が起きた場合、今後自社で同様の事態が起きないよう再発防止策を講じるべきでしょう。
とはいえ、具体的にどのような対策を講じるべきかわからない場合も多いと思います。
弁護士のサポートを受けることで、自社に合った効果的な再発防止策を講じやすくなります。
粉飾決算の対策や対応はAuthense法律事務所へご相談ください
粉飾決算は、不正な会計処理によって企業の業績を実際よりもよく見せる行為です。
金融機関から融資を引き出す目的や株価の低迷を防ぐ目的、公共工事に入札する目的などから行われる場合もある一方で、経理担当者などが自身の横領を隠ぺいする目的で行うこともあるでしょう。
自社で粉飾決算が起きた場合には、粉飾された決算書類を信じて融資をした金融機関などから損害賠償を請求されるおそれがあるほか、上場廃止となったり企業の信用が失墜したりするおそれも生じます。
そのような事態を避けるため、内部統制システムを構築するなど、日ごろから粉飾決算を防ぐ対策を講じておくべきでしょう。
すでに粉飾決算が起きてしまっている場合には、早期に弁護士にご相談ください。
弁護士へ相談することで、的確な調査や対処をとることが可能になり、裁判においても代理人となってもらえるほか、自社に合った再発防止策についてアドバイスを受けることもできます。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、粉飾決算の対処や予防策に関するアドバイス・サポートも可能です。
粉飾決算についてお困りの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。