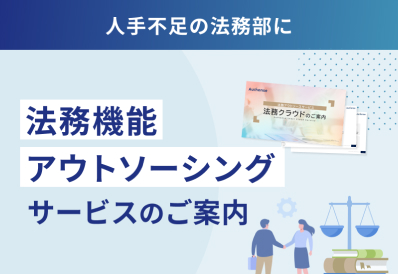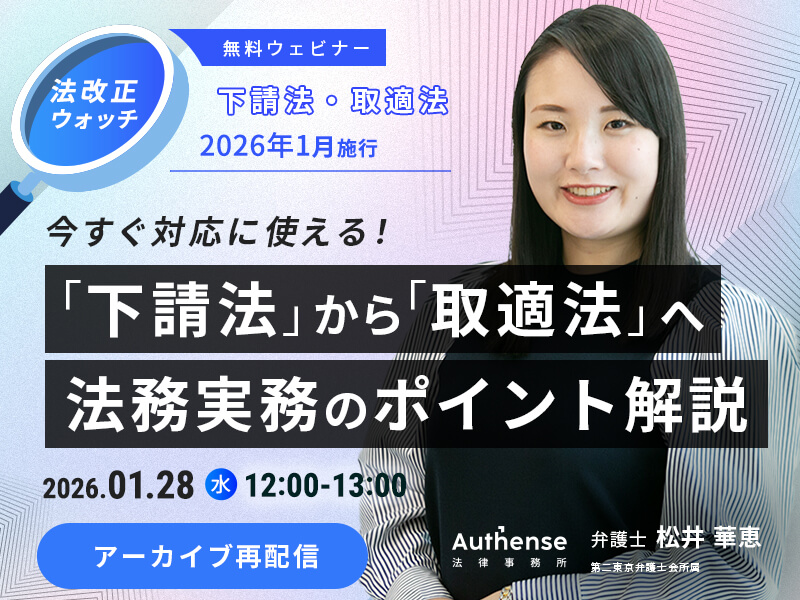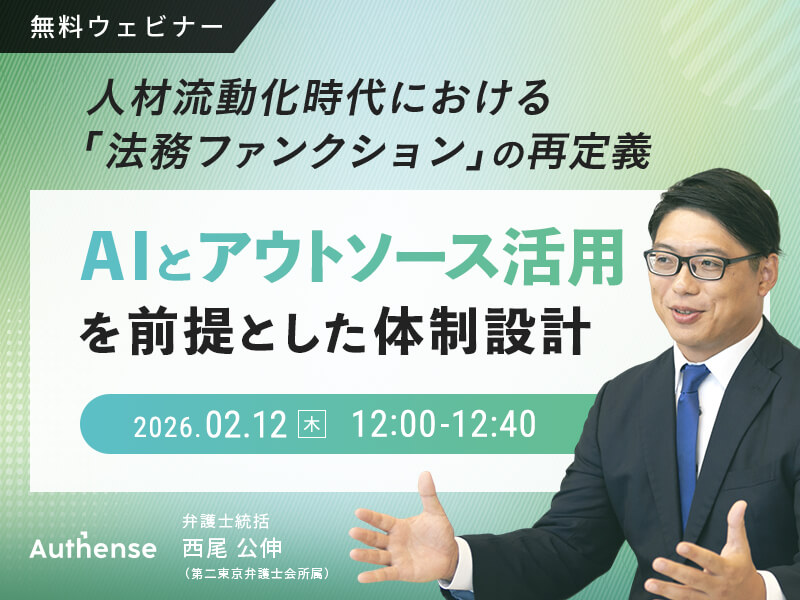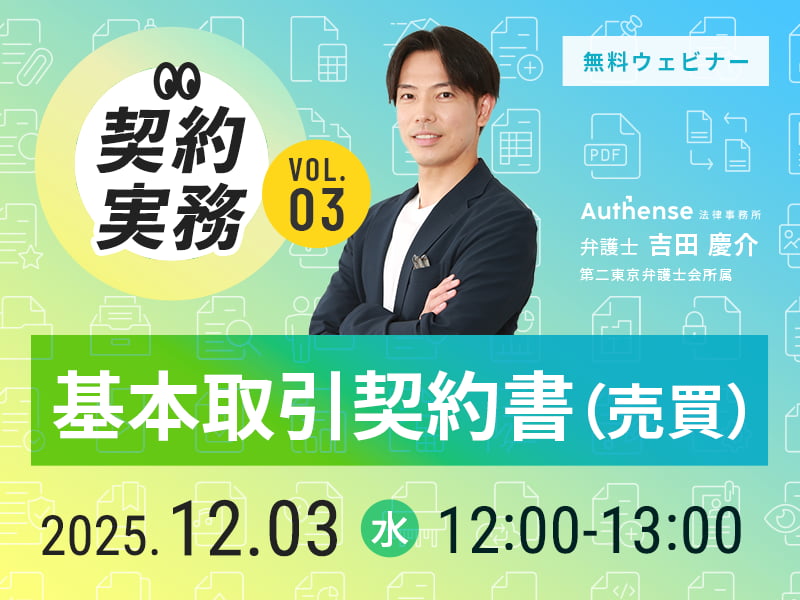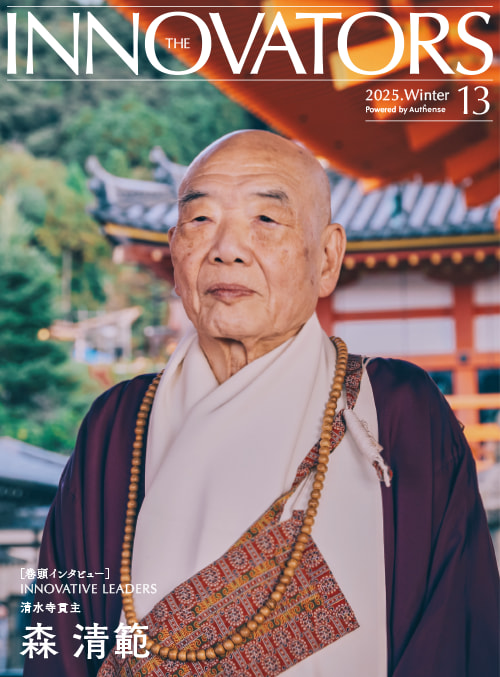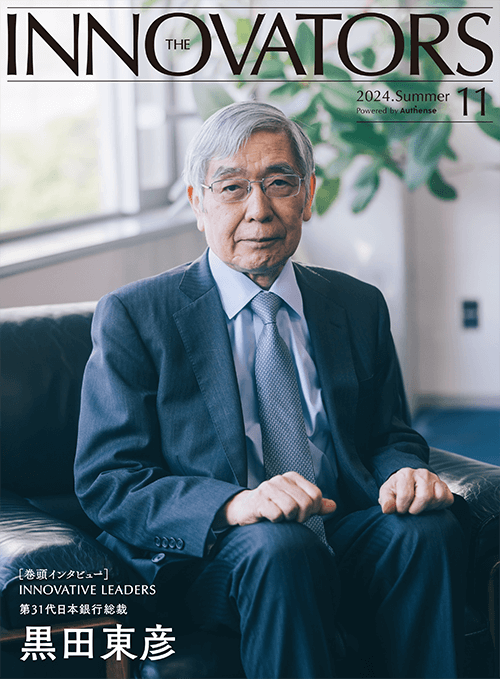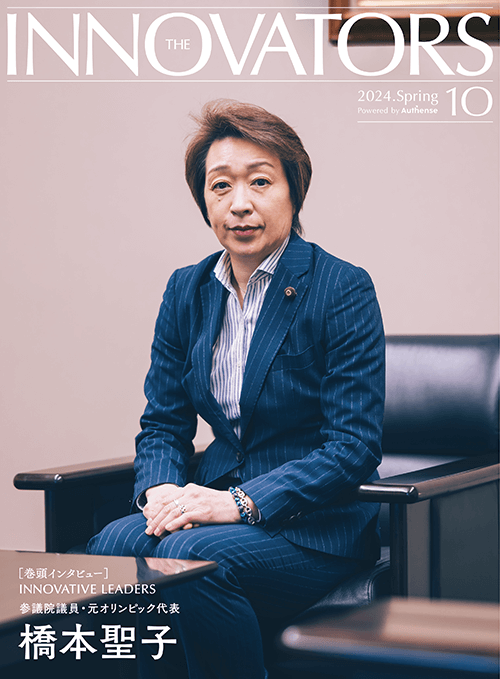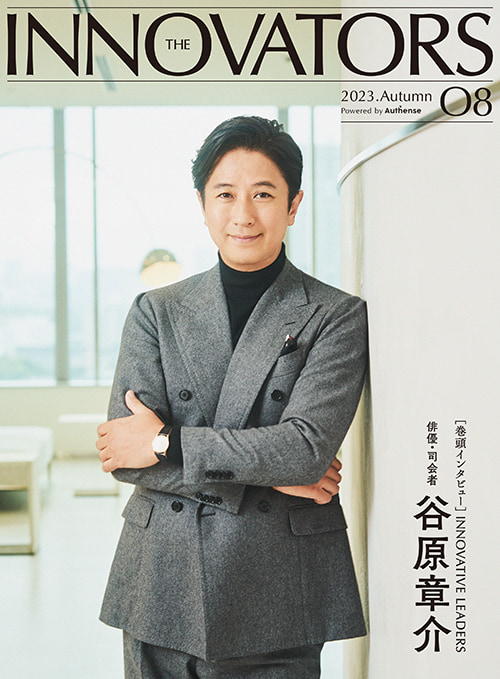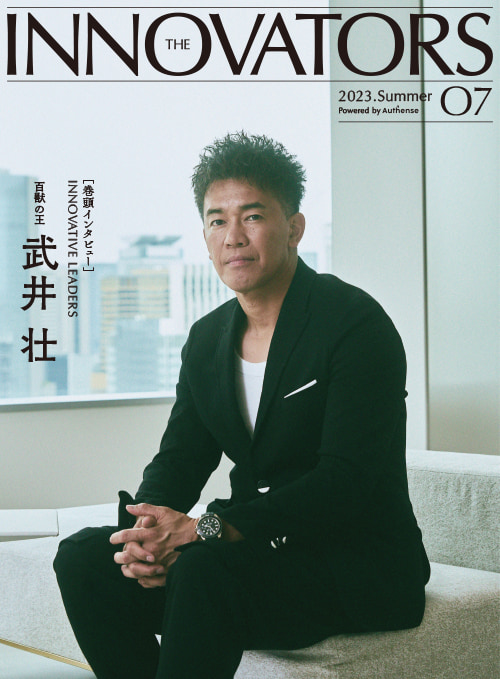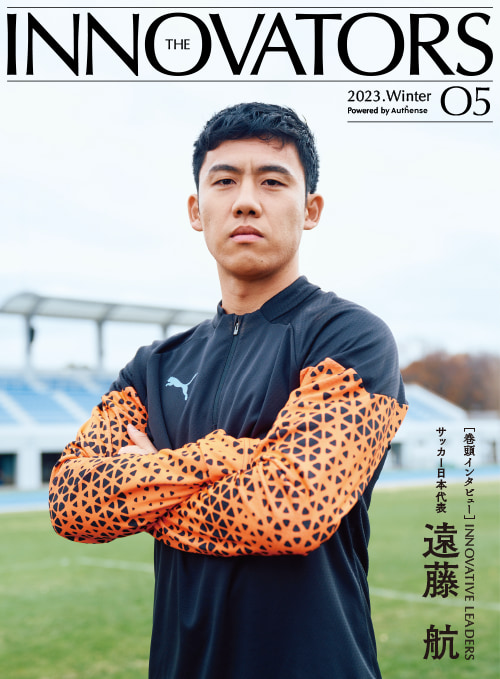内部通報制度は、企業のリスク情報を早期に把握し、不祥事を未然に防ぐための手段です。
2022年6月に施行された改正公益通報者保護法により、従業員300人超の企業には、適切な内部通報制度の構築が義務付けられることとなりました。
従業員数がこれに満たない企業であっても、不祥事を抑止しさらなる企業成長を目指すため、内部通報制度の導入を検討するとよいでしょう。
では、内部通報制度への対応には、どのような選択肢があるのでしょうか?
また、内部通報対応を弁護士に任せることには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
ここでは、内部通報制度の概要や内部通報対応の選択肢、内部通報対応を弁護士に依頼するメリットなどについてくわしく解説します。
なお、Authense法律事務所は内部通報制度の構築から通報受付、社内調査、関係者への処分に至るまで、総合的な運用支援を提供しています。
内部通報対応について相談・依頼ができる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
内部通報制度とは
内部通報制度とは、組織内の不正行為に関する通報や相談を受け付け、調査・是正する制度です。
企業内の不正を早期に発見し、企業と従業員を守ることが目的とされます。
企業の規模が一定以上になると、経営陣が社内の隅々にまで目を配ることが困難となり、多かれ少なかれ不正行為が生じやすくなります。
当初は一部の従業員による小さな不正であったとしても、これが発覚しないと不正行為がエスカレートしたり、不正行為が社内で横行したりする可能性があるでしょう。
経営陣が気付いたときにはすでに被害額が非常に多額に上っていたり、大々的な報道やSNSへの投稿などで広く世間に知られたりして、被害の回復が困難となるおそれが生じます。
内部通報制度を導入することで、早い段階で不正を発見しやすくなり、被害を最小限に留めやすくなります。
内部通報対応に関する主な選択肢
内部通用制度について、企業はどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、内部通報対応の主な選択肢を3つ紹介します。
- 社内に内部通報窓口を設置する
- 外部の弁護士を内部通報窓口とする
- (従業員300人以下の事業者)内部通報窓口を設置しない
社内に内部通報窓口を設置する
1つ目の選択肢は、社内に内部通報窓口を設置する方法です。
社内に窓口を設置する場合、総務部や人事部を窓口とすることが多いでしょう。
外部の弁護士を内部通報窓口とする
2つ目の選択肢は、外部の弁護士を内部通報窓口とする方法です。
内部通報対応を任せる弁護士は、「顧問弁護士」と「顧問弁護士ではない弁護士」の2つのパターンが想定できます。
(従業員300人以下の事業者)内部通報窓口を設置しない
3つ目の選択肢は、内部通報窓口を設置しない方法です。
従業員数300人以下の事業者にとって、内部通報窓口の設置は義務ではありません。
そのため、窓口を設置しないことも選択肢に入ります。
ただし、企業がある程度組織化されており、今後も事業を健全に継続したいと考えている場合は、法律の規定にかかわらず内部通報窓口の設置を検討すべきでしょう。
内部通報窓口を社外の弁護士とする主なメリット
内部通報窓口を社外の弁護士とすることには、多くのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを5つ解説します。
- 社内の人間関係を気にすることなく通報できる
- 経営幹部からの不当な干渉を避けられる
- 専門家の知見を活用できる
- 社内のリソースを圧迫しない
- 企業の高いコンプライアンス意識をアピールできる
なお、Authense法律事務所は、ご希望に応じて内部通報対応を担うことが可能です。
内部通報窓口を弁護士へ依頼したいとお考えの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
社内の人間関係を気にすることなく通報できる
1つ目は、社内の人間関係を気にすることなく通報ができることです。
内部通報窓口を社内に設置する場合、通報に対応するのも社内の従業員です。
そのため、通報の対象者と何らかの関係があることを懸念する場合もあるでしょう。
内部通報の対応者には守秘義務が課されているとはいえ、通報者が「窓口担当者と通報の対象者とが親しければ、通報したことが本人に伝わってしまうかもしれない」と不安を抱き、通報をためらう可能性は否定できません。
内部通報窓口を外部の弁護士に依頼する場合は、社内の人間関係を気にすることなく通報することが可能となります。
経営幹部からの不当な干渉を避けられる
2つ目は、経営幹部からの不当な干渉を避けられることです。
内部通報のなかには、経営幹部にとって都合の悪い内容もあるでしょう。
内部通報窓口を社内に設置する場合、自身にとって都合の悪い通報があった際、経営幹部が圧力をかけて、通報者の情報を聞き出したり通報の存在を隠ぺいしたりする可能性が否定できません。
内部通報窓口を外部の弁護士とすることで、このような不当な干渉を受けづらくなります。
専門家の知見を活用できる
3つ目は、専門家の知見を活用できることです。
内部通報窓口になされた相談の内容によっては、犯罪行為に関するものなど社内だけでの対応が難しいものもあるでしょう。
内部通報窓口を外部の弁護士とすることで、弁護士が有する知見を最大限に活用したうえで適切な対応が可能となります。
社内のリソースを圧迫しない
4つ目は、社内のリソースを圧迫しないことです。
社内の総務部や人事部などに内部通報窓口を設置しようにも、総務部や人事部が多忙であり、内部通報対応に人員を割けない場合も少なくありません。
そもそも内部通報への対応には高い倫理観が求められるため、内部通報への対応のために新たに雇用する人ではなく、長年の勤務で信頼関係が築けている従業員が望ましいといえます。
そのような人は他にも多くの業務を担っており、内部通報対応のための時間をとることが難しい場合も多いことでしょう。
社外の弁護士に対応を依頼する場合、社内のリソースを圧迫することなく内部通報窓口の設置を実現できます。
企業の高いコンプライアンス意識をアピールできる
5つ目は、企業の高いコンプライアンス意識を、ステークホルダーに向けてアピールできることです。
社外の弁護士を内部通報窓口とする場合、都合の悪い通報内容を握りつぶしたり、窓口担当者に圧力をかけて通報者の情報を聞き出したりすることは困難となります。
これは、場合によっては経営陣にとって都合が悪い一方で、自社の不正を一掃したいという覚悟のアピールともなるでしょう。
内部通報窓口を顧問弁護士とする主なデメリット・注意点
内部通報窓口を社外の弁護士とする場合、顧問弁護士とするか、顧問弁護士以外の弁護士とするか迷う場合もあるでしょう。
ここでは、判断の参考とするために、顧問弁護士に内部通報対応を依頼するデメリットと注意点を2つ解説します。
顧問弁護士の場合には利益相反のリスクが生じる
企業が契約をしている顧問弁護士は、企業の利益を守る役割を担います。
企業と従業員とが同じ方向を向いている場合には会社を守る一環として従業員も守る場合もあるものの、企業と従業員の利害が対立する場合には企業側につくこととなるでしょう。
しかし、内部通報対応においては、従業員側から企業で横行している不正を通報される場合もあり、企業と従業員との利害が対立する場面も想定されます。
また、その後企業を相手取った訴訟に発展することもあり、この場合において窓口となった顧問弁護士は通報者側の代理人となることはできません。
このように、顧問弁護士に内部通報対応を依頼する場合には、弁護士に利益相反のリスクが生じます。
従業員が通報をためらうおそれが生じる
繰り返しとなりますが、企業の顧問弁護士は企業の利益を守る役割を担います。
つまり、企業と通報者との利益が対立することとなった場合、その弁護士は企業側につくということです。
そのため、内部通報窓口である弁護士に伝えた内容が、その後の訴訟において自身に不利となる証拠として使われることを恐れた従業員が通報をためらい、内部通報制度が適切に機能しなくなる可能性があります。
Authense法律事務所は、内部通報制度への対応を支援するとともに、通報対応も行っています。
顧問弁護士がいる場合において、内部通報対応を任せられる顧問弁護士以外の弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
弁護士ができる主な内部通報対応
内部通報制度に関して、弁護士はどのような対応が可能なのでしょうか?
最後に、弁護士が担う主な内部通報対応について解説します。
- 内部通報体制構築へ向けた法的助言
- 内部通報への対応
- 内部通報を受けた内容の調査
- 通報者のケアなどに関するアドバイス
なお、具体的なサポート内容は弁護士によって異なる可能性があるため、実際に内部通報対応を依頼しようとする際は、その弁護士によるサポート内容をあらかじめ確認するとよいでしょう。
内部通報対応を依頼する弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
企業の状況や規模、業種、ご希望などに応じ、具体的なサポート内容を提案します。
内部通報体制構築へ向けた法的助言
弁護士は、内部通報体制の構築へ向けた法的な助言を行います。
内部通報制度に対応しようにも、何から手を付ければよいかわからない企業も多いでしょう。
内部通報窓口の設置は、単に人事部などを「相談窓口」として指定すればよいだけではありません。
内部通報対応の責任者や対応部署を指定したうえで、通報に対して適切に対応するための研修を実施したり、内部規程・対応マニュアルを整備したりするステップも必要です。
弁護士は、行うべき対応を具体的にアドバイスするとともに、研修の実施や社内規定などの整備についてもサポートします。
内部通報への対応
内部通報対応として弁護士を指定する場合、実際の通報への対応を行います。
法律の規定に従った的確な対応を行うため、企業が適法な内部通報対応を実現できるほか、通報者も安心して通報しやすくなります。
内部通報を受けた内容の調査
内部通報制度は、単に相談を受けるだけの窓口ではなく、通報内容を受け、具体的な対応や改善策などを講じる制度です。
内部通報によって不正行為が発覚した場合には、その不正に対して厳正に対処すべきでしょう。
しかし、寄せられた通報の内容がすべて真実であるとは限りません。
そのため、内部通報を受けたら、その内容について調査をする必要が生じます。
弁護士に内部通報対応を依頼する場合、内部通報がされた内容に関する調査についても任せることが可能です。
通報者のケアなどに関するアドバイス
弁護士は、通報者のケアなどに関するアドバイスを行います。
内部通報者がハラスメントを受けているなど、通報の内容によっては通報者のケアが必要な場合も存在します。
その場合には、調査をして通報内容が事実であると判断した時点で、行為者を異動させたり懲戒処分をしたりするなどの措置が必要となるでしょう。
この際、通報者を不利益に取り扱うことのないよう、十分に注意しなければなりません。
たとえば、行為者と引き離すために通報者である被害者を希望とは異なる部署に異動させたり、出勤停止を命じたりすることは避けるべきといえます。
また、行為の内容に比して懲戒処分の内容が重すぎると、行為者側から処分の無効を主張されトラブルとなるおそれもあるでしょう。
認識不足から誤った対応をすることのないよう、弁護士は事案に応じた適切な対応を助言します。
まとめ
従業員数が300人超である企業は、内部通報制度に適切に対応しなければなりません。
内部通報制度への対応方法としては、社内に内部通報窓口を設置する方法のほか、外部の弁護士に内部通報対応を担ってもらう方法があります。
弁護士に内部通報対応を依頼する主なメリットとしては、従業員が社内の人間関係を気にすることなく通報ができることや、専門家による知見が活用できること、社内のリソースの圧迫を避けられることなどが挙げられます。
内部通報制度への適切な対応を実現するため、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。
Authense法律事務所は、内部通報体制の整備支援や、窓口としての内部通報対応などを行っており、企業のコンプライアンス体制の強化を支援しています。
内部通報対応を任せられる実績豊富な弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にお問い合わせください。