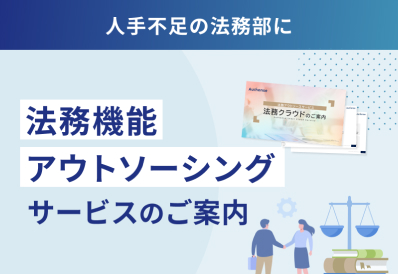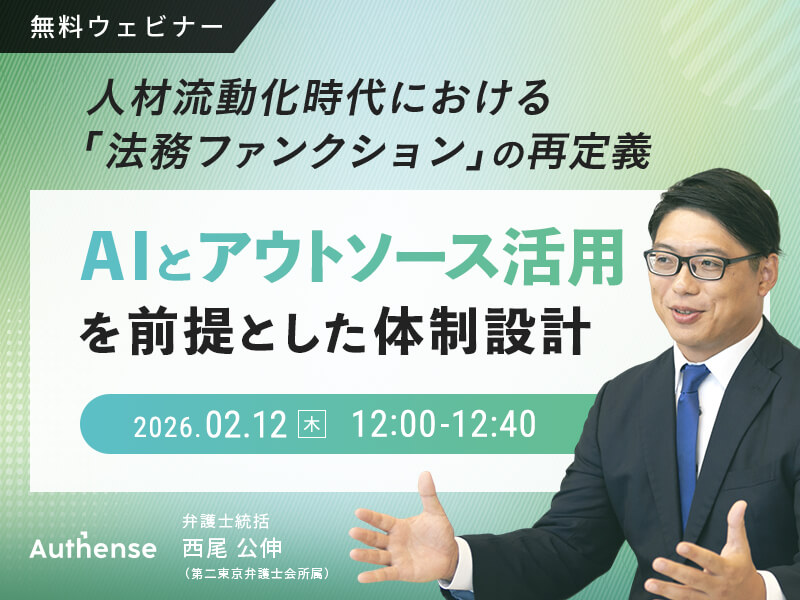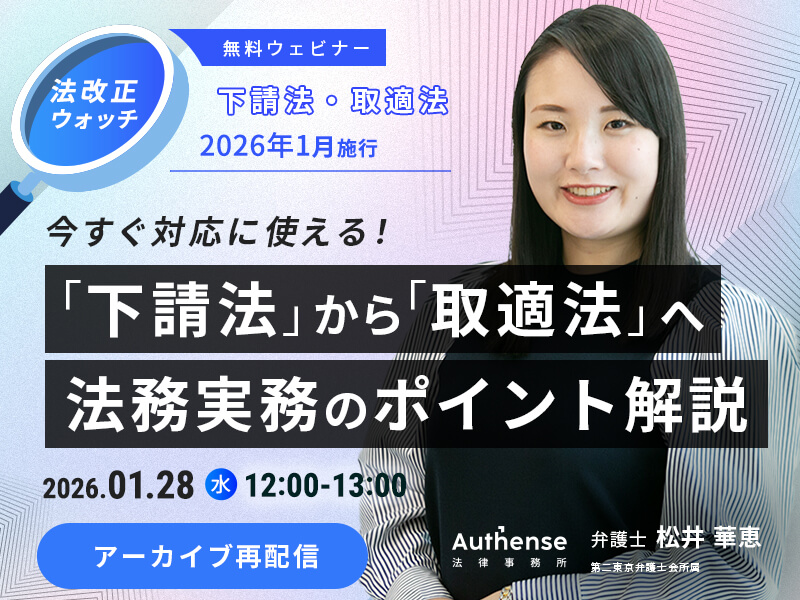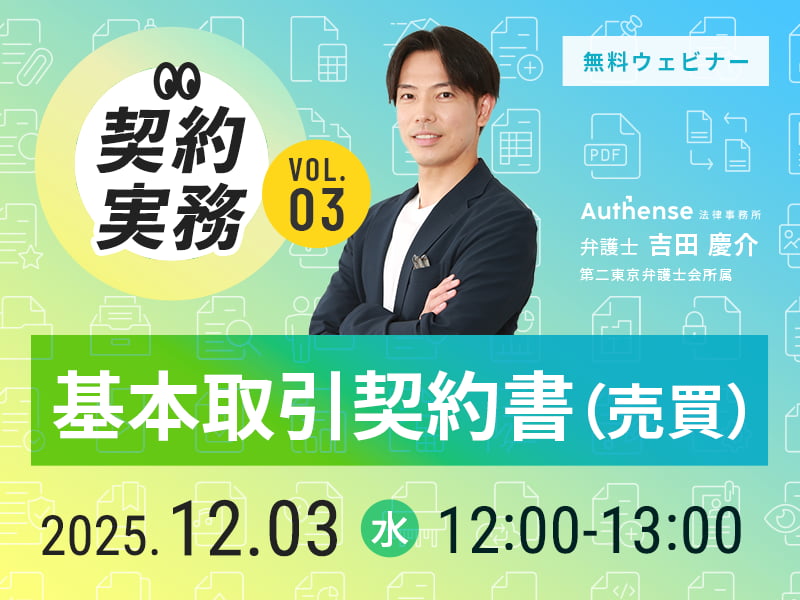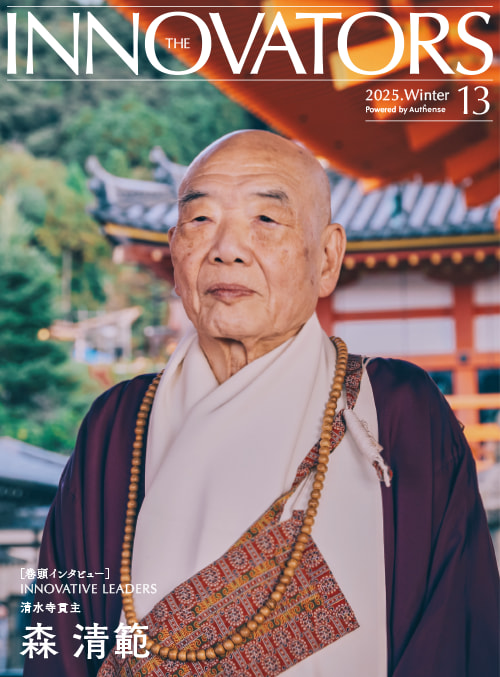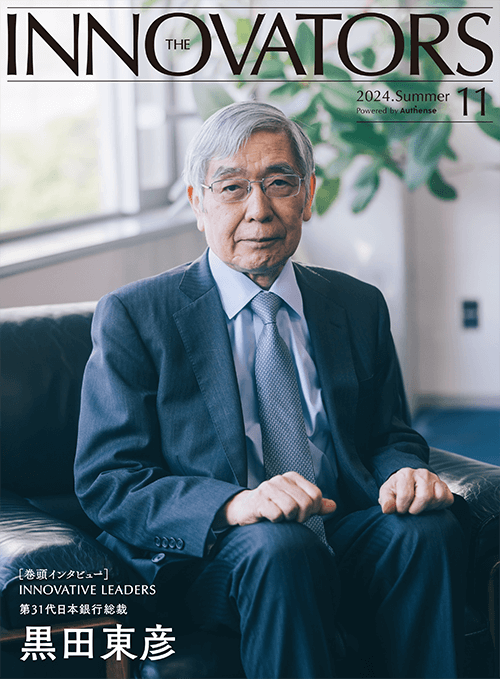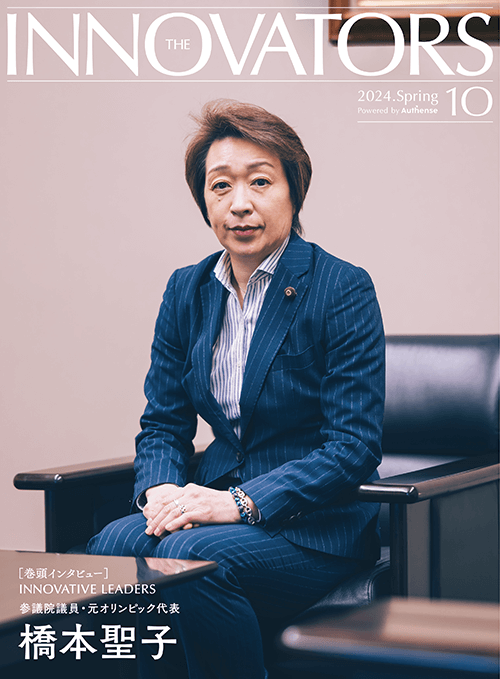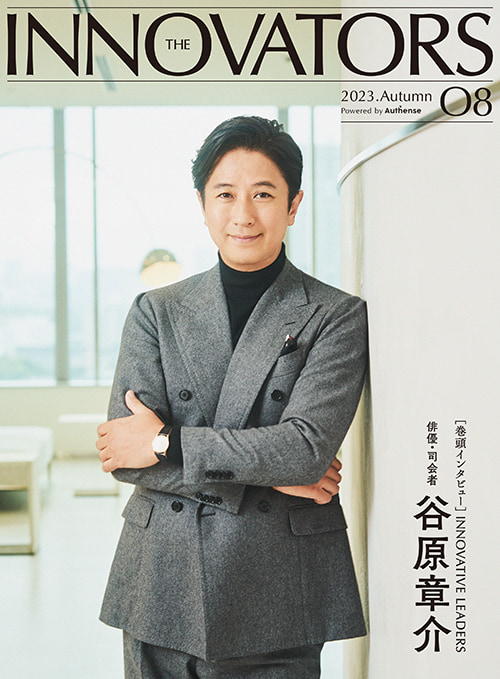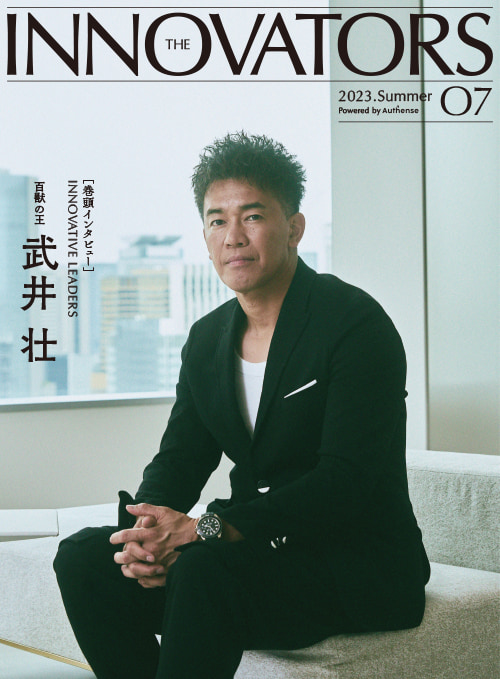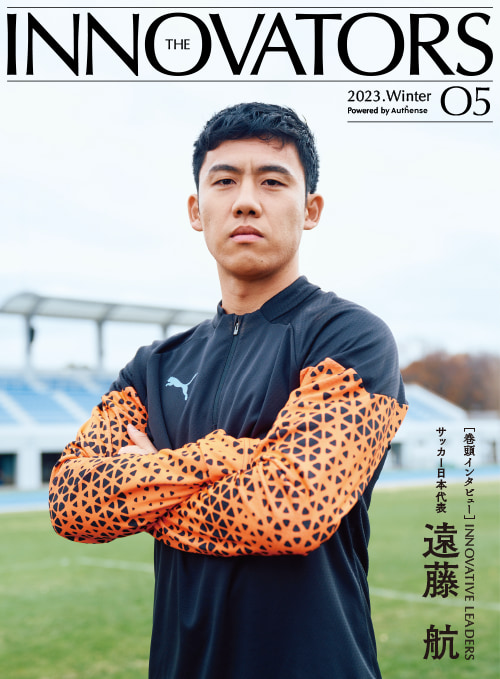会計不正はどの企業であっても起き得ることであり、決して他人事ではありません。
会計不正が明るみに出れば、企業の信頼が失墜したり株価低迷や上場廃止に至ったりするなど、多大な影響が生じ得ます。
では、会計不正はどのような原因で起きるのでしょうか?
また、自社で会計不正を起こさないためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、会計不正の概要や主な手口、自社で会計不正が起きないための対策などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当法律事務所「Authense法律事務所」は企業法務に特化した専門チームを設けており、会計不正を避けるための体制整備などのサポートが可能です。
会計不正を予防したい場合や自社で会計不正が起きてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
会計不正とは
会計不正(不正会計)とは、財務諸表について企業が意図的な改ざんを行い、実際の経営状況を歪曲する行為です。
貸借対照表や損益計算書などの財務諸表は、会社の業績や財務状況を示す重要な書類です。
そのため、投資家が投資を判断する際に参照するほか、金融機関が融資を判断する際や取引先が取引開始を検討する際などにも参照されます。
会計不正では、意図的な改ざんによって業績を実際よりもよく見せかける場合が多いでしょう。
法人税逃れなどの目的で実際よりも業績を悪く見せかける行為も会計不正の1つであるものの、これは「脱税」などと呼ばれることが多いといえます。
会計不正の主な手口や目的は後ほど解説しますが、たとえば横領を隠す目的で行われる場合や、業績不振を隠ぺいする目的で行われる場合などが見受けられます。
不適切会計との違い
会計不正と似た言葉に、「不適切会計」があります。
会計不正も不適切会計も誤った会計処理である点は共通している一方で、会計不正は意図的な不正のみを指すことが多いでしょう。
一方で、「不適切会計」という場合には意図的な改ざんのほか、ミスや誤った理解によるものなども含まれることが一般的です。
粉飾決算との違い
同じく会計不正と似た言葉に、「粉飾決算」があります。
会計不正と粉飾決算は、同じ意味で使われることが少なくありません。
ただし、粉飾決算は原則として実際よりも業績をよく見せかける不正だけを指すのに対し、会計不正は業績を実際よりよく見せる行為も悪く見せる行為も含みます。
また、粉飾決算は会計帳簿の偽装だけに焦点を当てている一方で、会計不正は「押し込み販売」などの不適切行為を含有する点でも異なっています。
不正会計の主な手口
会計不正の主な手口としては、どのようなものが挙げられるのでしょうか?
ここでは、会計不正の主な手口について解説します。
- 横領
- 循環取引
- 押し込み販売
- 棚卸資産の水増し
- 費用の資産計上
横領
会計不正の手口の代表格は、横領です。
手許現金を着服し、これを隠ぺいするために架空の経費を計上するなどの単純なケースのほか、経理担当者などが、自身が管理できる架空の企業に会社の資金を振り込むなど周到に計画されている場合もあります。
また、取引先の担当者などと共謀し、架空の売上をでっち上げたり実在する売上を水増しして請求したりして、その差額から個人的にキックバックを受ける手口なども存在します。
循環取引
循環取引とは、複数社で共謀して架空の取引を行い、各社が会計上のみで架空の売上を計上する行為です。
たとえば、実際には商品やサービスなどを提供していないにもかかわらず、会計上だけで「A社からB社」、「B社からC社」、「C社からA社」の架空の売上を計上する行為などがこれに該当します。
単純に架空の請求書を各社で発行するだけである場合のほか、循環取引の発覚を避けるために一部は実際に商品を出荷したり別の企業を仲介させたりするなど、複雑化させる場合もあります。
押し込み販売
押し込み販売とは、期末や締め日などの前に、自社製品を一方的に取引先(小売店)などに押し付け、販売したように見せかける行為です。
実際に販売したわけではないため、新年度になってから商品を回収することも多いでしょう。
押し込み販売の裏では、商品を押し付けられた取引先が販売に苦慮する事態が生じるほか、取引先の担当者に秘密裡に金銭が受け渡されている場合もあるなど、非常に問題のある行為といえます。
棚卸資産の水増し
棚卸資産の水増しとは、期末の棚卸資産を実際よりも多く計上することで、その期の利益を実際よりもよく見せかける行為です。
前提として、売上総利益は「売上-仕入高」で算定され、ここから経費を控除するなどしてその期の利益額が算定されます。
つまり、仕入高として計上すべき額が少なければ、それだけ利益額が多くなるということです。
そして、その期に計上する仕入高は、「期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高」で算定されます。
つまり、期末の棚卸高が多ければ、それだけその期に計上する仕入高が少なくなるということです。
そのため、期末の棚卸高を実際よりも多く計上するということは、その期の業績(利益)を実際よりもよく見せ換えることにつながります。
これも、会計不正でよくある手口の1つです。
費用の資産計上
費用の資産計上とは、本来はその期の経費として計上すべきものを、資産であると見せかける会計不正です。
原則として、資産は購入費用の全額がその期の費用となるのではなく、複数年に分けて少しずつ費用に計上します。
これを「減価償却」といいます。
本来であればその期に計上すべき経費を資産として不正に計上することで、その期に計上すべき費用が減ることとなり、その期の利益を実際よりも大きく見せかけることにつながります。
不正会計の主な原因
不正会計は、なぜ起きてしまうのでしょうか?
ここでは、不正会計が起きる主な原因を3つ紹介します。
経営不振
不正会計は、経営不振が原因で起きることが少なくありません。
経営不振が続くと株価が低迷し、経営陣が株主から責任を問われる可能性が高くなります。
また、金融機関からの融資も受けづらくなるでしょう。
そのため、経営陣が主導して会計不正に手を染めたり、経理担当者などが誤った「忖度」をして会計不正をしたりする可能性が生じます。
倫理観の低さ
会計不正が起きる原因として、倫理観の低さも挙げられます。
経営不振に陥っているからといって、すべての企業が会計不正に手を染めるわけではありません。
むしろ、多くの企業は業績不振から抜け出すため、正当な経営努力をするところでしょう。
そこで会計不正を選択するのは、企業としての倫理観が低いといわざるを得ません。
また、経理担当者などが横領など自身の利益を得るために会計不正に手を染める場合、これも倫理観の低さが原因であるといえるでしょう。
長年不正が見逃されてきた環境
会計不正が起きる背景には、長年不正が見逃されてきた環境があるケースも散見されます。
会計不正に一度手を染めると、辻褄を合わせるために不正を続ける必要が生じ、そこから抜け出すことは困難です。
会計不正を繰り返すうちに、より大きな不正や別の不正につながる可能性も高いでしょう。
また、はじめは少額の横領であってもこれが発覚しない場合、より手口が大胆なものとなるおそれもあります。
会計不正を避けるための主な対策
自社で会計不正が起きる事態を避けるため、企業としてはどのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、主な対策を4つ解説します。
- 不正が生じにくい体制を整備する
- 懲戒規定を整備する
- コンプライアンス研修を徹底する
- 内部監査体制を強化する
不正が生じにくい体制を整備する
1つ目は、不正が生じにくい体制を整備することです。
会計不正や横領などの不正は、不正がしやすい環境から生じることも少なくありません。
はじめは「出来心」から少額の横領を行い、これが発覚しなかったことで大きな金額の横領につながることもあるでしょう。
一般的には、経理担当者が1人で会社の資金移動などができる場合には、横領が起きやすい環境であるといえます。
振り込み作業にあたっては複数人による決済が必要であるとしたり、現金を触る際には複数人が立ち会うこととしたりするなどの体制を整備することで、会計不正が起きづらくなります。
懲戒規定を整備する
2つ目は、懲戒規定を整備することです。
会計不正が起きた際に懲戒処分をするためには、懲戒規定が整備されている必要があります。
懲戒規定を整備しておくことで会計不正が発覚した際に厳正な対処がしやすくなり、再発防止につながります。
コンプライアンス研修を徹底する
3つ目は、コンプライアンス研修を徹底することです。
会計不正は、コンプライアンス意識の欠如から起きることも少なくありません。
コンプライアンス研修を実施し、会計不正や横領をすべきでないとの会社の意思を明確にするとともに、会計不正に手を染めた場合に生じるリスクの内容などを伝えることで、会計不正の抑止力となるでしょう。
内部監査体制を強化する
4つ目は、内部監査体制を強化することです。
内部監査とは、企業内の独立した監査組織(監査役など)が企業の財務会計や業務について調査・評価したうえで、報告と助言を行うものです。
内部監査は従業員だけを対象とするものではなく、従業員のほか経営陣も監査の対象となります。
内部監査を強化することで、たとえ会計不正が生じても早期に発覚しやすくなるでしょう。
また、企業が内部監査を強化するとの姿勢を示すことで、会計不正や横領をした場合にも発覚する可能性が高いとのメッセージとなることから、不正の抑止力としての効果も期待できます。
会計不正対策について弁護士のサポートを受ける主なメリット
会計不正対策について弁護士に依頼した場合、どのようなサポートが期待できるのでしょうか?
ここでは、会計不正対策について弁護士に依頼する主なメリットを3つ解説します。
- 自社に合った適切な体制が講じやすくなる
- 最新の法令や事例を踏まえた研修が受けられる
- 会計不正が生じた際に的確な対応がしやすくなる
自社に合った適切な体制が講じやすくなる
弁護士にサポートを依頼することで、自社に合った適切な体制を整備しやすくなります。
会計不正を避けるために内部監査体制や内部統制システムを整備しようにも、具体的に何をすべきかわからないことも多いでしょう。
自社に合わない制度を無理に導入してしまうと、制度が形骸化したり対策が不十分となったりするおそれが生じます。
実績豊富な弁護士のサポートを受けることで、自社に合った体制が構築できます。
最新の法令や事例を踏まえた研修が受けられる
弁護士に依頼することで、最新の法令や事例を踏まえた研修を受けることが可能となります。
社内でコンプライアンス研修を実施する場合、社内の役職員が講師を務める方法もある一方で、外部の弁護士に講師を依頼する方法もあります。
弁護士に研修講師を依頼することで、最新事例を踏まえたより実践的な研修の実施が可能となるでしょう。
会計不正が生じた際に的確な対応がしやすくなる
日ごろから弁護士に相談しておくことで、万が一会計不正が生じた際にも適切な対応がしやすくなります。
会計不正が明るみに出た場合、株主や取引先、融資を受けている金融機関などあらゆるステークホルダーへの対応が必要となります。
また、場合によっては損害賠償請求が提起され、訴訟問題に発展する場合もあるでしょう。
さらに、行為者に対する懲戒処分も検討しなければなりません。
弁護士のサポートを受けることで、状況に応じた適切な対応についてアドバイスを受けられるほか、実際の対応の一部を代行してもらうことも可能となります。
会計不正の対策や対応はAuthense法律事務所へご相談ください
会計不正とは、不正な意図をもって財務諸表を改ざんする行為です。
これは、業績不振などが原因で会社への忖度から行われる場合もあれば、経理担当者などが自身の横領を隠す目的で行う場合もあるでしょう。
自社で会計不正を起こさないようにするには、不正が起きづらい環境を整備するとともに、コンプライアンス研修の徹底や内部監査の強化などが有効な対策といえます。
自社に合った対策を講じるため、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、会計不正が起きづらい体制整備などのサポートが可能です。
会計不正が起きないよう内部統制システムを構築したい際や、自社で会計不正が起きてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。