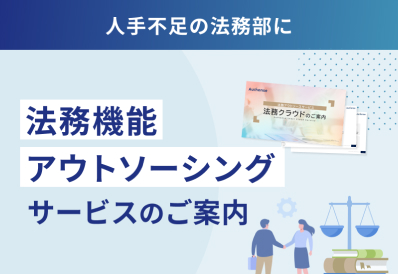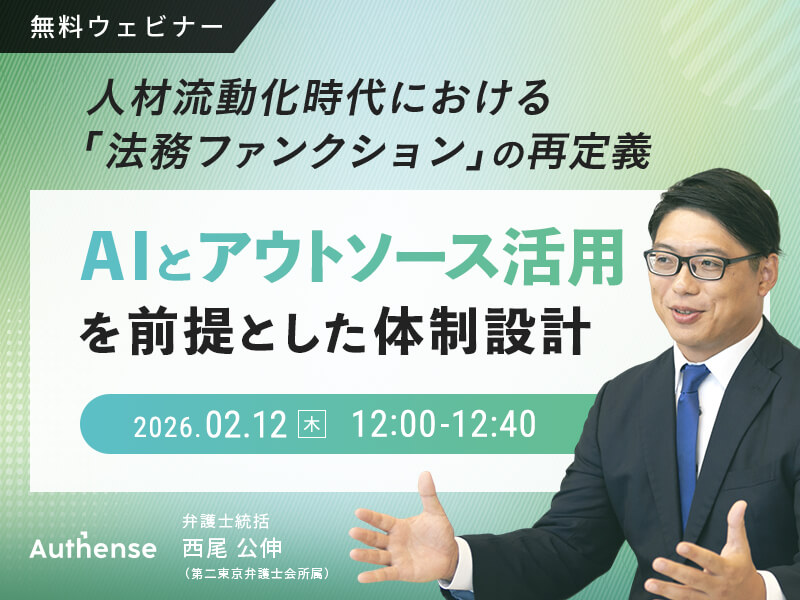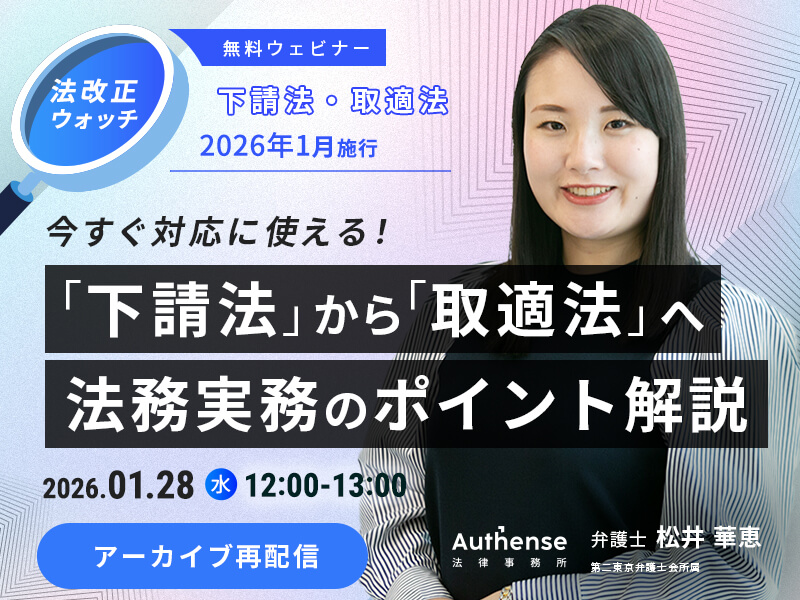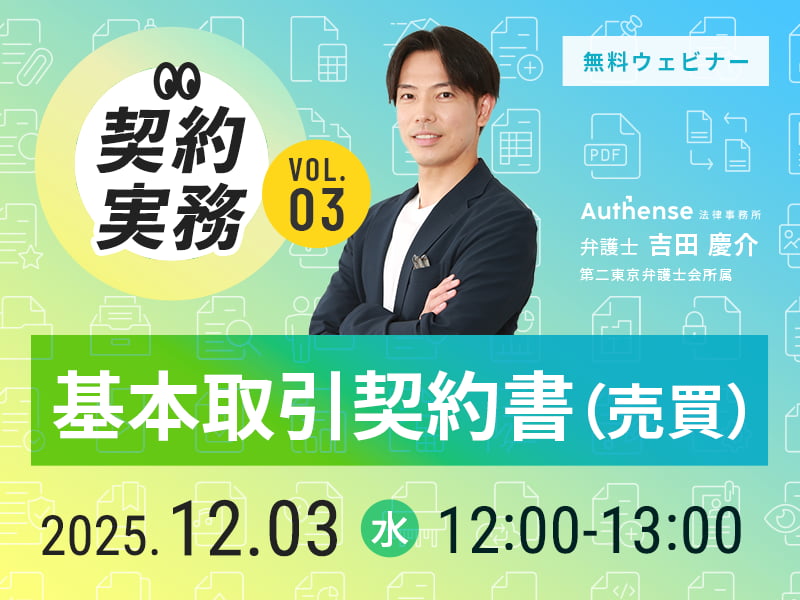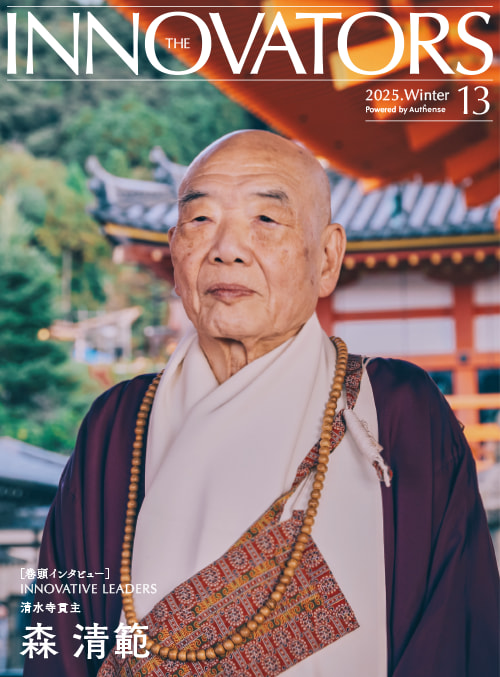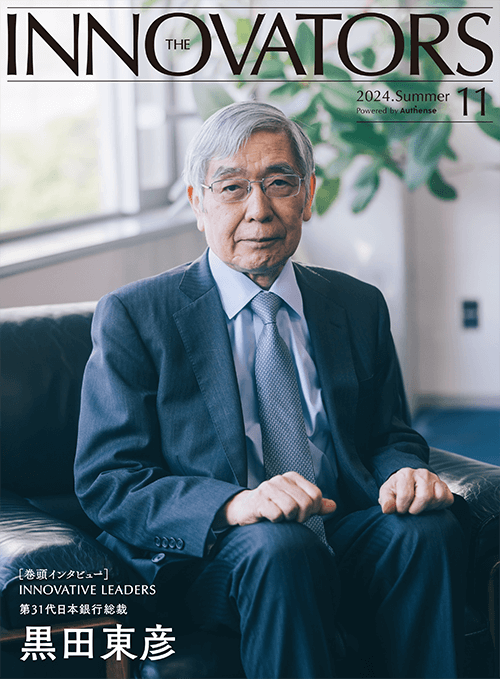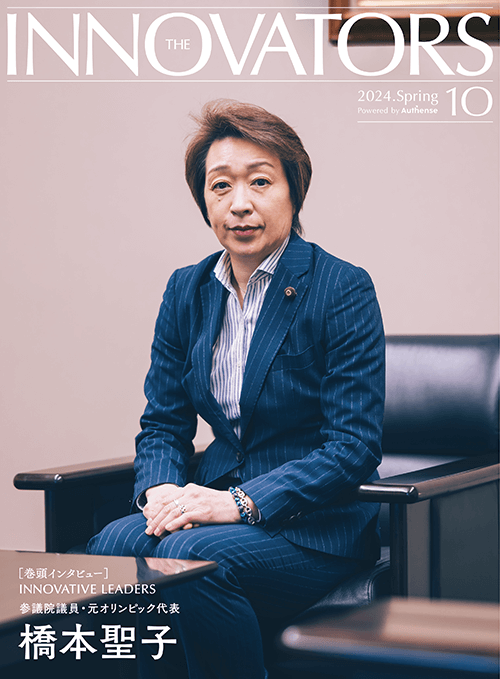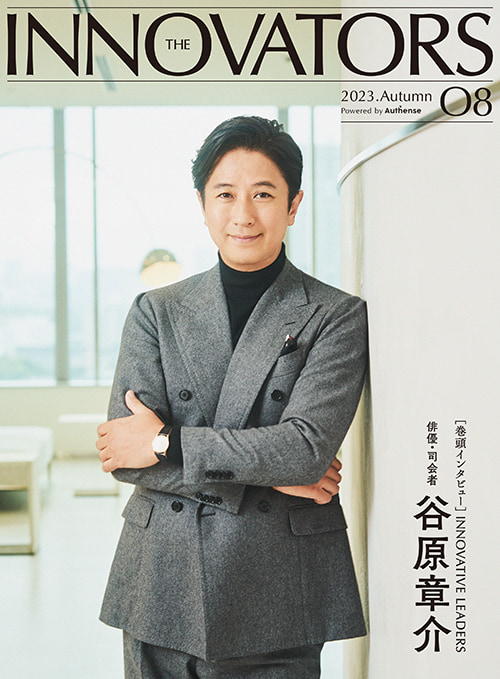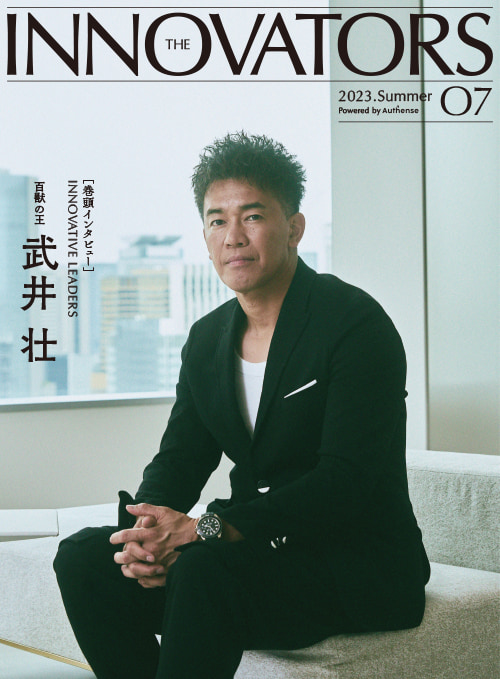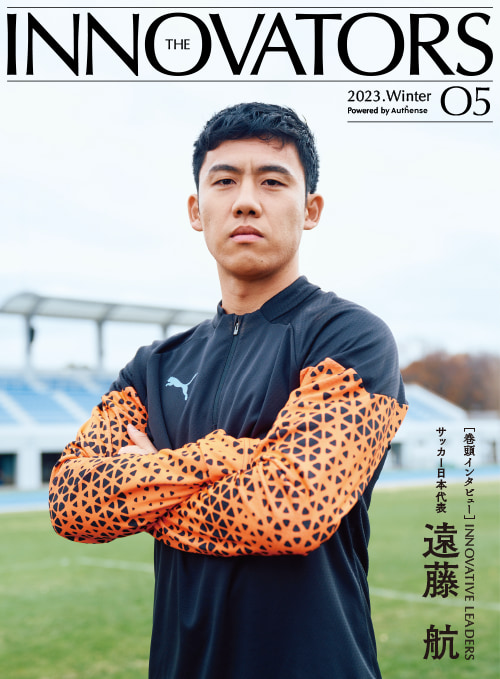医薬品などを取り扱う事業者様はもちろん、広告に携わる事業者様も、薬事不正をしないよう注意しなければなりません。
薬事不正は医薬品使用者の生命・身体に危険を及ぼす可能性が高く、社会的影響と企業継続性への重大な影響があります。
薬事不正が発生した場合には、規制当局対応、販売先・使用者への損害賠償請求対応、メディア対応、上場会社であれば株主や市場への対応が必要です。
では、薬事不正をした場合、具体的にどのような事態が生じ得るのでしょうか?
また、薬事不正の予防・対応に関して、弁護士はどのようなサポートが可能なのでしょうか?
今回は、薬事不正の概要や薬事不正によって生じ得るリスク、薬事不正を避ける対策などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当法律事務所「Authense法律事務所」は企業法務に特化した専門チームを設けており、薬事不正の予防や対応などについてのサポートも可能です。
自社で薬事不正が生じてお困りの際や、薬事不正を避けるための対策を講じたい場合などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
薬事不正とは
一般的に、薬事不正とは薬機法に違反する行為を指します。
薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、医薬品や医療機器などの品質や有効性、安全性を確保することを目的とした法律です。
以前は「薬事法」との名称であったところ、2014年の法改正により現在の名称へと改訂されました。
薬事不正の代表例
薬事不正の代表例としては、どのようなものが挙げられるのでしょうか?
ここでは、薬事不正の主な例を3つ紹介します。
- 承認された工程と異なる製造
- 未承認医薬品の広告
- 虚偽・誇大広告
承認された工程と異なる製造
1つ目は、承認された工程と異なる製造です。
医薬品などは人の身体に直接影響を及ぼすものであり、その影響も甚大なものとなりかねません。
そのため、製造許可を受けるにあたっては、製品の生産方法や管理体制が審査対象とされており、実際に製造をする際はその工程を厳格に守る必要があります。
過去には、この製造工程が遵守されなかった結果、本来であれば混入しないはずの別の成分が混入し、健康被害が出た事例もありました。
また、健康被害には至らなかったものの承認外の手順で製造していたことが明らかとなり、自主回収に至ったり業務停止処分の対象となったりした例もあります。
未承認医薬品の広告
2つ目は、未承認医薬品の広告です。
薬機法には広告規制が設けられており、この規制の対象は「何人も」とされていることに注意しなければなりません。
つまり、医薬品の製造や販売をしている事業者のみならず、化粧品などのPRを委託された企業やインフルエンサー、アフェリエイターなども規制の対象になるということです。
未承認医薬品の広告とは、厚生労働省の承認を受けていない医薬品や医療機器、再生医療などの製品を広告することです(薬機法68条)。
たとえば、医薬品としての承認を受けていない健康食品についてあたかも医薬品の効用を有するような広告をしたり、国内で承認されていない海外の医薬品を広告したりする行為などがこれに該当します。
いわゆる正式な広告に限らず、SNS上での発信などでも対象となり得ることに注意が必要です。
虚偽・誇大広告
3つ目は、虚偽や誇大な広告です。
これは、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果、性能に関して、明示的・暗示的を問わず虚偽や誇大な広告を禁じる規定です(同66条)。
この規制に違反した事例は非常に多く、たとえば化粧品として表示できる効果効能の範囲を超えた広告をしたり、承認された効能を逸脱した効能を広告したりするものがこれに該当します。
この点も、医薬品等を製造販売する事業者のみならず、広告に携わる事業者やインフルエンサーなども十分に理解しておかなければなりません。
薬事不正によって生じ得る主なリスク
薬事不正が起きると、企業にとってどのようなリスクが生じるのでしょうか?
ここでは、薬事不正によって生じ得る事態について解説します。
- 損害賠償請求の対象となる
- 製品の回収が必要になる
- 課徴金納付命令の対象となる
- 行政処分の対象となる
- 罰則が適用される
- 企業の信頼が失墜する
損害賠償請求の対象となる
薬事不正によって消費者の生命や身体に影響が生じた場合、損害賠償請求の対象となります。
被害が甚大であれば、損害賠償額も非常に高額となるでしょう。
製品の回収が必要になる
たとえ生命や身体には影響が生じなかったとしても、承認されたものとは異なる工程で製造された場合などには、製品の回収が必要となります。
流通している数が多ければ、回収も多大なコストを要することとなるでしょう。
課徴金納付命令の対象となる
薬機法の広告規制に違反した場合には、課徴金納付命令の対象となります。
課徴金とは、行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益です。
誇大広告などは薬機法で禁止されているものの、誇大広告によって得られる収益が多額である場合には、罰則の適用だけでは違反の抑止力とならないおそれが生じます。
そこで、金銭的不利益を課す課徴金制度を導入することで、違反の抑止力となる効果が期待されています。
薬機法に違反した場合に課され得る課徴金の額は、課徴金納付対象となる違反行為によって得た対価の4.5%です(同75条の5の2 1項)。
この割合は、利益額などではなく売上額に乗じることに注意しなければなりません。
たとえば、違反行為によって10億円の売上を得た場合、これによって得た利益額にかかわらず、課徴金の額は4,500万円(=10億円×4.5%)になるということです。
なお、算定した課徴金の額が225万円未満の場合には、納付を命じられないとされています(同4項)。
行政処分の対象となる
薬事不正をした場合、課徴金納付命令以外にも行政処分の対象となり得ます。
たとえば、違反を是正すべき旨の命令がなされる可能性があるほか、違反事例の公表や業務停止命令、許可・登録の取消しなどの処分がなされる可能性があります。
業務停止命令や許可・登録の取り消しがなされると事業に重大な影響が生じ、その後の事業継続が困難なものとなりかねません。
罰則が適用される
薬事不正をした場合、罰則が適用される可能性があります。
薬事不正によって課される刑事罰は違反の内容によって異なるものの、たとえば無許可営業や医薬品等の未承認販売などの罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科です(同84条)。
また、広告規制に違反した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはこれらの併科に処されます(同85条)。
さらに、法人の業務として薬事不正が行われた場合、法人も罰金刑の対象となります(同90条)。
企業の信頼が失墜する
薬事不正をした場合、企業の信頼が失墜する可能性があります。
医薬品などは人の人体に重大な影響を及ぼし得るものであり、そのような重要なものを信頼できない企業から購入したくないと考えるのは自然なことでしょう。
そのため、薬事不正が明るみに出ると消費者や取引先が離反するおそれが生じます。
また、上場企業であれば株価が低迷し、取締役などの経営陣が株主から責任を問われる事態ともなりかなません。
このように、薬事不正が発生すると企業に甚大な影響が生じます。
薬事不正を防ぐ主な対策
自社で薬事不正が起きる事態を避けるため、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、主な対策を5つ解説します。
- 薬機法とガイドラインをよく理解する
- コンプライアンス研修を実施する
- 弁護士に相談できる体制を整備する
- 社内規定や業務フローを整備する
- 小さな不正も見逃さない
薬機法とガイドラインをよく理解する
1つ目は、薬機法とガイドラインを読み込み、理解することです。
薬事不正を避けるためには、薬機法やガイドラインの正しい理解は不可欠です。
少なくとも経営陣と法務担当者は薬機法とガイドラインを読み込み、十分に理解しておく必要があるでしょう。
コンプライアンス研修を実施する
2つ目は、コンプライアンス研修を定期的に実施することです。
たとえ経営陣が薬事不正を避けるべきと考えていても、現場の従業員の法令遵守の意識が低くコンプライアンスが徹底されていなければ、薬事不正が起きるおそれが高くなります。
たとえば、安全のために必要な工程を組んで医薬品などの製造承認を受けているにもかかわらず、現場にそのような意識がなく現状の製造工程の効率が悪いと判断すれば、無断で製造工程を変更してしまうかもしれません。
また、より収益を上げるため、薬機法違反にあたる表現で広告を出してしまうかもしれません。
コンプライアンス研修を実施し、どのような行為が薬事不正に当たるのか、また薬事不正をするとどのような事態が生じ得るかなどを社内に浸透させることで、薬事不正が生じる事態を避けやすくなります。
弁護士に相談できる体制を整備する
3つ目は、弁護士に相談できる体制を整備することです。
実際に業務を行う中で、薬事不正であるか否か判断に迷うこともあるでしょう。
薬機法に強い弁護士と顧問契約を締結するなどすぐに相談できる体制を整備することで、判断ミスなどから薬事不正に手を染める事態を避けやすくなります。
社内規定や業務フローを整備する
4つ目は、社内規定や業務フローを整備することです。
薬機法の規制対象である医薬品の製造や販売などでは、一般的な製造業のように自由な製造工程の変更などができません。
社内規定や業務フローを整備して、変更をしようとする際の承認申請などの流れを整備することで、知らずに不正が生じる事態を避けやすくなります。
小さな不正も見逃さない
5つ目は、小さな不正も見逃さないことです。
薬事不正に限らず、社内で起きる不正は、小さな不正から始まることが少なくありません。
これが見逃されることで、不正の規模が徐々に大きくなったり、不正が長年の「慣習」化したりすることとなります。
そのような事態を避けるため、たとえ小さな不正であっても、見つけた際は厳正に対処すべきでしょう。
薬事不正に関する弁護士の主なサポート内容
薬事不正に関して、弁護士はどのようなサポートができるのでしょうか?
最後に、弁護士による主なサポート内容を紹介します。
-
- 広告審査代行・レビュー
- 相談対応
- 自社に合った内部統制システムの構築支援
- 研修講師
- 不正発覚時の対応支援
なお、実際のサポート内容は弁護士によって異なる可能性があるため、依頼する前に具体的なサポート内容を弁護士とすり合わせるとよいでしょう。
広告審査代行・レビュー
弁護士は、広告審査の代行や広告のレビューでお役に立てます。
あらかじめ弁護士のチェックを受けることで、薬機法に違反した広告を出稿する事態を避けることが可能となります。
また、どのような表現を避けるべきであるのか、自社の実際の広告案についてフィードバックが受けられるため、社内での知見も蓄積するでしょう。
相談対応
弁護士は、薬機法にまつわるご相談に対応できます。
自社の検討している行為が薬機法違反にあたるか否か、判断に迷うこともあるでしょう。
その際にすぐに弁護士へ相談することで、経営判断に活かせるほか、知らずに薬事不正に手を染める事態を避けやすくなります。
自社に合った内部統制システムの構築支援
弁護士は、自社に合った内部統制システムの構築を支援します。
内部統制システムとは、企業が健全かつ効率的な経営を行うための社内のルールや仕組みです。
たとえば、業務フローや承認フローの整備や業務執行の報告体制の整備などがこれに該当します。
薬事不正を避けるには、不正が起きづらい体制の整備が不可欠でしょう。
弁護士のサポートを受けることで、自社の業務内容や規模、上場の有無などを踏まえた適切な内部統制システムの整備が実現できます。
研修講師
弁護士へは、研修講師も依頼できます。
たとえば、経営陣を対象とした薬機法やガイドラインを理解するための研修のほか、従業員を対象としたコンプライアンス研修などの講師を依頼できるでしょう。
不正発覚時の対応支援
弁護士は、不正発覚時の対応でもお役に立てます。
自社で薬事不正が起きた場合、どのように対応すればよいか右往左往してしまうことも多いでしょう。
しかし、初期の対応を誤れば問題がさらに大きなものとなりかねません。
弁護士のサポートを受けることで、状況に応じた的確な対応を実現でき、問題の早期終結や再発防止などにつながります。
薬事不正を防ぐ対策や対応はAuthense法律事務所へご相談ください
薬事不正とは、薬機法に違反する行為を意味します。
薬事不正が起きてしまうと、損害賠償請求がなされたり罰則が適用されたりするなど、多大な影響が生じかねません。
企業の信頼が失墜すれば、再起をはかるハードルも高くなるでしょう。
そのような事態を避けるため、企業は薬事不正を起こさない対策を講じるべきです。
たとえば、コンプライアンス研修の徹底や業務フローの整備、内部統制システムの構築などがこれに該当します。
自社に合った対策を講じるため、まずは弁護士へご相談ください。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、薬事不正を避ける体制整備のサポートも可能です。
自社で薬事不正が起きてお困りの際や、薬事不正が起きないための体制整備をご検討の際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。