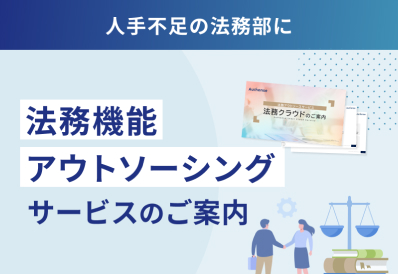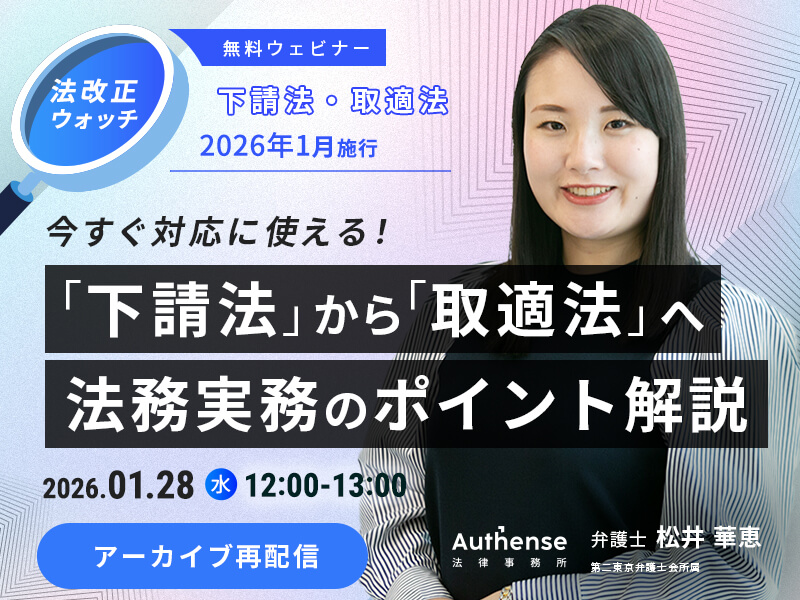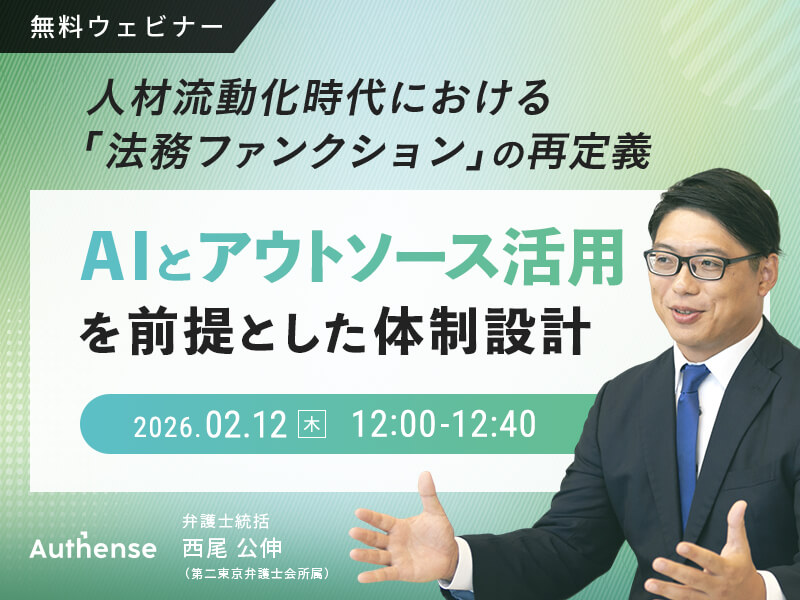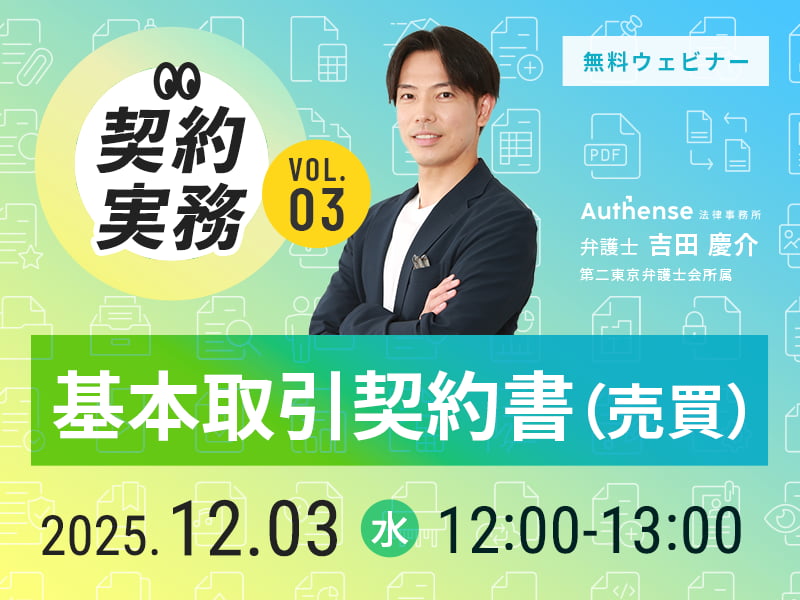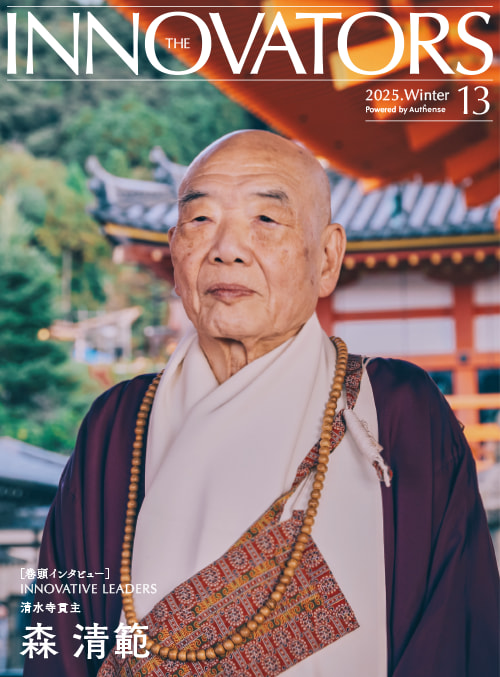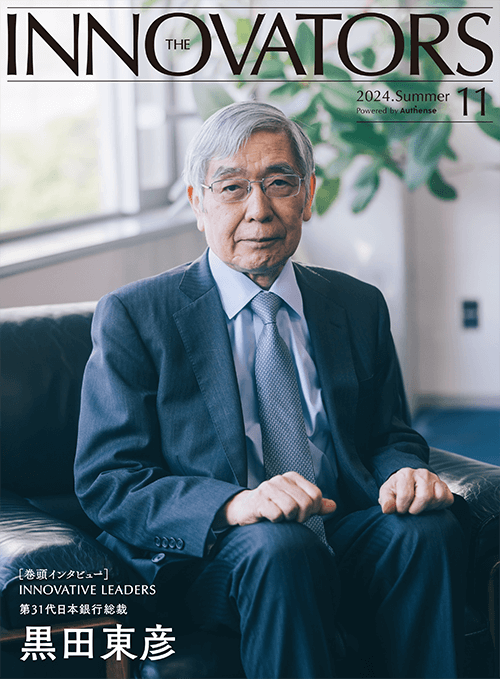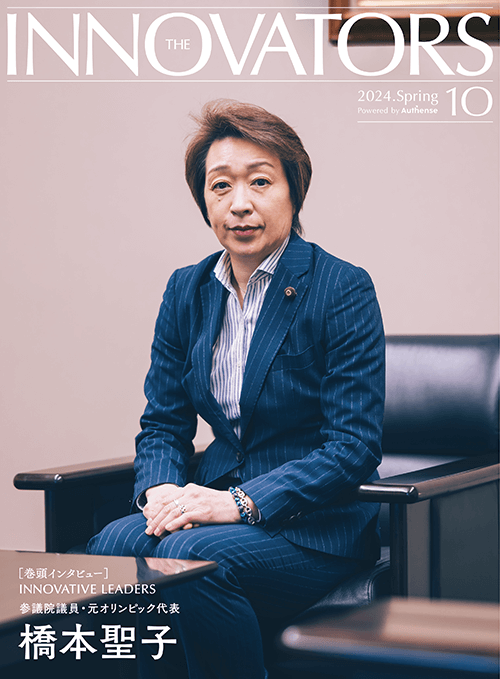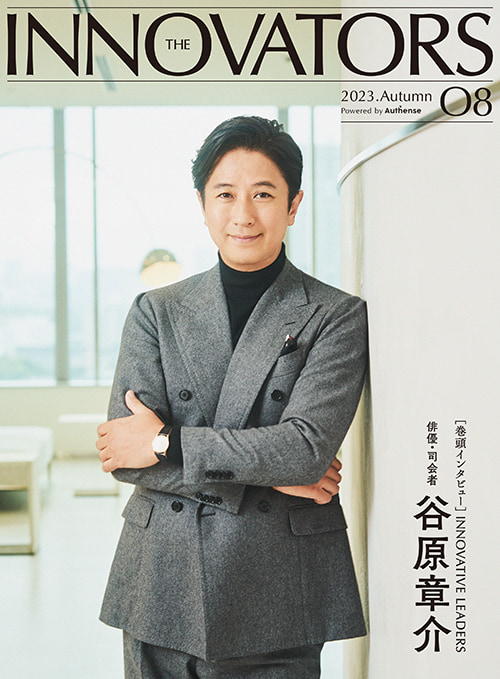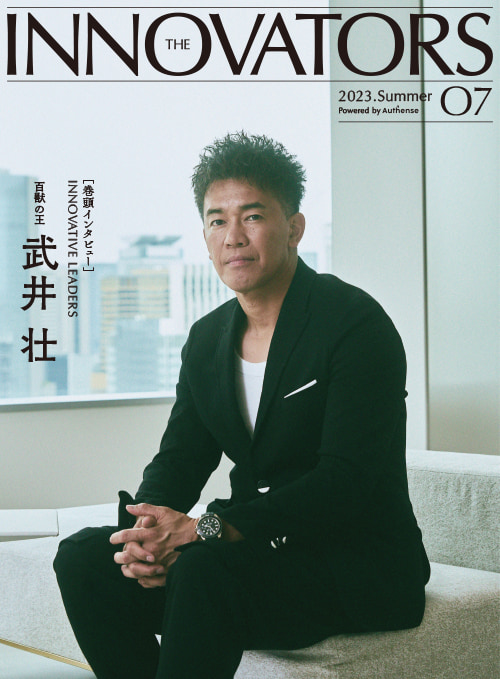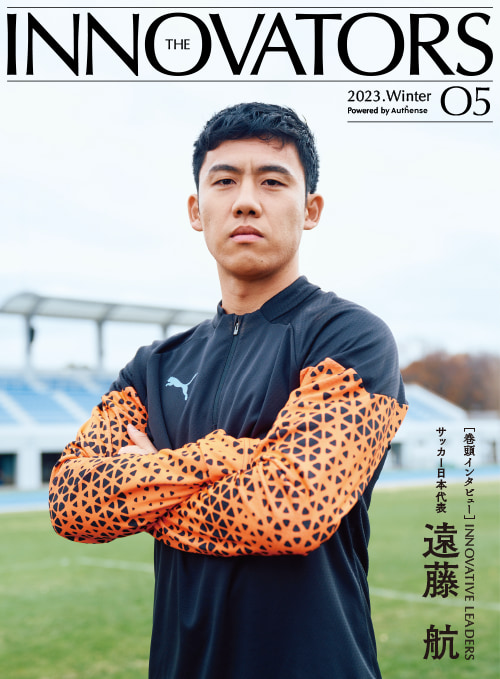社内で横領事件が起きると、企業としてさまざまな対応が必要となります。
では、社内で横領事件が起きたら、どのように対応すればよいのでしょうか?
また、横領事件を防ぐため、企業はどのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、横領事件の概要や起きてしまった場合の対応、発生させないための対策などについて、弁護士がくわしく解説します。
なお、当法律事務所「Authense法律事務所」は企業法務に特化したチームを設けており、横領事件が生じた場合の対応や横領事件を起こさないための対策などのサポートが可能です。
横領事件について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
目次

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
横領事件とは
横領事件とは、自身が占有する他人の物を不法に領得する事件を指します。
たとえば、友人から預かっていたお金を無断で使う行為や、道で拾った財布を警察に届けず自分のものにする行為などがこれに該当します。
このうち、前者は原則として「単純横領罪(刑法252条)」に、後者は「遺失物横領罪(同254条)」に該当します。
一方で、企業で発生する横領事件は、業務上横領罪の構成要件を満たす可能性が高いでしょう(同253条)。
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する罪です。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役であり、単純横領罪や遺失物横領罪よりも厳しく設定されています。
従業員が横領に手を染める主なパターン
業務上の横領は、どのようなケースで生じやすいのでしょうか?
ここでは、社内で横領が生じる主なパターンを紹介します。
なお、ここで紹介するのは一例であり、必ずしもこのようなパターンから横領が生じるとは限りません。
集金担当者による横領
1つ目は、集金担当者による横領です。
顧客などからの集金業務を任されている従業員が、顧客から手渡された金銭を会社に納めず、無断で自分のものとする場合がこれに該当します。
顧客からの代金は未収であると報告する場合もある一方で、無断で商品などを持ち出して取引を行い、その顧客の存在自体を会社に報告しない場合もあります。
また、金融機関の従業員が顧客のもとへ出向いて預金のための金銭を預かり、これを実際には預金せず着服するケースもあります。
ただし、金融機関が預金のために現金を運ぶ機会自体が減っているため、このような横領は減っているものと思われます。
経理担当者による横領
2つ目は、経理担当者による横領です。
経理担当者は会社の預金や現金を取り扱う機会が多いため、横領も起こりやすいといえます。
たとえば、立替金などを現金で精算する際に、請求額を水増しして差額分を着服する行為のほか、架空の請求書を発行して自身が管理する口座に金銭を振り込ませる行為などがあります。
購買担当者による横領
3つ目は、購買担当者による横領です。
このケースでは、架空の仕入れをでっち上げ、その代金を着服する手口が多いといえます。
また、取引先の担当者と共謀して実際よりも高い金額で請求書を発行させ、その差額を無断でリベートとして分け合うケースもあります。
店長クラスの従業員による横領
4つ目は、店長クラスの従業員による横領です。
店長クラスの従業員による横領では、飲食店や小売店など現金決済が多い業種において売上の記録を改ざんし、現金を着服するケースなどがあります。
また、切手などを着服し、これを現金化して横領するケースもあります。
取締役による横領
5つ目は、取締役など経営陣による横領です。
このケースは被害額がもっとも大きくなりやすく、企業に重大な影響を与える可能性が高いでしょう。
取締役による横領では、自身が別の会社を設立し、その会社にまとまった金額を送金させるなどして横領する手口などがあります。
社内で横領事件が発生した際の対応
社内で横領事件が発生した場合、企業としてはどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、横領事件が発覚した場合の対応について解説します。
- 弁護士への相談
- 証拠の確保・保全
- 事情調査
- 横領事件を起こした従業員の解雇など
- 返済方法の協議・訴訟の提起
- 刑事告訴の検討
- 必要に応じて社内外への説明
- 再発防止策の検討
弁護士への相談
社内で横領事件が発生した場合、的確な証拠保全や調査、懲戒処分などが必要となります。
また、訴訟を提起したり刑事告訴をしたりする必要が生じる場合もあるでしょう。
これらの対応を適切に行うため、まずは弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、実際に発生した横領事件について自社が具体的に行うべき対応が明確となります。
証拠の確保・保全
社内で横領事件が発生したら、まずは証拠の確保と保全に努めます。
横領されている可能性が高く、実行者についてもある程度推測できていても、証拠がなければ本人に否定された場合に、それ以上の追及が困難となるためです。
また、この段階では可能な限り会社が横領事件の調査をしていることを本人に知られないよう注意すべきです。
調査をしていることを知られると、証拠を隠ぺいされる可能性があるためです。
核心に近づいていくと本人に知られる可能性が高くなるため、本人に気づかれづらい証拠から徐々に集めていくことがポイントです。
横領事件の証拠となり得るのは、入出金記録や監視カメラの映像、顧客など第三者による証言などです。
ただし、実際に必要となる証拠は横領の手口などによって大きく異なるため、弁護士へ相談したうえでそのケースにおいて必要な証拠を集めましょう。
事情調査
横領事件の証拠がある程度集まった段階で、横領事件を起こした本人に事情調査を行います。
この段階では、本人に横領事件を起こしたことを認めさせ、横領事件を起こした旨と返済する旨を承諾する書面を差し入れさせることが目的です。
本人が横領を認めない場合には、解決までに時間を要する可能性が高くなります。
そのため、事情調査は弁護士に同席してもらうか、弁護士に代理してもらうとよいでしょう。
横領事件を起こした従業員の処分など
横領事件を起こした本人に対しては、何らかの処分が必要となるでしょう。
具体的な処分の内容は、弁護士へ相談する等したうえで適切な方法を選択する必要があります。
返済方法の協議・訴訟の提起
続いて、横領された金銭の返還について本人と協議します。
金額が大きい場合には一括返済は難しいと主張される可能性が高いものの、企業としては可能な限り一括返済をするように検討すべきでしょう。
分割返済とすると、返済を受けるまでに時間がかかるうえ、返済が滞った際に再度訴訟などの対応が必要となり企業にとっての負担が大きいためです。
一括返済の方法としては、親族からの借り入れによる方法や自宅など資産の売却による方法、生命保険の解約による方法などが検討できます。
また、雇用に際して身元保証人をつけている場合には、その身元保証人への請求の可否も検討します。
全額の一括返済が難しい場合には、一部を分割返済とする場合もあるものの、この場合には必ず公正証書としたうえで、強制執行認諾文言を付けておくべきです。
強制執行認諾文言付きの公正証書としておくことで、万が一返済が滞った場合に強制執行がスムーズとなるほか、滞納の抑止力ともなります。
一方で、本人が返済に応じない場合には、訴訟を提起します。
刑事告訴の検討
冒頭で解説したように、職場での横領は刑法上の業務上横領罪に該当する可能性が高いでしょう。
企業としてより厳正に対応したいと考える場合には、刑事告訴を行います。
横領罪は親告罪(被害者側からの告訴がなければ起訴できない罪)ではないものの、実際には被害者からの告訴や被害届により操作が開始されることが通常です。
必要に応じて社内外への説明
社内で横領事件が起きた場合、必要に応じて社内外に説明をします。
説明の要否や説明すべき内容は、弁護士へ相談したうえで検討するとよいでしょう。
説明にあたっては、横領事件を起こした犯人の名誉毀損にあたらないよう注意が必要です。
再発防止策の検討
今後同様の事件が起きないよう、再発防止策を検討します。
弁護士のサポートを受けて再発防止策を検討することで、より自社に合った対策を講じやすくなります。
横領事件を防ぐための主な対策
自社で横領事件が起きる事態を避けるため、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、主な対策を3つ解説します。
- 金銭を取り扱う業務の属人化やブラックボックス化を避ける
- コンプライアンス研修を実施する
- 横領事件が発覚した際は厳正に対処する
金銭を取り扱う業務の属人化やブラックボックス化を避ける
1つ目は、横領事件が起こりづらい環境を整備することです。
横領事件は、「横領しやすい環境」や「横領をしても発覚しづらい環境」が原因で起きることが少なくありません。
そこで、出金時にダブルチェックを必須とするなど金銭を取り扱う業務の属人化を避けることや、金銭を取り扱う業務のブラックボックス化を避けることなどが有効な対策となります。
コンプライアンス研修を実施する
2つ目は、コンプライアンス研修を実施することです。
「横領をしてはならない」ということは一般常識として理解していても、「横領をしたら具体的にどうなるのか」までは理解できていない場合もあります。
コンプライアンス研修を実施することで、横領に手を染める事態を抑止しやすくなります。
横領事件が発覚した際は厳正に対処する
3つ目は、横領事件が発生したら厳正に対処することです。
横領事件が発生した際に、少額であることなどを理由に見逃してしまうと、横領の手口や金額がエスカレートするおそれがあります。
また、会社が横領を見逃すことは、「少額の着服程度であれば問題にならない」という誤ったメッセージを社内に伝えることにもなりかねません。
このような事態を避けるため、社内で横領事件が発生した際は、たとえ少額であっても厳しく対処するべきでしょう。
横領事件で弁護士のサポートを受ける主なメリット
横領事件に関して弁護士にサポートを受けることにはさまざまなメリットがあります。
ここでは、主なメリットを4つ解説します。
- 的確な証拠保全・調査が可能となる
- 横領事件を起こした従業員の処遇について的確な対応が可能となる
- 事案に応じて返済を受ける方法や刑事告訴などを検討できる
- 横領事件を防ぐための体制整備などのサポートが受けられる
的確な証拠保全・調査が可能となる
先ほど解説したように、横領事件に対して厳正に対処するには、証拠の保全や調査が必須といえます。
弁護士のサポートを受けることで、本人に知られず的確な調査や証拠保全を行いやすくなります。
横領事件を起こした従業員の処遇について的確な対応が可能となる
懲戒処分を検討する際は、本人がした行為の内容と処分の内容のバランスを慎重に検討しなければなりません。
弁護士のサポートを受けることで、そのケースにおける適切な対応が可能となります。
事案に応じて返済を受ける方法や刑事告訴などを検討できる
横領事件が起きた際は、返済を受ける方法などを協議することなるものの、企業としてどのような形で返済を求めるか判断に迷うことも多いでしょう。
同様に、刑事告訴をするか否かについても迷うことが多いと思います。
弁護士のサポートを受けることで、状況に応じた的確な対応を検討できます。
横領事件を防ぐための体制整備などのサポートが受けられる
弁護士は、横領事件を防ぐための体制整備などのサポートも可能です。
横領事件を避けるには、「横領しづらい環境」づくりや「横領が起きても早期に発覚しやすい環境」づくりをすることがポイントです。
とはいえ、具体的に何を行えばよいか判断に迷うことも多いでしょう。
弁護士は、企業の規模や業種、成長ステージに合った体制づくりのサポートも可能です。
横領事件に強い弁護士をお探しの際はAuthense法律事務所へご相談ください
横領事件の概要を紹介するとともに、横領事件が起きた場合の初期対応や横領事件を防ぐ対策などを解説しました。
横領事件を防ぐには、横領が起きやすい業務の属人化やブラックボックス化を避けることが有効です。
また、横領事件が起きた際は、厳しく対処するべきでしょう。
厳しい対処をすることで、再発防止につながります。
横領事件が起きてお困りの際は、早期に弁護士へご相談ください。
弁護士へ相談することで、証拠収集や事情聴取、返済交渉などを含め、適切な対応についてアドバイスやサポートを受けることが可能となります。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、横領事件についても多くの対応実績があります。
横領事件に強い弁護士をお探しの際はAuthense法律事務所へご相談ください。