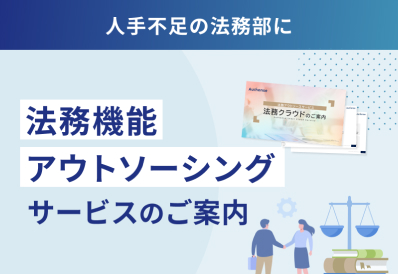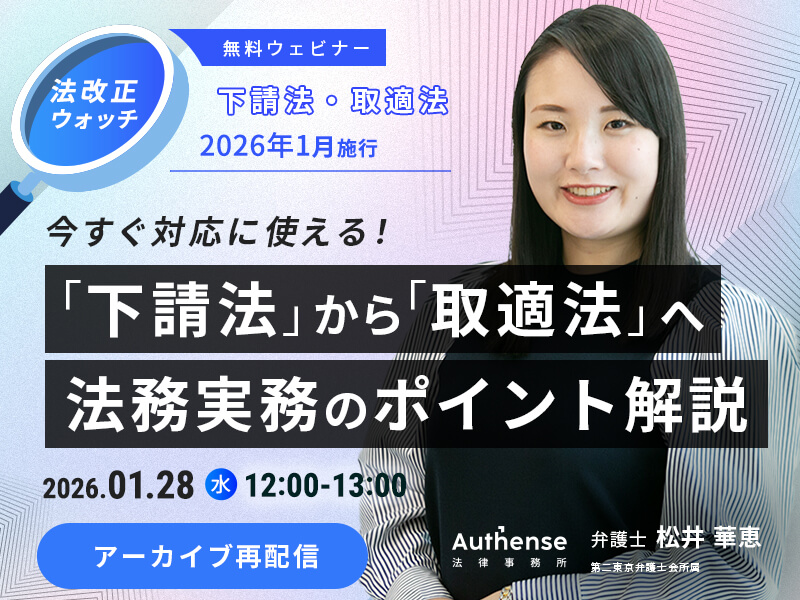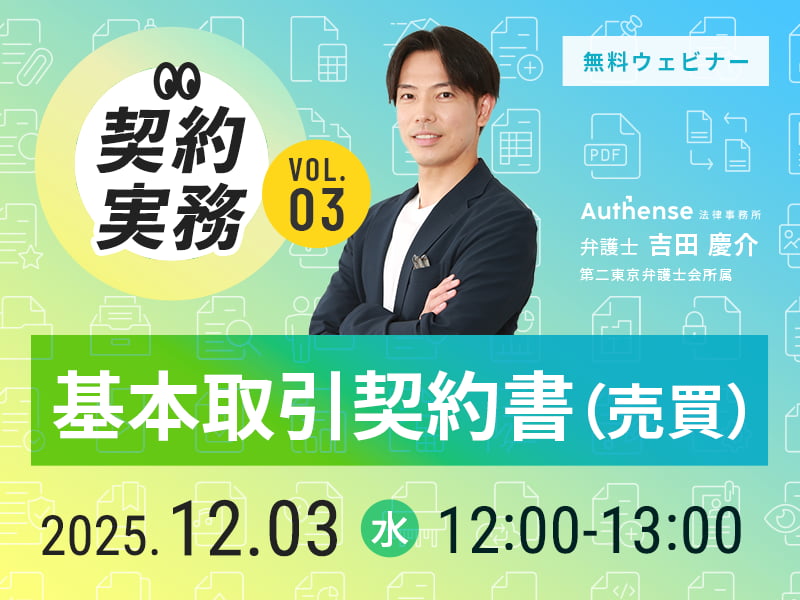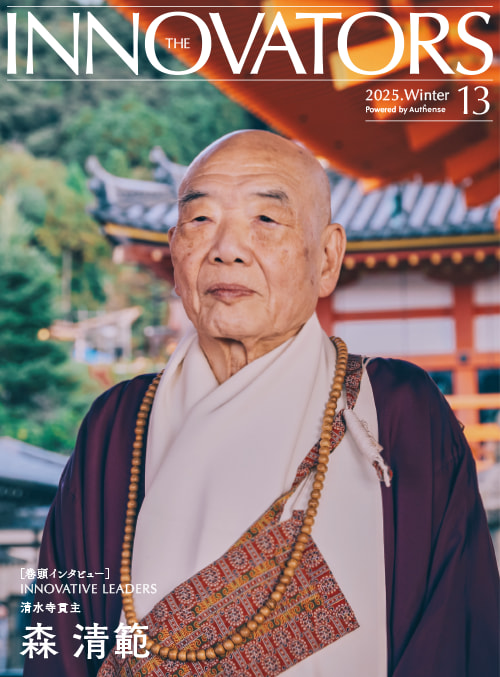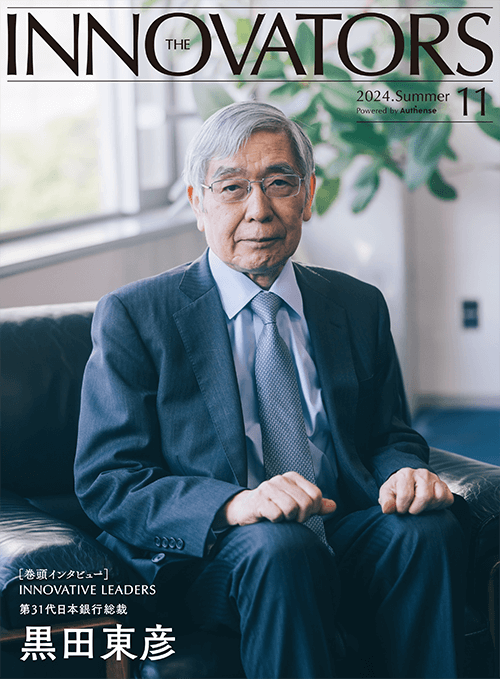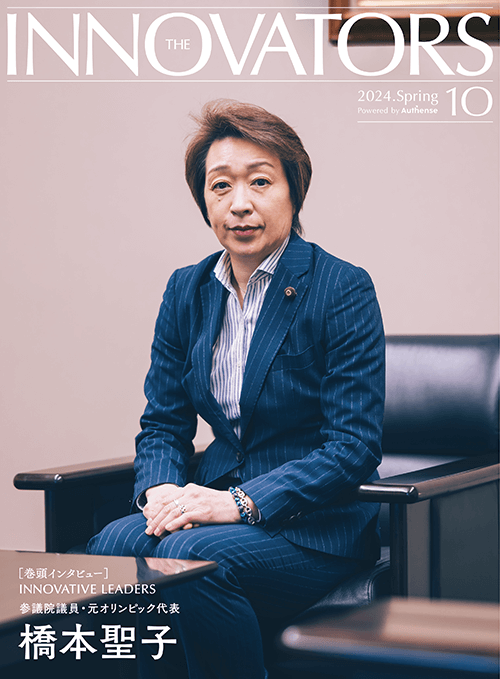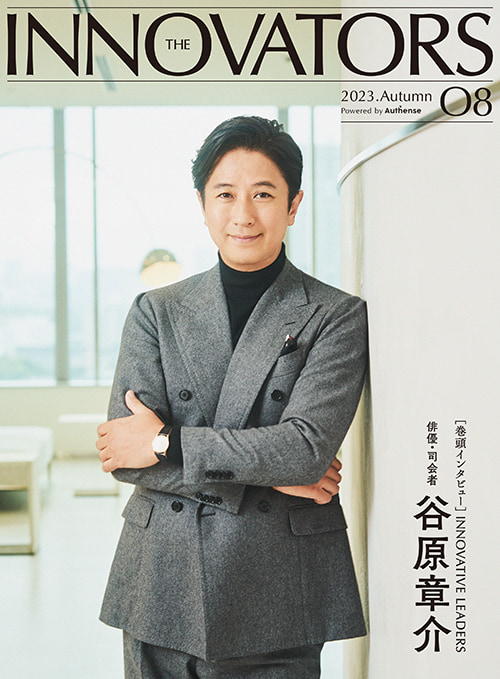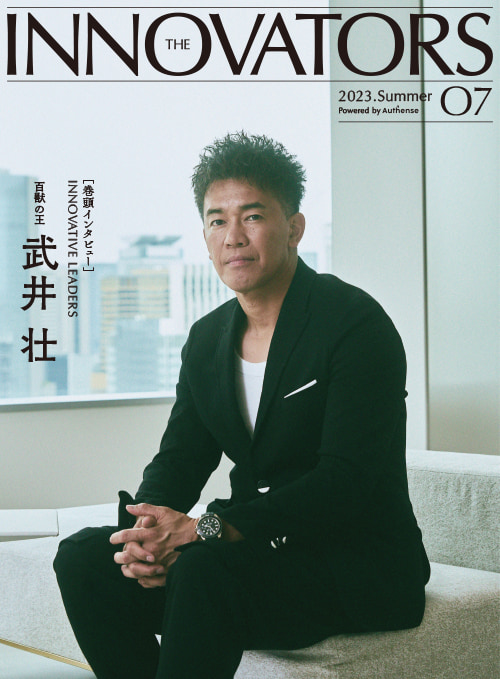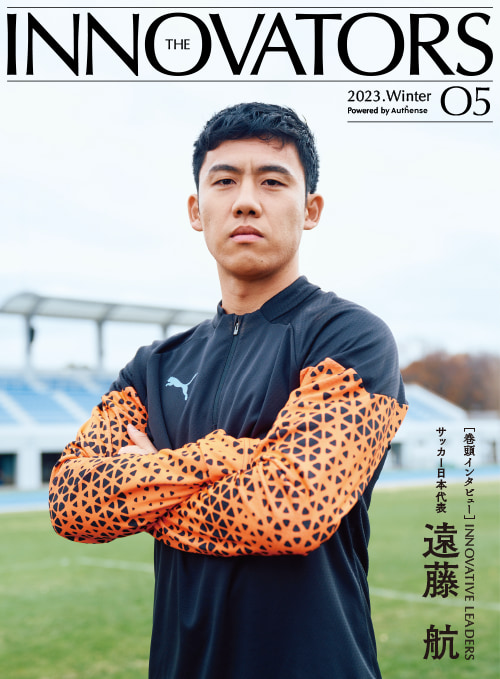自社でインサイダー取引が起きると、企業としてさまざまな対応が必要となります。
では、自社でインサイダー取引が起きた場合、どのような事態が生じるのでしょうか?
また、自社でインサイダー取引が起きないためには、企業としてどのような対策を講じればよいのでしょうか?
今回は、インサイダー取引の概要やインサイダー取引が起きた場合に企業に求められる主な対応、インサイダー取引を防止するための主な対策などについて弁護士が解説します。
なお、当事務所「Authense法律事務所」は企業法務に特化した専門チームを設けており、インサイダー取引への対応や対策についても豊富な実績を有しています。
インサイダー取引について相談できる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
目次

<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
インサイダー取引とは
インサイダー取引とは、企業の内部情報に接する立場にある経営陣や従業員、取引先などが、その立場を利用して会社の経営や財務などに関する重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にその会社の株式などの取引を行うことです。
たとえば、A社の役員Xや経理担当者Yであれば、A社の業績が上方修正されるなどの情報に公開前に接する機会があるでしょう。
この情報に接した役員Xや経理担当者Yが、上方修正されるという情報が世間に公表される前にA社の株を購入し、情報が公開された後に売却すれば、容易に利益を得ることが可能となります。
同様に、XやYが自ら取引をするのではなく、家族に情報を伝えて株取引をさせたり、知人に対して情報を売ったりすることでも利益を上げることができてしまいます。
このような行為が横行すると、一般の投資家は安心して株取引をすることができません。
そこで、ここで紹介した役員Xの行為などが、インサイダー取引として規制対象とされています。
自社でインサイダー取引が起きた場合に生じ得る事態
自社でインサイダー取引が発生した場合、どのような事態が生じるのでしょうか?
ここでは、インサイダー取引が自社に与える主な影響について解説します。
- 関係者が刑事罰を受ける
- 課徴金納付命令の対象となる
- 企業の信頼が失墜する
- 株主やメディアなどへの対応が必要となる
関係者が刑事罰を受ける
自社に関してインサイダー取引が発生した場合、インサイダー取引を行った者に刑事罰が課されます。
インサイダー取引の刑事罰は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科です(金融商品取引法197条の2 13号、14号、15号)。
また、インサイダー取引を実際に行った者に対してインサイダー情報を伝達した者も、同様の罪に問われます。
さらに、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業員が、会社や個人の業務や財産に関してインサイダー取引がなされた場合、会社にも「5億円以下の罰金」が科されます(同207条1項2号)。
会社の知り得ないところで従業員がインサイダー取引を行った場合、原則として会社自身が刑事罰に問われるものではありません。
とはいえ、役員や従業員に対して刑事罰が下ることは、会社にとっても少なからぬ影響が生じるでしょう。
また、警察や検察などの捜査に会社として対応すべき場面も生じることが多く、対応に人員を割く必要が生じます。
課徴金納付命令の対象となる
インサイダー取引は、課徴金納付命令の対象となります(同175条、175条の2)。
課徴金とは、違反行為を行った者に行政機関が課す金銭的な負担であり、インサイダー取引など違反行為によって行為者が得られる金銭的利益が多額となりやすい違反について、違反の抑止力となる効果が期待されて設けられています。
インサイダー取引規制の適用を受ける会社関係者などには、法人も含まれるため、その法人の役員等が当該法人の計算でインサイダー取引を行ったときは、課徴金納付命令の対象となります。
企業の信頼が失墜する
インサイダー事件は、企業の情報管理の甘さを露呈することにつながります。
そのため、企業は「被害者」である一方で「情報管理が甘い」との認識がもたれ、顧客や取引先などからの信頼が失墜する可能性があります。
株主やメディアなどへの対応が必要となる
インサイダー取引が発生した場合、株主やメディアへの対応が必要となります。
企業としては原因究明に努め、説明責任を果たす必要が生じるでしょう。
自社でインサイダー取引が起きた場合の対応
社内でインサイダー取引が発生した場合、企業としてはどのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、インサイダー取引が発生した際の基本的な対応方法について解説します。
- 弁護士へ相談する
- 内部調査をして事実関係を確認する
- 取引所や金融庁などへ必要な報告をする
- 株主など社外へ向けた説明をする
弁護士へ相談する
社内でインサイダー取引が発生してしまったら、まずは弁護士へご相談ください。
顧問弁護士がいる場合には顧問弁護士がベストである一方で、顧問弁護士がいない場合や顧問弁護士では対応が難しい場合などには、別の弁護士へ相談しても構いません。
弁護士へ相談することで、そのケースにおける具体的な対応の検討が可能となります。
内部調査をして事実関係を確認する
内部調査を行い、インサイダー取引の事実関係の把握に努めます。
事実関係の確認を自社だけで行うことは容易ではないため、弁護士のサポートを受けつつ調査を進めるとよいでしょう。
取引所や金融庁などへ必要な報告をする
調査の結果、インサイダー取引が実際に発生したことが判明したら、上場先の証券取引所や金融庁などへ必要な報告を行います。
報告を怠ると会社にも罰則が適用される可能性があるため、早期の報告に努めるようにしてください。
株主など社外へ向けた説明をする
インサイダー取引は、株主にとって重大な影響を与え得るものです。
そのため、ある程度情報が把握できた段階で、株主や社外の関係者に説明すべきであるといえます。
なお、会社が何も把握できていない段階で説明会を開いても説明できる内容がなく、むしろ対応を疑問視されるおそれが生じます。
一方で、すべての情報を把握するまで説明をしなければ、説明の遅さに不信感を抱かれかねません。
そのため、ホームページ上での情報公開などと併用し、弁護士へ相談したうえで適切な時期での説明を検討するとよいでしょう。
自社でインサイダー取引を生じさせないために講じたい対策
自社でインサイダー取引を生じさせないようにするには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、主な対策を4つ解説します。
- 情報管理を徹底する
- 就業規則を整備する
- 適時開示を積極的に実施する
- コンプライアンス研修を実施する
情報管理を徹底する
1つ目は、情報管理を徹底することです。
企業の株価に影響を与えるような重大な情報に多くの従業員が触れられる状態では、インサイダー取引が起きるリスクが高くなります。
インサイダー取引が起きる事態を避けるため、未公表の会社情報が他に漏れたり不正に利用されたりすることのないよう、社内体制を整備することが重要です。
インサイダー情報に触れる人が少なければ、それだけインサイダー取引が発生するリスクを減らすことが可能となります。
また、不審な取引が発生した際には、その情報に触れられる限られた人が疑われかねないことから、インサイダー取引の抑止力ともなるでしょう。
就業規則を整備する
2つ目は、就業規則を整備することです。
インサイダー取引の懸念がある上場企業においては、就業規則により、該当する有価証券の取引を制限する旨の規定を盛り込むとよいでしょう。
ただし、インサイダー取引には関係のない株式の取引までを制限することは行き過ぎた規制となりかねないため、バランスへの配慮が必要です。
就業規則を適切に整備するため、あらかじめ弁護士へ相談するとよいでしょう。
併せて、インサイダー取引を行った場合における懲戒規定も整備します。
従業員の懲戒は就業規則などの規程に従って行う必要があり、懲戒規定が存在しないとインサイダー取引を行った従業員への懲戒処分(解雇や減給など)が困難となります。
このような視点から、就業規則を見直しておくことをおすすめします。
適時開示を積極的に実施する
3つ目は、適時開示を積極的に実施することです。
適時開示とは、株価に影響を与える可能性がある経営上の重要な情報を、上場企業自らが速やかに公表する制度です。
株価に影響を与える情報を公開前に利用して取引をするとインサイダー取引となる一方で、適時開示によって一般の投資家にも広く知られることとなっていれば、原則としてインサイダー取引とはなりません。
そのため、企業が積極的に適時開示を行い、一般の投資家に早期に情報を提供していくことで、インサイダー取引を防ぐことが可能となります。
コンプライアンス研修を実施する
4つ目は、コンプライアンス研修を実施することです。
上場企業の経営陣がインサイダー取引に常に注意を払っている可能性が高い一方で、一般の従業員はインサイダー取引をさほど意識していないことも少なくありません。
そのため、たとえば経営陣から不意にコピーを依頼された従業員が、その用紙に記載されているインサイダー情報を目にし、罪の意識などのないままに自身で取引を行ったり家族や友人に情報を伝えたりするおそれもあるでしょう。
このような事態を避けるため、定期的にコンプライアンス研修を実施し、すべての従業員がインサイダー取引について正しく理解するよう努めることが重要です。
インサイダー取引に関して弁護士ができる主なサポート
インサイダー取引に関して弁護士ができるサポートには、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、主なサポート内容を紹介します。
なお、具体的なサポート内容は事務所によって異なるため、ご希望のサポートがある際は、あらかじめ依頼を検討している事務所が対応しているか否か確認するようにしてください。
- 情報管理体制や就業規則の整備支援
- コンプライアンス研修の実施
- インサイダー取引発生時の内部調査支援
- インサイダー取引発生時における対応の支援
Authense法律事務所はインサイダー取引が生じた際の対応や、インサイダー取引が起きないための体制整備のサポートに力を入れています。
インサイダー取引に関してお困りの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
情報管理体制や就業規則の整備支援
弁護士は、情報管理体制の整備や、就業規則の整備などのサポートが可能です。
弁護士の支援を受けることで、自社に合った的確かつ実効性の高い情報管理体制や就業規則の整備が実現できます。
コンプライアンス研修の実施
弁護士は、コンプライアンス研修を実施できます。
インサイダー取引を防止するためのコンプライアンス研修は自社で実施する方法もある一方で、弁護士に講師を依頼して行うことも可能です。
弁護士にコンプライアンス研修の講師を依頼することで、他社で起きた実際のインサイダー取引の事例などを踏まえ、最新の法令に即した的確な研修を受けることが可能となるでしょう。
インサイダー取引発生時の内部調査支援
弁護士には、インサイダー取引が発生した際の内部調査の支援を依頼できます。
自社でインサイダー取引が発生した場合、その後の対応を的確なものとするには、早急に事実関係を調査する必要が生じます。
調査に遅れが生じたり調査方法に問題があったりすると、証拠が隠ぺいされるなどして事実関係が闇に葬られてしまうかもしれません。
インサイダー取引が発生した際に弁護士へ相談することで、状況に応じたスピーディーかつ的確な内部調査を実現できます。
インサイダー取引発生時における対応の支援
弁護士には、インサイダー取引が発生した際の対応についてサポートを依頼できます。
先ほど解説したように、社内でインサイダー取引が発生するとさまざまな対応が必要となります。
代表的なものには、証券取引所や金融庁への報告や、インサイダー取引に関わった従業員の懲戒処分の検討、株主・メディア対応などがあります。
弁護士へ依頼する場合は、これらの対応についてアドバイスや支援などが受けられるため、企業としての対応を誤りづらくなります。
インサイダー取引に強い弁護士をお探しの際はAuthense法律事務所へご相談ください
インサイダー取引が発生すると関与した人について刑事罰の対象となるほか、企業としてもさまざまな対応に追われる事態が生じます。
特に、インサイダー取引は株主に重大な影響を与えるため、株主に対する真摯な対応が必要となるでしょう。
社内でインサイダー取引を発生させないようにするには、情報管理の徹底や積極的な適時開示、コンプライアンス研修の実施などの対策が検討できます。
自社に合った適切な対策を講じたい際は、弁護士にサポートを受けるようにしてください。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、インサイダー取引発生時の対応やインサイダー取引を予防するための社内体制の構築支援などを得意としています。
社内でインサイダー取引が発生してお困りの際や、インサイダー取引が起きづらい体制を整備したい際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。