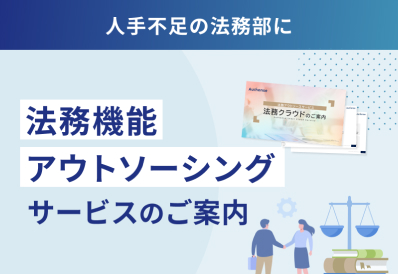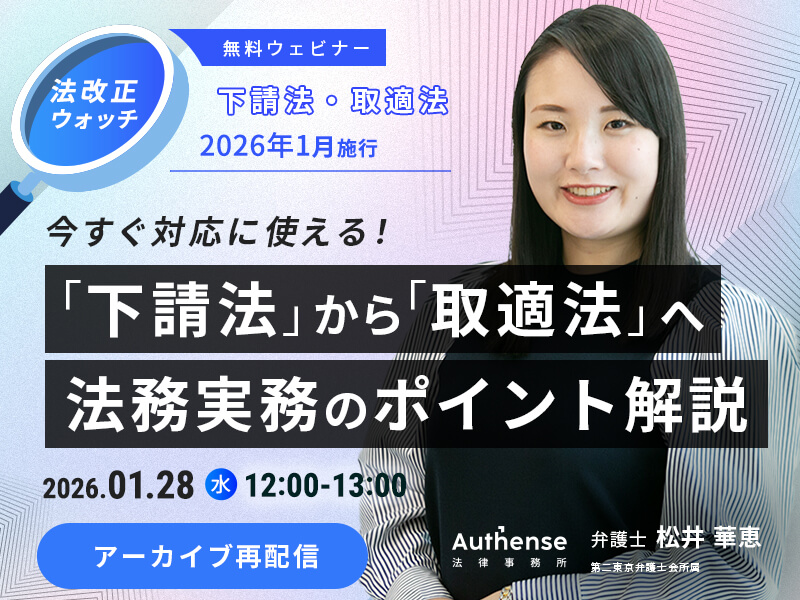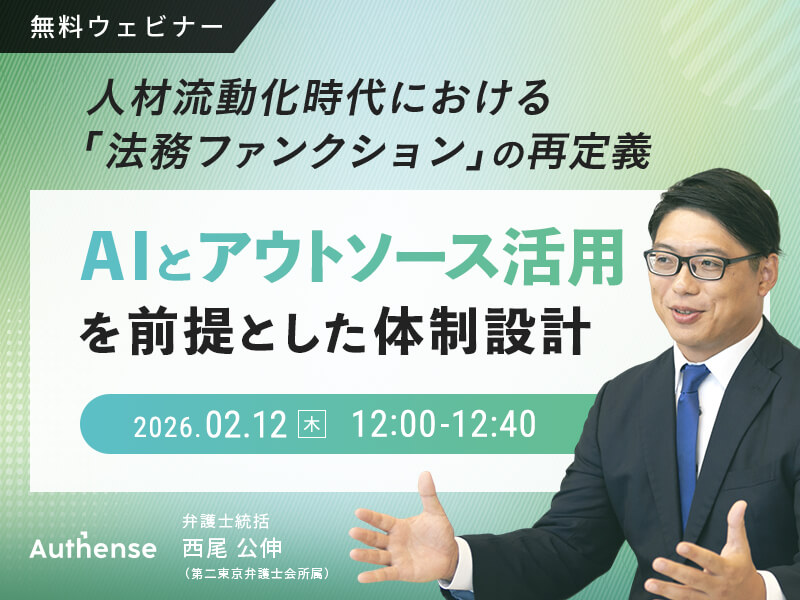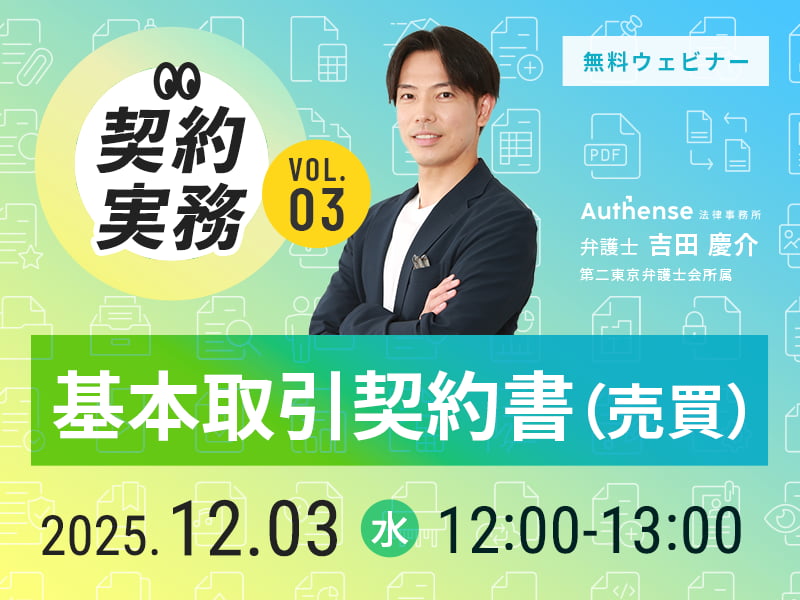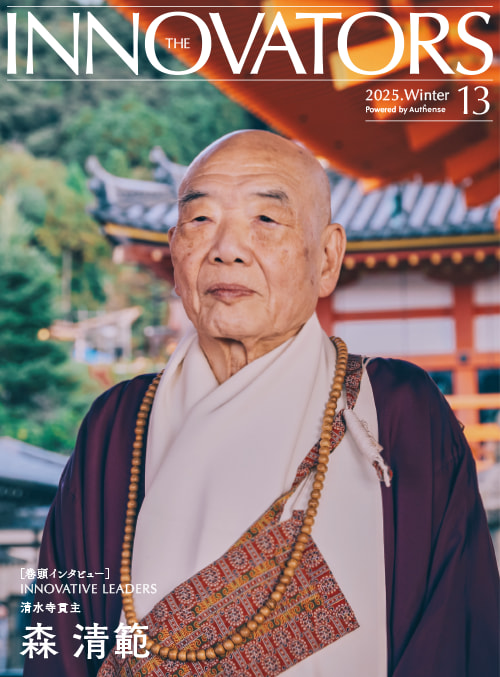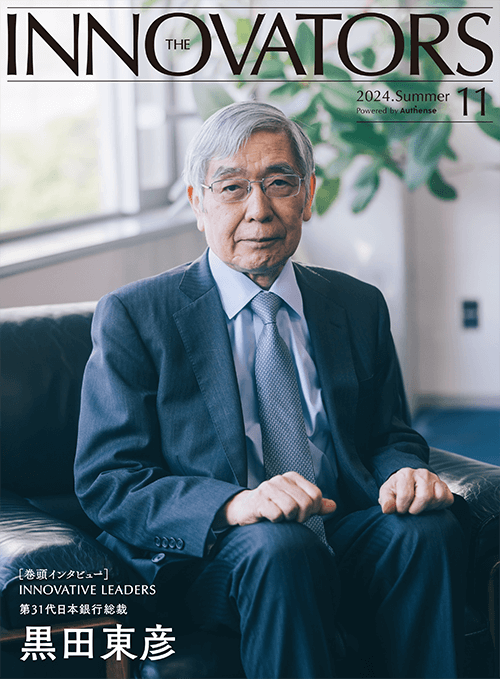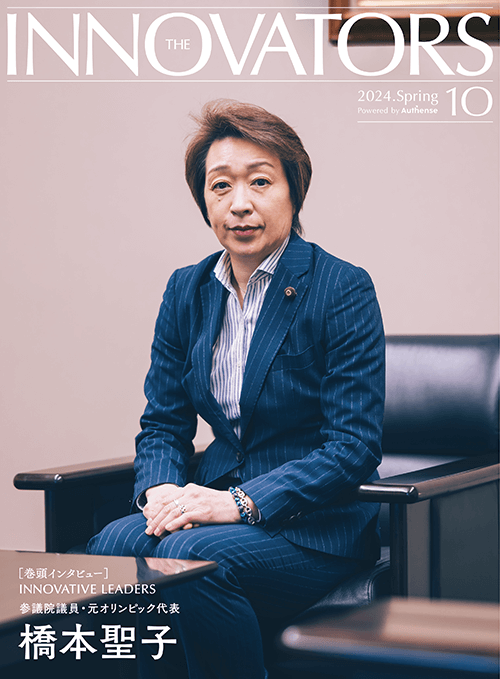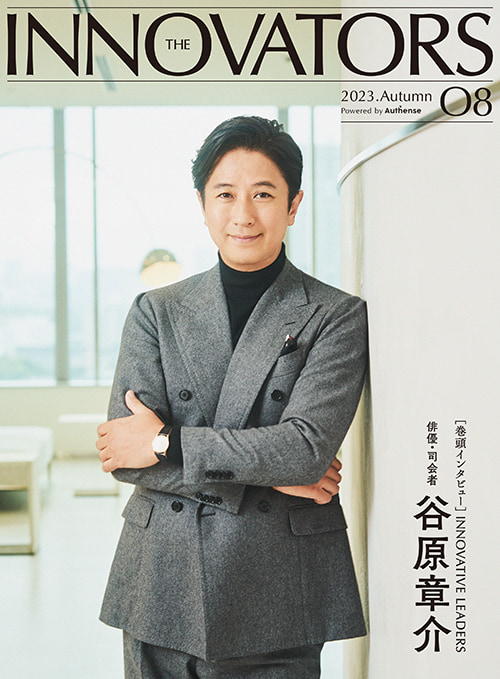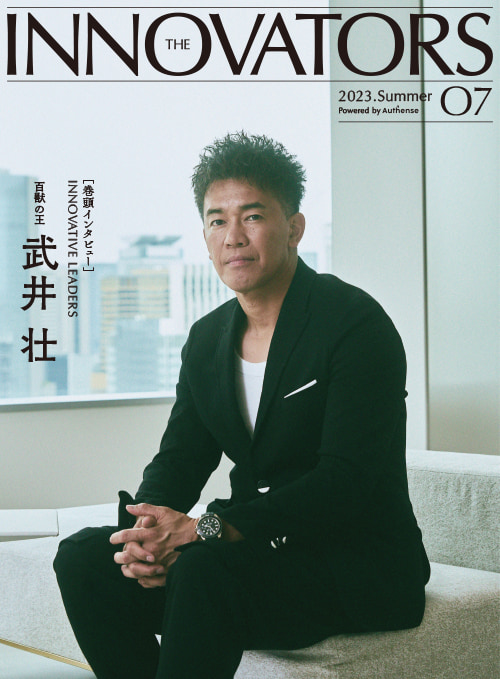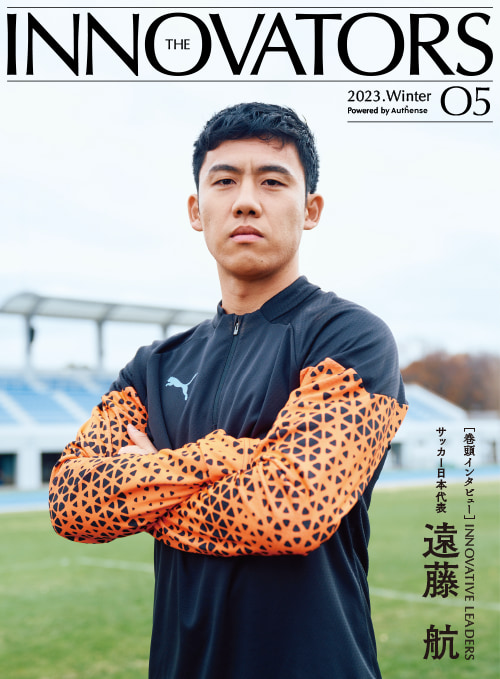企業の持続的な活動において、コーポレートガバナンスの強化やコンプライアンス経営の推進、CSR、SDGsへの取り組みなどの重要性が年々増しています。
特に危機や有事には、リスク把握と企業価値の回復に高度な戦略が求められるでしょう。
では企業に生じ得る主な「危機」には、どのようなものがあるのでしょうか。
また、危機管理対応に関して、弁護士はどのようなサポートができるのでしょうか?
ここでは、危機管理対応の概要や企業に生じ得る主な「危機」を紹介するとともに、危機管理対応を弁護士に依頼するメリットや弁護士による主なサポート内容などについて解説します。
なお、Authense法律事務所は危機管理対応に力を入れており、メディア対応の経験が豊富な弁護士が、危機管理広報のコンサルタントなどの専門家と協力しながら支援します。
危機管理対応を任せられる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
危機管理対応とは
危機管理対応とは、企業について一定の危機が生じた場合に行う対応の全般です。
企業では、重大な危機が生じないよう、日ごろから対策を講じるべきです。
しかし、事業を運営する中で危機の発生をゼロとすることは困難であり、万が一危機が生じた際の対応についても検討しておくべきでしょう。
危機が生じた際に早期に的確な対応をとることで、事業に及ぼす影響を最小限に抑えやすくなります。
企業に生じる主な「危機」とは
企業に生じる主な「危機」には、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、企業に生じ得る主な危機を紹介します。
- 会計不正
- インサイダー取引
- 従業員不正
- 品質不正・データ偽装
- 製品事故
- 特別背任
- 個人情報漏洩
- サイバーインシデント
- ハラスメント
- 反社会的勢力との関与
- 不適切広報によるSNSなどでの「炎上」
会計不正
会計不正とは、企業の財務情報を意図的に改ざんする行為です。
経理担当者などが自身の横領を隠ぺいする目的で行う場合があるほか、業績不振を隠す目的で企業ぐるみで行われる場合や、誤った忖度によって行われる場合などもあります。
インサイダー取引
インサイダー取引とは、企業の内部情報に触れる立場にある役員や従業員が、未公表の重要事実をもとに株式を売買するものです。
また、自身が直接売買するのではなく、親族などに売買をさせたり、知人などの情報を伝える見返りに対価を得たりする場合もあります。
従業員不正
従業員不正とは、従業員によって意図的になされる不祥事です。
たとえば、従業員による横領や詐欺、意図的な情報漏洩などがこれに該当します。
品質不正・データ偽装
品質不正とは、実際には所定の品質を満たしていないにもかかわらず、あたかも基準を満たしているように装って製品を販売したり、国や行政庁に届け出たりすることです。
品質不正には、検査結果を意図的に改ざんするデータ偽装を伴う場合もあります。
製品事故
製品事故とは、製品の欠陥を原因として、消費者などの生命や身体に対する危害が発生した事故を指します。
製品に起因して生じた事故である限り、「包丁という製品を使用して、人を刺した」のように明らかに製品の欠陥が原因ではない場合を除き、製品事故に該当する可能性があります。
特別背任
特別背任とは、取締役や監査役、執行役などが、自己または第三者の利益を図ることを目的として任務に背く行為をし、会社に財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪です。
これらの者は社内で大きな権限を有していることが多く、従業員による横領などと比較して損害額も多額となりやすいでしょう。
個人情報漏洩
個人情報漏洩とは、個人情報が意図せず外部に流出したり、第三者に不正に取得されたりすることです。
パソコンの置き忘れなど従業員のミスによる場合もある一方で、サイバー攻撃によって起きる場合もあります。
サイバーインシデント
サイバーインシデントとは、情報セキュリティ上の脅威となり得る事象です。
たとえば、マルウェアへの感染やシステム障害、情報漏えいなどがこれに該当し、不正アクセスや標的型攻撃などによって生じます。
ハラスメント
ハラスメントも、企業が注意を払うべき危機の1つです。
企業が注意すべき代表的なハラスメントには、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、マタニティハラスメントが挙げられます。
ハラスメントは加害者である従業員だけの問題ではなく、適切に対処しなかった企業としても責任を問われ得るものです。
反社会的勢力との関与
企業は、反社会勢力との関与を避けなければなりません。
万が一、取引関係にある相手が反社会的勢力であることが判明した場合や反社会的勢力から不当な要求を受けた場合などには、早急かつ適切な対応が求められます。
不適切広報によるSNSなどでの「炎上」
昨今、SNSでの「炎上」も企業にとって無視できない危機の1つです。
特に、不適切な広報が「炎上」の原因である場合、企業イメージが大きく低下し顧客が離反する事態ともなりかねません。
危機管理対応を弁護士に依頼する主なメリット
危機管理対応は社内で行うこともできる一方で、弁護士に依頼するメリットは小さくありません。
ここでは、危機管理対応を弁護士に依頼する主なメリットを4つ解説します。
危機管理対応を任せられる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
- 危機に対する的確な調査が実現できる
- 法令を踏まえた適切な対応が可能となる
- 不適切な会見による影響の長期化を避けやすくなる
- 訴訟や捜査機関への対応を任せられる
危機に対する的確な調査が実現できる
1つ目は、危機に対する的確な調査が実現できることです。
適切な危機管理対応をするには、その「危機」に関する事実や原因などを調査しなければなりません。
しかし、危機への調査には注意すべき点も多く、対応や調査手順を誤ると証拠が隠滅されるなどして事実関係の把握が困難となるおそれもあります。
また、発生したのが組織ぐるみの問題であると疑われる危機である場合、社内だけの調査ではステークホルダーからの納得が得づらいでしょう。
弁護士が第三者委員会を設置するなどして調査をすることで、企業が膿を出し切ろうとしているとのメッセージともなり、再起を図りやすくなります。
法令を踏まえた適切な対応が可能となる
2つ目は、法令を踏まえた適切な対応が可能となることです。
弁護士は法律のプロフェッショナルであり、危機が生じた状況に応じた的確な対応を実現できます。
たとえば、生じた危機の内容に応じて各行政機関に法令で求められる届出をしたり、企業を適法な状態とするための対応の助言をしたりすることなどが挙げられます。
不適切な会見による影響の長期化を避けやすくなる
3つ目は、不適切な会見による影響の長期化を避けやすくなることです。
企業に不祥事などの危機が生じた場合、記者会見など初期の対応に問題があると、事態は収束するどころか顧客や投資家などが離反し影響が長期化するおそれが生じます。
危機管理対応の実績が豊富な弁護士は、単にリーガル面でのサポートだけをするわけではありません。
模擬記者会見を行い、想定される質問への対応を検討したり、記者会見に同席をして経営陣をサポートしたりすることなども可能であり、これにより不適切な会見を避けやすくなります。
訴訟や捜査機関への対応を任せられる
4つ目は、訴訟や捜査機関への対応を任せられることです。
危機が生じた場合、訴訟を提起したり訴訟を提起されたりする場合があります。
たとえば、製品事故など直接的な被害者のあるものである場合、被害者側からの損害賠償に関する訴訟が提起される可能性があるほか、株価を引き下げる内容の危機であれば投資家などから経営陣の責任を追及される可能性もあるでしょう。
また、特別背任などの場合、企業側から行為者に対して訴訟を提起することもあります。
さらに、横領事件などの場合には捜査機関が関与する場合も多く、企業としても捜査機関への協力などの対応が必要となるでしょう。
弁護士に依頼する場合にはこれらへの対応を任せられるため、的確な対応が実現できるほか、自社のリソースを圧迫しづらくなります。
危機管理対応に関して弁護士ができる主なサポート
危機管理対応に関して、弁護士にはさまざまなサポートが期待できます。
ここでは、弁護士による主なサポート内容を紹介します。
- 企業刑事弁護
- 行政機関対応
- 第三者委員会の設置支援・事実関係調査
- 記者会見対応支援
- 訴訟対応
- 従業員への懲戒対応
- 内部統制システムの整備支援
- コンプライアンス研修講師
なお、具体的なサポート内容は依頼する弁護士によって異なる可能性があります。
そのため、実際に危機管理対応について弁護士に依頼しようとする際は、あらかじめ対応可能な範囲を確認しておくことをおすすめします。
危機管理対応に強い弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までご相談ください。
企業刑事弁護
弁護士は、企業の刑事弁護をサポートします。
企業に生じた危機の内容によっては、企業や役員、従業員が捜査機関から捜査や訴追を受け、刑事責任を追及されることがあります。
このような際、弁護士は刑事責任を軽減するための弁護活動を行います。
弁護士に依頼することで、企業の刑事責任を最小限に抑え、事業活動への影響を軽減できます。
行政機関対応
弁護士は、行政機関対応をサポートします。
危機の内容によっては、各業法に基づいて行政機関から調査を受けたり、行政処分の対象となったりする場合があります。
行政処分の幅は非常に広く、行政指導に留まることもあれば、企業名の公表や業務停止命令、許認可の剥奪、課徴金の賦課など事業に多大な影響が及ぶ処分がなされる可能性も否定できません。
弁護士のサポートを受けることで、行政処分の回避や軽減を図り、企業への負担を減らすことが可能です。
第三者委員会の設置支援・事実関係調査
弁護士は、第三者委員会の設置支援や事実関係調査の支援を行います。
企業が危機に適切に対応するためには、的確な調査が不可欠です。
調査が不十分であると、事実関係が把握しきれずに危機の種を除去しきれないおそれがあるほか、ステークホルダーに対して納得のいく説明をすることもできません。
弁護士に依頼することで、徹底した調査を実施し、企業にとって有利な説明責任を果たすことが可能になります。
記者会見対応支援
弁護士は、記者会見の対応を支援します。
生じた危機の内容に応じて、企業にはマスコミへの対応や記者会見の実施、コメントの公表などが求められます。
これらの対応に問題があると、企業の信用がさらに失墜し、企業価値が大きく毀損する事態にもなりかねません。
弁護士にサポートを依頼することで、適切なマスコミ対応を実施し、企業の信頼回復を図ることが可能になります。
訴訟対応
弁護士は、訴訟対応を行います。
危機の内容によっては、企業が訴訟を提起したり、反対に訴訟を提起されたりする場合があります。
弁護士に依頼することで、訴訟に関する戦略を練り、企業のリスクを最小限に抑えることができます。
従業員への懲戒対応
弁護士は、従業員への懲戒対応を支援します。
横領事件やインサイダー取引、ハラスメントなど従業員が主体となって企業不祥事を引き起こした場合、その従業員への懲戒処分を検討することとなります。
しかし、懲戒処分をするには、原則として就業規則や懲戒規定などに根拠規定を設けている必要があります。
また、規定があったとしても行為の内容と比較して処分が重過ぎると判断されれば、対象の従業員から処分の無効を主張されてトラブルとなるおそれもあるでしょう。
弁護士に依頼することで、事案に応じた適切な懲戒処分の内容についてアドバイスを受けたり、対象の従業員との面談に同席してもらったり、面談を代行してもらったりするなどのサポートを受けられます。
内部統制システムの整備支援
弁護士は、内部統制システムの構築を支援します。
内部統制システムとは、社内不祥事などのリスクを低減し、企業が健全な企業活動を維持するための仕組みです。
社内で危機が生じる事態を避けるには、内部統制システムの整備が不可欠といえます。
しかし、適切な内部統制システムはその企業の規模や業務内容によって異なるため、画一的に何らかの仕組みを導入しさえすればよいものではありません。
また、内部統制システムを整備する過程では、社内規定や組織体制などを見直すべきことも多いでしょう。
弁護士のサポートを受けることで、自社に合った適切な内部統制システムを構築しやすくなります。
コンプライアンス研修講師
弁護士へは、コンプライアンス研修の講師も依頼できます。
不祥事やハラスメントなどの危機を抑止するには、コンプライアンス研修の実施も効果的です。
コンプライアンス研修の講師は社内の役職員が務めることもできる一方で、弁護士に依頼することもできます。
弁護士に講師を依頼することで、法令や最新事例を交えた研修を実施しやすくなります。
まとめ
企業には、会計不正やデータ不正、製品事故、個人情報の漏洩など、さまざまな危機が生じる可能性があります。
社内で万が一危機が生じてしまった際に備えて、危機管理対応に強みを有する弁護士を見つけておくとよいでしょう。
危機管理対応を弁護士に依頼することで、的確な社内調査やマスコミ対応などが実現でき、事業への影響を最小限に抑えやすくなります。
また、訴訟や捜査機関への対応なども任せられるため、危機管理対応にあたって社内のリソースを圧迫しづらくなります。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、危機管理対応への実績豊富な弁護士が的確な対応を支援します。
危機管理対応について相談や依頼ができる弁護士をお探しの際は、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。