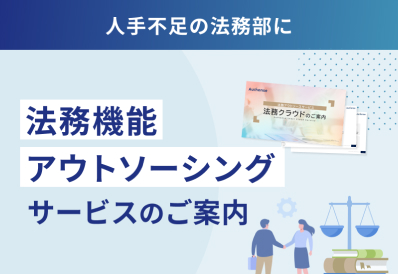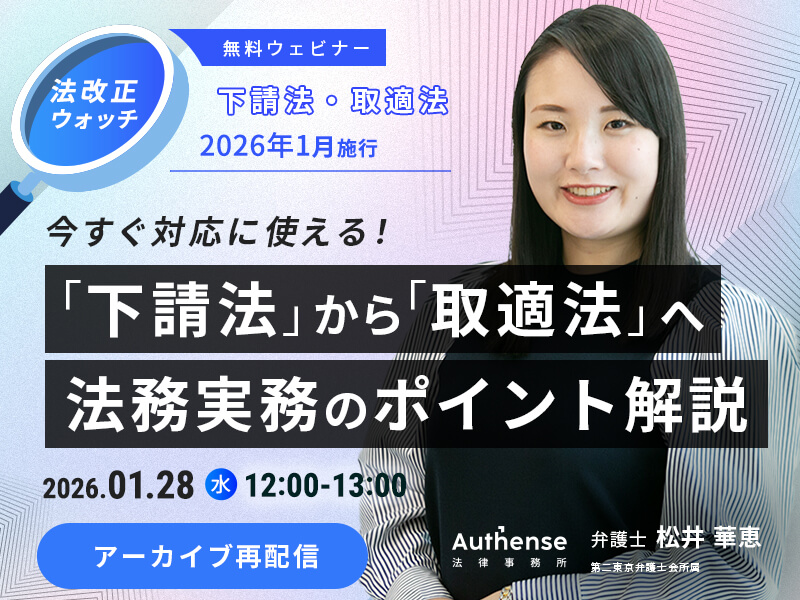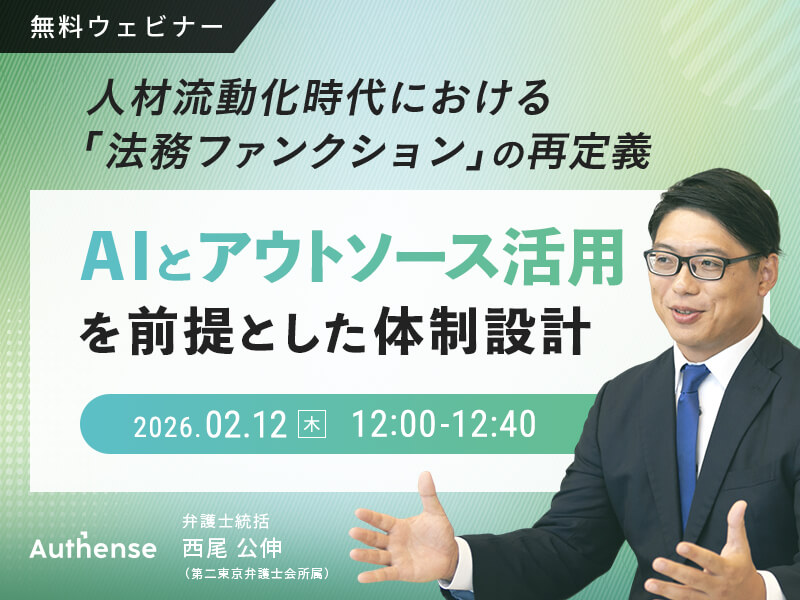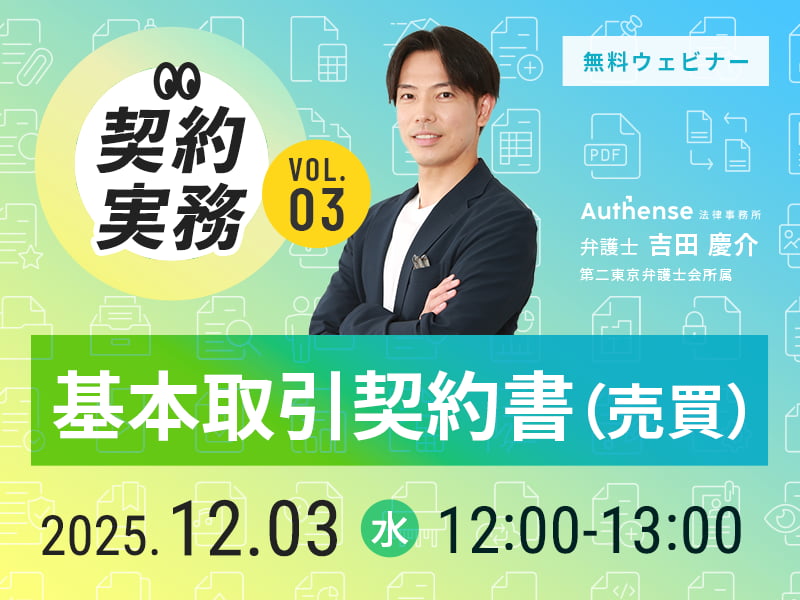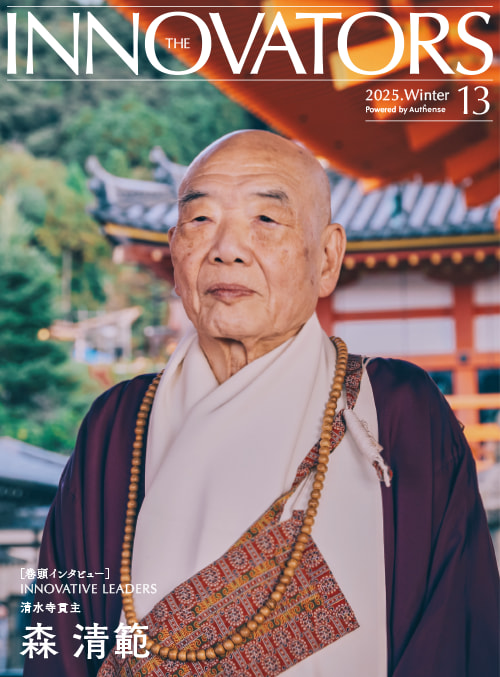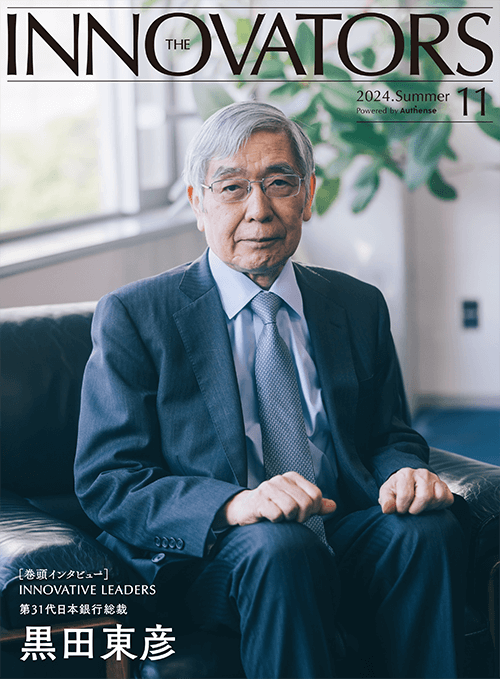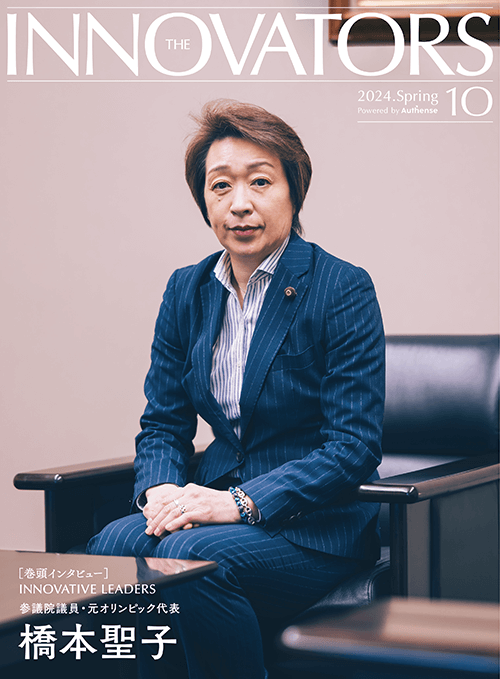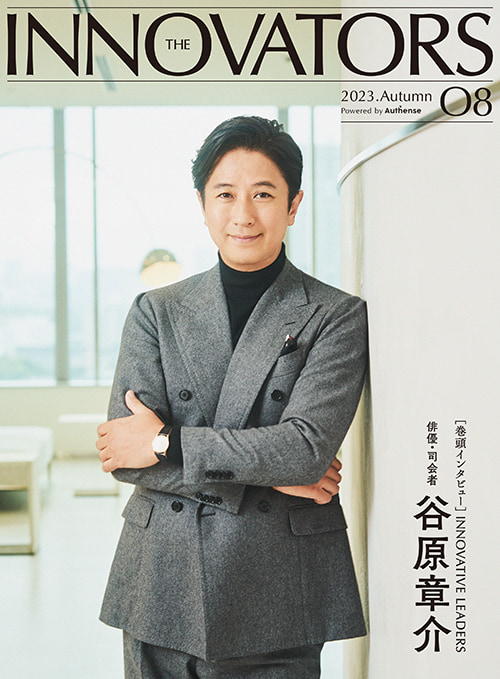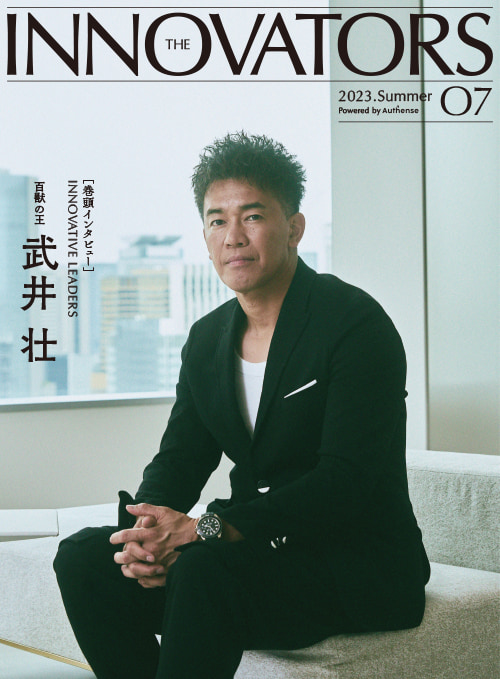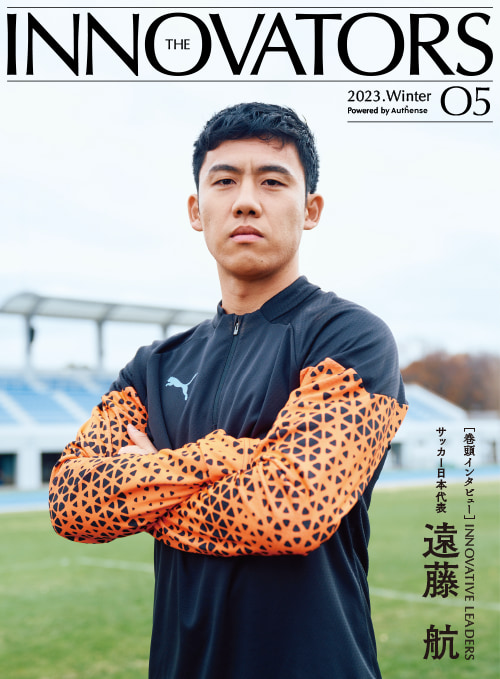社内で品質不正や検査偽装、製品事故が起きると、企業にとって多大な影響が生じ得ます。
では、品質不正や検査偽装、製品事故は、どのような原因で起きるのでしょうか?
また、これらが生じるのを避けるためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、品質不正や検査偽装、製品事故の概要や品質不正などが生じる原因、品質不正などを避けるための対策などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当法律事務所「Authense法律事務所」は企業法務に特化した専門チームを設けており、品質不正や検査偽装、製品事故に関するご相談も数多くお受けしています。
品質不正などを避ける体制を整備したい際や、自社で品質不正などが生じてお困りの際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。
目次
<メディア関係者の方>取材等に関するお問い合わせはこちら
品質不正・検査偽装・製品事故の概要
はじめに、品質不正と検査偽装、製品事故について、それぞれ概要を解説します。
品質不正とは
品質不正とは、その製品が備えているべき性能を実際には備えていないにもかかわらず、その性能を備えていると偽る行為です。
法令が定めている基準を満たしていないにもかかわらずその旨を隠して流通させる場合のほか、自社が公開しているパンフレットなどに表示した品質を満たしていない製品を流通させる場合があります。
検査偽装とは
検査偽装とは、検査結果を偽装する行為です。
製品の品質に関する検査結果の改ざんは、検査偽装であると同時に、品質不正にも該当します。
また、製品そのものに関する検査結果ではなく、工場から排出されるCO2などの測定結果を偽装して自治体などに報告するものもこれに該当します。
製品事故とは
製品事故とは、製品によって一般消費者の生命や身体に危害が発生することです。
製品が本来有しているべき安全性を備えていないと、消費者の安全が脅かされることとなりかねません。
製品事故は予期せぬ不具合によって発生することもある一方で、品質不正の結果として生じることもあります。
品質不正や検査偽装、製品事故が起きる主な原因
品質不正や検査偽装、製品事故は、どのような原因で生じるのでしょうか?
ここでは、これらが生じる主な原因について解説します。
企業内の風通しの悪さ
1つ目は、企業内の風通しの悪さです。
社内の風通しが悪い場合、品質不正などが生じやすいうえ、実際に生じた際にも発覚しづらいといえます。
風通しが悪いと、担当者が企業全体や消費者利益ではなく、自身の目先の利益(「上司から叱られない」など)を重視するおそれが生じるためです。
また、疑問に感じる部分があっても、他部署や上司などに相談することができず、品質不正に手を染めるおそれもあるでしょう。
倫理観の低さ
2つ目は、倫理観の低さです。
企業内に、「品質を多少ごまかしてでも利益を上げる方が大切だ」「多少の品質不正など、どの企業でもやっているだろう」などといった考えが蔓延している場合、品質不正や検査偽装などの問題が生じやすくなります。
このような倫理観が蔓延していると、新たに配属された従業員が問題を提起しても、その従業員側が社内で問題視される事態にもなりかねません。
長年不正が見逃されてきた環境
3つ目は、長年不正が見逃されてきた環境です。
品質不正や検査偽装は、長年の「慣習」として行われている場合もあります。
上司などから「これまでもこのように対応してきた」と指導されると、新たに配属された従業員もそういうものであると考えてこれに倣ってしまう可能性が高いでしょう。
このようなケースでは、具体的に不正であることを指摘されるまで、問題があることを自覚できない可能性もあります。
強いプレッシャー
4つ目は、強いプレッシャーです。
たとえば、発売時期間際となってから最終の検査で満たすべき性能を満たしていないことが判明した場合、本来は発売時期を遅らせて性能を改善したり、法令上の性能でなければパンフレットなどの表記を修正したりするべきでしょう。
しかし、社内に発売時期に間に合わせるべきという強いプレッシャーがあると、性能を満たしていないことを言い出すことができず、そのまま発売してしまう可能性が高くなります。
品質不正や検査偽装、製品事故によって生じ得る主なリスク
品質不正や検査偽装、製品事故が生じた場合、企業にはさまざまなリスクが生じます。
ここでは、主なリスクについて解説します。
- 損害賠償請求がされる
- 製品の回収が必要となる
- 刑事罰の対象となる
- 行政処分の対象となる
- 顧客や取引先が離反する
- 株価が低迷する
損害賠償請求がされる
品質不正などが原因で製品事故が起きた場合、被害を受けた消費者などから企業に対して損害賠償請求がなされる可能性が高くなります。
また、品質不正や検査偽装のある製品を他社に納入していた場合には取引先にも影響が及ぶため、納入先の企業から損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。
さらに、株主から取締役の責任が追及され、会社に対して取締役個人が損害賠償責任を負うべきとされる場合もあります。
製品の回収が必要となる
品質不正や検査偽装が発覚した場合、すでに市場に流通させた製品の回収(リコール)が必要となる可能性が生じます。
これには多大なコストを要するため、業績に大きく影響する可能性があるでしょう。
刑事罰の対象となる
品質不正や検査偽装の内容によっては、刑法上の詐欺罪や不正競争防止法違反などの罪に問われる可能性があります。
これにより、担当する取締役が逮捕されたり有罪判決が下ったりすれば、影響は甚大となるでしょう。
行政処分の対象となる
品質不正や検査偽装などをした場合、内容や事業内容によっては行政処分の対象となります。
行政処分では業務改善命令がなされる可能性があるほか、状況によっては業務停止命令がなされたり許認可が取り消されたりするおそれもあります。
顧客や取引先が離反する
品質不正や検査偽装などが明るみに出ると、その企業の製品に関する信頼が揺らぎ、顧客や取引先などが離反する可能性が生じます。
不正の内容によっては影響が長期に及び、業績回復が難しくなるおそれもあるでしょう。
株価が低迷する
上場会社である場合、品質不正や検査偽装などが明るみに出ると、株価が低迷する可能性が生じます。
株価の低迷が続き業績の回復も困難となれば、上場廃止を余儀なくされる場合もあるでしょう。
品質不正や検査偽装、製品事故の予防策
ここまで解説したように、品質不正や検査偽装、製品事故がひとたび起これば、その影響は甚大なものとなりかねません。
では、自社で品質不正などが起きる事態を予防するには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?
ここでは、主な予防策を5つ解説します。
- 企業として不正を許さない態度を明確にする
- 内部統制システムを整備する
- コンプライアンス研修を実施する
- 内部通報制度を整備する
- 小さな不正も見逃さない
企業として不正を許さない態度を明確にする
1つ目は、企業として不正を許さない姿勢を明確にすることです。
企業が不正を許さないことなど当たり前のように感じるかもしれませんが、従業員が良かれと考え、誤った忖度から品質不正や検査偽装に至るケースは少なくありません。
その結果、重大な製品事故につながり多大な影響が生じてしまえば、目も当てられないでしょう。
企業として不正を許さない態度を明確に示し発信を続けることで、誤った忖度から不正に至る事態を避けやすくなります。
内部統制システムを整備する
2つ目は、内部統制システムを構築することです。
内部統制システムとは、企業が不正行為を避け、適切かつ効率的に運営するための仕組みやルールのことです。
経営陣が従業員を一方的に監視・監督するのではなく、監視・監督の対象が経営陣にも及ぶことが大きな特徴といえます。
品質不正や検査偽装が頻発する場合や重大な不正が長年見過ごされている場合、その企業の内部統制システムは十分に機能していない可能性が高いでしょう。
弁護士など外部の第三者のサポートを受けて内部統制システムを見直し抜本的に改革することで、不正行為が起きづらい企業体質を構築しやすくなります。
コンプライアンス研修を実施する
3つ目は、コンプライアンス研修を実施することです。
品質不正や検査偽装は「企業のために」との誤った忖度から生じることも多く、横領などとは異なり、手を染める従業員として「悪いことをしている」との認識が浅い場合も少なくありません。
コンプライアンス研修を徹底し、個々の従業員が具体的にどのような行為を避けるべきであるのか認識することで、品質不正や検査偽装を避けやすくなります。
研修では、他社で実際に起きた品質不正や検査偽装などの事例や顛末を紹介することで、不正の抑止によりつながりやすくなるでしょう。
内部通報制度を整備する
4つ目は、内部通報制度を整備することです。
内部通報制度とは、社内で起きた不正について、社内の窓口や外部の弁護士事務所に設置した窓口に個々の従業員が通報できる制度です。
内部通報制度では、通報した従業員を特定することや、通報した従業員を、通報を理由に不利益に取り扱うことなどは禁止されています(公益通報者保護法5条)。
なお、公益通報者保護法では、アルバイトなどを含む従業員数が300人を超える企業に内部通報制度の導入が義務付けられていますが、従業員数がこれに満たない企業であっても積極的に制度を導入するとよいでしょう。
内部通報制度を導入することで問題が大きくなる前に社内の不正を把握しやすくなり、早期の是正をはかりやすくなるためです。
また、不正への相互監視が働きやすくなることから、不正行為の抑止力としての効果も期待できます。
小さな不正も見逃さない
5つ目は、小さな不正であっても見逃さないことです。
品質不正や検査偽装が初めから大胆に行われることは稀であり、はじめは小さな不正から始まることが多いでしょう。
これが発覚しなかったことで、悪しき企業風土として定着し、不正が繰り返されることとなります。
そのため、品質不正や検査偽装を避けるには、小さな不正であっても見逃さず厳正に対処することが有効です。
不正について厳正に対処することで不正が繰り返されづらくなり、品質不正などの抑止力ともなるでしょう。
品質不正、検査偽装、製品事故に関して弁護士がお役に立てること
品質不正や検査偽装、製品事故に関して、弁護士はどのようなサポートができるのでしょうか?
最後に、弁護士による主なサポート内容について解説します。
- 企業に合った体制の構築支援
- 内部通報制度の構築支援
- 社内規定の整備
- 研修の実施
- 不正発覚時の対応支援・訴訟対応
なお、ここで挙げたものは一例であり、実際のサポート内容は状況やクライアントの要望などによって異なります。
企業に合った体制の構築支援
弁護士は、企業に合った体制構築を支援します。
先ほど解説したように、品質不正や検査偽装などの不正は内部統制システムが十分に機能していないなど、体制の不備によって起きることも少なくありません。
弁護士が外部の視点から体制整備をサポートすることで、不正が起きづらい企業体質を構築しやすくなります。
内部通報制度の構築支援
弁護士は、内部通報制度の構築を支援します。
内部通報制度を導入しようにも、何から手を付ければよいのか、またどのように運用すべきかわからないことも多いでしょう。
弁護士のサポートを受けることで、適切な内部通報制度の導入が可能となります。
社内規定の整備
弁護士は、社内規定の整備を支援します。
たとえば、社内で発生した品質不正や検査偽装に起因して従業員を懲戒処分するには、懲戒規程が整備されていなければなりません。
懲戒規程に不備があると、懲戒処分が困難となります。
また、内部統制システムの構築にあたっては、社内整備の改訂を伴うことも多いでしょう。
弁護士は、企業の規模や成長ステージに合った社内規定の整備をサポートできます。
研修の実施
弁護士へは、研修の講師を依頼することも可能です。
品質不正が起きづらい体制を構築する中で、コンプライアンス研修の実施を希望する場合も多いでしょう。
弁護士に講師を依頼することで、法令に沿った的確な研修が可能となるほか、最新事例を交えた研修が可能となります。
不正発覚時の対応支援・訴訟対応
弁護士は、不正発覚時の対応や訴訟対応を支援します。
自社で品質不正や検査偽装が発覚したり、製品事故が発生したりした際には、各所へのスムーズな対応が必要となります。
また、提起された訴訟に対応すべき場面や、反対に訴訟を提起すべき場面などもあるでしょう。
弁護士は状況に応じた最適な対応を支援するため、安心してお任せいただけます。
品質不正や検査偽装、製品事故の対策・対応はAuthense法律事務所へご相談ください
品質不正や検査偽装、製品事故は頻発しており、どの企業であっても他人事ではありません。
経営陣は自社で不正など起きるはずがないと考えていても、現場では小さな不正が繰り返されている可能性もあります。
品質不正や検査偽装などを避けるため、企業としては不正を許さないとの姿勢を明確に示すとともに、弁護士のサポートを受け自社の体制を見直すとよいでしょう。
Authense法律事務所は企業法務に特化した専門チームを設けており、品質不正や検査偽装、製品事故などに関するご相談・サポートについて豊富な実績を有しています。
自社で品質不正などが発覚してお困りの際や、品質不正などを避ける体制を構築したい際などには、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。